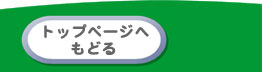|
���Â̒n��C�Ӎ������c��@��R���c�L�^
�P�@�J�Ó����@�@�@����15�N 9 ��22���i���j�@�ߌ�3��
�Q�@�J�Ïꏊ�@�@�@���p�s�c��@�S�����c�
�R�@�o�Ȏҁ@�@�@�ψ��E�E�E�E�@14���i�S���o�ȁj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���S���ҁE�@���ʑ����������A���c�����������i���p�s�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؑ��������������A�R���������ێ�C�i���⒬�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ǁE�E�E�@�������v�A�����N�i�A���}���F�L�A���c��
�S�@��c����
�Z��
�@(1)�@��10���@�@���������̎��g�ݏɂ���
�Z���c
�@(1)�@���c�đ�10���@�@�V�s�����\�z�i�āj�ɂ���
�@(2)�@���c�đ�11���@�@�����V�~�����[�V�����i�ꎟ���Z�j�ɂ���
�T�@��c�L�^
�i���ʑ��������j����������A��3�Â̒n��C�Ӎ������c����J������܂��B��낵�����肢�\���グ�܂��B�܂����߂ɓ����c��̉�ł��鍲�����p�s����育���A�Ղ������Ƒ����܂��B
�i������j�ψ��̊F�l�ɂ͑�ς��Z�������A���o�Ȓ����܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�C�Ӎ������c�������łR��𐔂��܂��B�����e�n�̍������c��͕̏��Ă���Ƃ���ɂ��܂��ƁA���ɍ����Ɍ��������ɘb���������i�W���Ă���Ƃ��낪�������ŁA�l�X�ȕǂɓ˂��������ē�q���Ă���Ƃ����ӂ��Ȓn��������A��ϓ���ȂƂ����ӂ��Ɋ����Ă���Ƃ���ł������܂��B���̓x�A�V�s�̏����\�z�Ăƍ����V�~�����[�V�����̑�ꎟ���Z���܂Ƃ܂����Ƃ���ł������܂��B�����ɂ��ẮA�\�z���Ă���܂������̂̏����I�ɂ͔��Ɍ������\�z���ʂ��o�Ă���܂��B�Z���̕��X�����S���čK���Ȑ������ł���A�����Ă܂����͂���܂��Â���̂��߂ɂ����Č��ɑ��Ċ����Ȃ����c���A�����Ă܂��M�d�Ȃ��ӌ�������܂��悤�ɂ��肢�\���グ�܂��Ĉꌾ�����A�ƒv���܂��B
�@
�i���ʑ��������j���肪�Ƃ��������܂����B���ɁA�c���ɓ��肽���Ǝv���܂��B�c���́A���c��K���7���4���ɂ��A������߂邱�ƂƂȂ��Ă���܂��B�������낵�����肢�������܂��B
�i������j����ł͂��ꂩ���3�c����J�Â������܂��B�c���̐i�s�ɂ��܂��ẮA�~���ɐi�߂��܂��悤�����͂����肢�\���グ�܂��B�Ȃ��A���������ꍇ�͋���̂�����������������悤���肢�������܂��B�܂��A�����ǂ��o�Ȉψ��ɂ��ĕ肢�܂��B
�i���������ǒ��j�{���̏o�Ȉψ��͑S�ψ�14�����o�Ȃ���Ă���܂��B�葫���ł���ߔ��������Ă���܂��̂ŁA��c���������Ă��邱�Ƃ����������܂��B
�i������j���ɁA��c�^�����l�̑I�o�ł����A���c���c�^�c�K����5���3���ɂ��c�����w�����邱�ƂƂȂ��Ă���܂��B�{���̋c���^�����l�́A�ޗǁ@��O�Y�ψ��A�H�{�@��s�ψ��̂���l�ɂ��肢�������܂��B������c���Ɉڂ点�Ă��������܂��B��10���u���������̎��g�ݏɂ��āv�����ǂ����������肢���܂��B
�i���������ǒ��j�܂��n�߂ɁA����̋��c��̋��c�����̔z�z�ɂ�����܂��ĕs��ۂƐ\���܂����A����킵���_������܂������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B����17���ɂ��͂��������܂��������̂����̍����V�~�����[�V�����ꎟ���Z�ɂ��܂��ẮA���̑����̍������c��̗p���Ă��鎎�Z�ɂ������Ă̑O�������������Ď��Z�������̂ł���܂��B��َs����s�O���̍������c��̍����V�~�����[�V�����Ƃ����Z�l�͈قȂ�܂�����ǂ���r���₷���_���l�������O������Ŏ��Z�������܂����B�{���ł���A���̎��Z��������ł����c������������ŏC���Ȃǂ��s���Ĉψ��̊F�l�ɂ��͂����Ȃ���Ȃ�܂���ł������A����c��������Ƃ̒��������������̊J�Â�19���ƒx���Ȃ��Ă��܂��܂����B������ɂ����܂��Ēn����t�ł�������������A���ʌ��ݎ��Ɣ��15�N�x���Z�����݂ŌŒ肷��O��Ƃ��Ă�����z�����ʌ��ݎ��Ɣ�����̗��Ō��������Ď��Z���ׂ��ł͂Ȃ����B�܂��A�������Ȃ邩�s�����ȗՎ�������������������ł���B�����܂Ȃ��ꍇ�����Z���K�v�ł͂Ȃ����B��̃p�^�[���ŌŒ肷����O��������قȂ镡���̃p�^�[���������������c���������Ă��悢�̂ł͂Ȃ����B�Ƃ������Ƃ���}篁A��̃p�^�[���ŃV�~�����[�V��������������lj��ł��͂������Ă��������܂����B����ď����̒x��Ȃǂ��畴��킵�������̔z�z�ɂȂ�܂������Ƃ��d�˂Ă��l�ѐ\���グ�܂��B
����ł́A��10���ɂ��Ă����������Ă��������܂��B�O��̋��c��ł��\���グ�܂����Ƃ���A�V�s�����\�z�̍���A�����V�~�����[�V�����A�������ƈꌳ���A�d�Z�V�X�e���̓����Ɋւ��钲�������{���Ă���܂��B
�V�s�����\�z�ɂ��ẮA��قǓ��e���������������܂����A����9��12���Ɏ������x���ł���܂����S���҂ɂ���敪�ȉ���J�Â��A�n��̊T���A���ꂩ��ۑ�ƍ����̕������A��v�s���̏������ʂ����ɂ��ċ��c���s���Ă���܂��B
�����܂��č����V�~�����[�V�����ɂ��܂��Ă��A8��27���y��9��12���ɓ��l�ɗ��s�������S���҂ɂ��܂��������ȉ���J�Â��A�ϑ��Ǝ҂����Z�����f�[�^�������E�C���������̂����Ɏ��Z�Ɋւ��O������̍l�����A���ꂩ�玎�Z���l�ɂ��ċ��c���s���Ă���܂��B
�������ƈꌳ���ɂ��܂��ẮA8��25���̌ߑO�ɏ��⒬�ŁA�����ߌ�ɂ͎��p�s�ɂ����āA���s���̎������Ƃ��r���鎖�����ƌ��������̎��{���@�ɂ��āA���s���̐E���ɑ��Đ�������s���Ă���܂��B�����Ԃ��Ȃ������͏I������\��ƂȂ��Ă���܂��B���̌�A�\�̍쐬�A��r�\�̍쐬��i�߂Ă܂���܂��B
�d�Z�V�X�e���̓����Ɋւ��钲���ɂ��܂��ẮA7��30���A9��4���ɓd�Z���ȉ���J�Â��A�d�Z�V�X�e���̈Ⴂ�ɂ��ċ��c���s���Ă���܂��B
9��19���ɂ́A���s���̏����A�����y�эL��s���g���̎����ǒ��ō\���������܂���������J�Â��A�{���̋��c��ł̋��c���e�ɂ��Ă��c�_���������Ă���܂��B
�ȏ�ȒP�ł͂������܂����A���������̎��g�ݏɂ��ĕ��I���܂��B
�i������j��10���̐������I���܂����B�������ⓙ������܂����炲�����肢�܂��B
�������܂��B
�@�Ȃ��悤�ł��̂ŁA��10���ɂ��Ă̔����́A����őł���Ƃ������܂��B�����āA���c�ɓ���܂��B���c�đ�10���u�V�s�����\�z�i�āj�ɂ��āv�����ǐ����肢�܂��B
�i���������Lj��j����ł͋��c�đ�10���u�V�s�����\�z�i�āj�v�ɂ��Đ����������Ă��������܂��B�悸�A�ڎ����J���Ă������������Ǝv���܂��B
�@����������܂��̂́A�ڎ��Ō����܂��Ə��ɂ����ĂP�����̔w�i�ƕK�v������S�����\�z�̍�����ԁA�T���p�n��̊T���̂Ȃ��ł�1�ʒu�Ǝ��R�I�����`5��ʖԁA�U���p�n��̉ۑ�Ɣ��W�̕������ɂ��܂��Ă�1�l���̓������猩���n��I�ۑ�ւ̑Ή��`9�n�������̐��i�ƍs������Ղ̋����A�V�V�s�܂��Â���̏������Ɗ�{�I�Ȑ��������ł�1��v�w�W�̏������ʂ��܂łł������܂��B
�@�V�V�s�܂��Â���̏������Ɗ�{�I�Ȑ��������A2�V�s�܂��Â���̗��O�Ə������A3�V�s�܂��Â���̊�{�I�����A4�V�s�܂��Â���̐헪�I�v���W�F�N�g�ɂ��܂��ẮA����̋��c��ł��������邱�ƂƂȂ�܂��̂ł������������������Ǝv���܂��B
�@�Ȃ��A�W�����V�~�����[�V������ꎟ���Z�ɂ��܂��ẮA���c�đ�11���Ƃ��Č�قǐ����������܂��B����ł́A����ǂ��Đ����������܂��B
�@�͂��߂ɁA�u���ɂ����āv�ł������܂����A1�y�[�W����3�y�[�W�������肢�܂��B
�@�����ł́A�P�����̔w�i�ƕK�v���Ƃ��āA(1)�ō������Ƃ�܂���ʓI�ȎЉ�I�o�ϓI�������q�ׁA(2)�����̕K�v���̕����ł́A���ʂ̉ۑ�������p�s�Ə��⒬���n��o�ς̊�ՂÂ���̂��ߋ��Ɏ���g����K�v�����邱�ƁA�������̊g��ƏZ���j�[�Y�̑��l���E���x���ւ̑Ή��Ƃ��āA���݂Ɉˑ��������Ȃ����̓I�Ȑ��������`�����Ă���n��Ƃ��āA�L��I�ϓ_�ɗ������傫�ȃX�P�[���ŁA���A�n��̌����������Ȃ���A����ɑΉ����Ă����K�v�����邱�ƁA���q����̐i�W�ɔ����Љ�\���̕ω��ւ̑Ή��Ƃ��āA�l�I�E�����I�Ȋ�Ղ̐����E�[����}�邽�߁A�n���ۂƂȂ�����g�݂����߂��Ă��邱�ƁA�n�������̐��i�ƍs������Ղ̋����Ƃ��āA�n��������S���A�n��̎����I�Ȕ��W��}��A��̓I�E�����I�ȍs���^�c���\�ɂ��邱�ƁA�ȏ�4�̊ϓ_���獇���̕K�v�����q�ׂĂ���܂��B
�@������2�ŏ����\�z�̍����|�A3�ŏ����\�z�̍\���ɂ���4�ŏ����\�z�̌v����Ԃ�17�N�x���畽��27�N�x�܂ł̊T��10���N�Ƃ��邱�Ƃɂ��ċL�q���Ă���܂��B
�@���ɁA�T���p�n��̊T���ɂ��Ăł������܂����A4�y�[�W����15�y�[�W�������肢�܂��B
�@�͂��߂ɂP�ʒu�Ǝ��R�I�����ł́A(1)�ʒu�ƒn���A(2)�C��A(3)�ʐςƓy�n���p�ɂ��āA���v���l��������������Ă���܂��B
�@������2���v���A���j�I�o�܂��j���Ɋ�Â��Đ������A3����I�Ȑ����s�����ƈړ����ł́A(1)�ʋΌ��A(2)�ʊw���A(3)�����A(4)�ړ����ɂ��āA���v���l���痼�s������̓I�Ȑ��������`�����Ă��邱�Ƃ�������Ă���܂��B
�@4�Љ�I�o�ϓI�T���ł́A(1)�l���E���сA(2)�Y�ƕʏA�Ɛl���A(3)�Y�ƕʏ����Y�z�A(4)�s�������z�����A(5)�����ɂ��āA��������v���l�����猻��͂��Ă���܂��B
�@5��ʖԂł́A�������H�ԁA������ʋ@�֓��̏ɂ��Đ������Ă���܂��B
�@���ɁA�U���p�n��̉ۑ�Ɣ��W�̕������ɂ��Ăł������܂����A16�y�[�W����21�y�[�W�������������������Ǝv���܂��B
�����ł́A�T�ł̌��͂���A�V�s�̂܂��Â���Ɍ��������p�n��̉ۑ�Ɣ��W�̉\�����܂Ƃ߂Ă���܂��B
�@1�ł͐l���̓��Ԃ���݂��n��I�ۑ�ւ̑Ή��Ƃ������ƂŁA���p�n��͉ߑa���A���q����A�j�Ƒ������i��ł������A�����ɑΉ��������ߍׂ��Ȏ{���߂��Ă��邱�Ƃɂ���(1)�`(3)�ŏq�ׂĂ���܂��B
�@17�y�[�W�����2�ł͒���Ă���Y�Ƃ̐U���Ƃ������ƂŁA��1���Y�Ƃɂ��Ă͌X�̔_�Ƃ̎��Ԃ����ɂ߁A�I�ʂ��āA���ߍׂ��Ȏ{����u����K�v�����邱�ƁA��2���Y�Ƃɂ��ĐV�������͂���ٗp���̑n�o�E������}��K�v�����邱�ƁA��3���Y�Ƃɂ��Ắu�\�a�c�E�������v�ό�����u���p�v�ό��ւ̓]����}��K�v�����邱�Ɠ���(1)����(3)�ɂ����āA���ꂼ��L�q�����Ă���܂��B
�@19�y�[�W�̂ق��ł����A3�ł͐��Y���̌���ƕt�����l�̑n�o�ɂ��s�����z�����̌���ɂ��āA4�ł͗��n�������������������E�|�p�̖ʂł̍L��I�Ȍ𗬂�ڎw�����܂��Â���A5�ł͖��͓I�Ȏs�X�n�����Ə��Ƃ̊������A6�ł͂܂��Â���ւ̌�ʖԂ̊��p�Ɛ�����Ԃɔz���������H�����A21�y�[�W��7�ł͂����₩�ň��S�ł��镟���T�[�r�X�̊m���A8�ł͗��j��Y�E�n�敶���̓`���̕K�v���A9�ł͍s�������v�ɂ��s�����^�c�̌������Ƃ��̊�Ջ����̕K�v���ɂ��āA���ꂼ��L�q���Ă���܂��B
�@���ɁA�V�V�s�܂��Â���̏������Ɗ�{�I�Ȑ��������ɂ��Ăł���܂����A22�y�[�W����27�y�[�W�������肢�܂��B
���̏͂ɂ��܂��ẮA�`���\���グ�܂����悤�ɁA�{���������܂��̂́A1��v�w�W�̏������ʂ��݂̂ƂȂ�܂��B
�@�l���ɂ��ẮA�R�[�z�[�g�v���@�ɂ��܂��ƁA17�N��̕���32�N�ɂ�����{�n��̐l���́A30�C700�l�Ɨ\�z����Ă���܂��B
�@24�y�[�W�A���ѐ��ɂ��ẮA�g�����h���v�ɂ��A����32�N�ł�16,200���сA���т��\������Ƒ�����2.17�l�Ɨ\�z����Ă���܂��B
�@�Y�ƕʏA�Ɛl���ɂ��ẮA�g�����h���v�ɂ��܂��ƁA����32�N�ɂ͏A�Ɛl�����}�C�i�X�ƂȂ�܂��̂ŁA������̏A�Ɨ���50���A��1���Y�Ƃ̏A�Ɛl���䗦��10���A��2���Y�Ƃ̏A�Ɛl���䗦��35���A��3���Y�Ƃ̏A�Ɛl���䗦��55���ƌ�����ŁA���v�l���Ɋ�Â��A����32�N�ł́A��1���Y��1,800�l�A��2���Y��6,200�l�A��3���Y��9,700�l�Ɛ��v���Ă���܂��B�Ȃ��A�����̐��l�́A����̎{���@���ɂ���đ傫�����E����邱�Ƃ�t�L���Ă���܂��B
�@26�y�[�W�ł������܂����A�Y�ƕʎs�������Y�z�ɂ��ẮA�A�Ɛl���䗦�Ɠ��l�̗��R����A����12�N�̎��ђl�����ƂɁA�A�Ɛl��1�l������̏����Y�z���Y�ƕʂɋ��߁A����������̏A�Ɛl���ɏ悶�Đ��v���Ă���A����32�N�ł́A��1���Y��30���~�A��2���Y��191���~�A��3���Y��581���~�A�v802���~�Ɨ\�z���Ă���܂��B
�@27�y�[�W�ł������܂��B�s�����z�����ɂ��ẮA���p�s��������X���ɂ���܂����A���⒬�����Ȃ�L�тĂ���܂��̂ŁA���p�s�̌��������J�o�[����`�Ő��ڂ���ƍl���A���݂̂Ƃ��땽��32�N�ɂ�320���~�ɂȂ�Ɛ��v���Ă���܂��B
�@�Ȃ��A���⒬�̐L�т��ꎞ�I�Ȃ��̂Ȃ̂��A��������̌X���������̂��ɂ��ẮA����13�N�x�̐��l���o���i�K�ōČ��������ƍl���Ă���܂��̂ŁA����ɂ����Ď�̏C������������ꍇ�����邱�Ƃ����f�肢�����܂��B�ȏ�A�u�V�s�����\�z�i�āj�v�̐������I���܂��B
�i������j�������܋��c�đ�10���̐������I���܂����B���̋��c�Ă��܂��āA������A���ӌ�������܂����炲�����肢�܂��B
�i�����ߗY�ψ��j3��ǂ܂��Ē����܂������A���p�n��̊T���̐��m�ȑ����������Ă���Ƃ������Ƃ���ۂɎc��܂����B���̏�Ŏ��p�n��̉ۑ�Ɣ��W�̕������͊T�˓K�ȑΉ����N���Ă���Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɋ����܂����B
�i������j���ɂ������܂��B
�i���������Y�ψ��j���A������������b����܂����悤�ɁA���̌��́A�����Ă܂��A�ۑ�ɂ��Ă͂��̉ۑ�̒���������V�s�̏����\�z����N����Ă���̂ł͂Ȃ����ȂƂ����C�����Č����Ē����܂������A������f�������̂ł����A�s�������z�����̐��ځA���̎��p�s�Ƃ��ꂩ��27�y�[�W�A13�y�[�W�ɂ��܂��Ă͓��Ɏ��p�s�̏ꍇ�͓��v���ɖ��N�o���Ă��Ă��鐔�l�ƈقȂ鐔�l���f�ڂ���Ă���킯�ł����A����ɂ��Ă͂ǂ����������킯�ł����B
�i���������Lj��j13�y�[�W�̎s�������z�����̐��ڂɂ��܂��ẮA�����̂ق��Ŏ��p�s�̓��v����14�N�x�ł��o�ĂȂ��̒��ŏH�c���s�������������v���v�̔N����ϑ��Ǝ҂ł���܂����@�K�Ɏ������܂����W�����A���l�����v�����Ƃ���Ă���_�͂������܂��B�s�������z�����ɂ��Ă͂����̂ڂ��ďC�������������肷����̂ł����獡��ɂ����܂��ẮA���������̌X���͂���ł����Ă��邩�Ǝv���܂����A�ŐV�̐����ɍ���������悤�ɂ������Ǝv���܂��B
�i���������Y�ψ��j14�N�ł̐��l�ƒ����˗��������l�͈Ⴄ���̂��Ƃ������Ƃ͗������܂����A��قǎ����ǂ���������������s�����z�����̏����\�z�A���⒬�̂ق��������ȐL�т������Ă����Ď��p�s�̕����J�o�[�ł���ƁA2.09���̐��l����������͏ڂ����������Ă��܂���ǂ��A���̎��p�s�̏ꍇ��7,8,9����12�N�܂őΑO�N9�N10�N�����������ŁA���Ƃ͑ΑO�N�����ƃ}�C�i�X�X���ő��ΓI�ɂ��t��2.0�����炢�}�C�i�X���ƁB���̏���Ɗ܂߂��Ȃ���2.09���㏸����ƃJ�o�[�ł���Ƃ����\���̐��l�����͔[���ł��Ȃ����l�ŁA���⒬�̕��z�����Ŏ��p�s�̃}�C�i�X2.0�����̓J�o�[�ł��鐔�l����̓I�ɏo����̂��ȂƂ����̂ŁA���Ƃŏo���ꂽ���l�̒��g�������Ă������������̂ł����A���Z�I�Ɍ��������ł͂��̐��l���B���Ȑ��l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����ǐ����ł��܂����B
�i���������Lj��j���̓_�ɂ��܂��ẮA�����̂ق��Ŏ��������i�K�œ����悤�Ȍ����ł����B�����A�����Ŏ�\���グ�܂�������ǂ����⒬�̏����̐L�т���������̂܂܂��̐����Ōp������̂��ǂ����A13�N�x�̐��l�����͂����肵���i�K�Ŏ�A�C����������ꍇ������Ƃ������Ƃł����B���̕ӂ̐��v�̍l�����ɂ��܂��Ă͍����A�Ǝ҂̕������Ă���܂��̂ŁA���̐��l�I�ȂƂ�����܂߂Ď�����������Ă������������Ǝv���܂��B
�i���@�K�j����ł́A���b�����Ă��������܂��B
�܂����̒��Ŏ��Ԃ��������Ă��������܂��ƁA13�y�[�W�A���p�s����̏ꍇ�ł��ƕ���8�N�x����12�N�x�̎s�����z�����ł����A���ꂾ������ƌ������Ă���B����ŁA��������̏��⒬����̒������z�����ł���10�N�x�܂ʼn��~���Ă����āA11�A12�N�x�Ə㏸���Ă���Ƃ������Ƃł��B����ŁA����������ǂ������ނ��A�S�̓I�Ɍ��܂��ƍ��v�ł��̎��Z�̂悤�ɂȂ�܂��B11�N�x�܂Ō����X���ɂ�����12�N�x�ɂ����Ă͑������Ă���B�������Ă���w�i�ɂ́A���⒬����̉e���ɂ���Ĉ�s�꒬�ł���������Ƃ������Ƃ������܂��B���͉��́A���⒬���}���ȑ����X���������Ă��邩�Ƃ������Ԃ�11�N�x����12�N�x�ɂ����Ă��̔w�i�����܂��ƒ������z�����̂�����Ə����ł��邱�Ƃ��킩��܂��B�����m�̂悤�ɕ��z�����ɂ͌ٗp�ҏ����A���Y�����A���{��Ǝҏ���������܂����A���̂����̊�Ə������}���ɑ����Ă��܂��B��ƂƂ����Ă���ꎟ�����O���܂ł���܂����A���������ǂ̎Y�Ƃ������Ă��邩�Ƃ������g�𐄌v���܂��Ƒ�O���Y�Ƃ������Ă��܂��B��O���Y�Ƃ̒��̓��ɕی��A���Z���тɕs���Y�Ƃ����⒬�̏ꍇ�A�}���ɐL�тĂ��܂��B����ł́A����͂ǂ��������ƂȂ̂��A���v�I�ɂ͌�����̂ł�����ǂ��A���ہA�Ⴆ���Z�@�ւ����̎��_�ŗ��n�������̂����邢�͕s���Y�ƂƂ����Ǝ킪����Ȃ̂��킩��܂���B����ǂ��}���ɑ����Ă���Ƃ����̂͂��������w�i�ł��B�ł́A�����������Ԃ��ӂ܂��ď����ǂ������ނ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�傫�ȍl�����Ƃ��Č�������Ƃ����l�����Ɖ����A���ꂩ�珃��������Ƃ����Q�̃p�^�[�����l�����܂��B�ߋ��A5�N�ʂŌ��܂��Ƃ����炭�������邾�낤�ƍl�����܂��B���⒬����̏ꍇ��11�N����12�N�ɂ����Ă��܂�ɂ��}���ȑ����������Ă���킯�ł����A���̎��Ԃ�����ǂ��Ȃ邩�ɂ���đ啪�A�ς���Ă��܂��B�}���ȐL�т���������҂ł���Ƃ������O��̎��Z�ɂȂ��Ă���܂����Ƃ��������������������Ǝv���܂��B
�i������j�ق��ɂ������܂��B
�i�����ߗY�ψ��j19�y�[�W�ł����ǁu�\�a�c�E�������ό��v����u���p�ό��v�ւ̓]���A���ɋ�������c�Ă��Ǝv���܂����B�l���Ă݂܂��Ǝ��R�����Ƃ��Ă̏\�a�c�E�������ƂȂ�Ɣ͈͂��L������̂ł͂Ȃ����A�ŋ߁A�p�ْ��̕��Ɖ��~�̊ό��A����͂������V�����u���܂��v�̉e�����傫���킯�ł����ό��q�͑����̈�r�ɂ���Ǝv���܂��B���ꂩ��̊ό��Ƃ����̂́A��͂���j�E�����E�H�E�����A���ɉ���ł��ˁB�����𒆐S�ɂ����ό����嗬�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B���̒�Ă͍L���c�_���Ă݂�K�v������B���͑O�����ɂ���Ɏ^�����Ă݂����Ƃ����C�����ł��B
�i�r�c�ψ��j�������܂̈�������̔����Ɋ֘A���܂�����ǁA���̒��Łu�\�a�c�E�������v�ό�����u���p�ό��v�֓]����}���Ă����Ƃ������̒��g�͂ǂ��������g�ł����B
�i���������ǒ��j��̓I�Ȓ��g���͂�����Ɛ\���グ��Ƃ������Ƃ͓���킯�ł����A�����鍡�܂ł̏\�a�c���������R�����ɑ傫���ˑ������悤�Ȋό��Ƃ����������p�n��ɂ������قLj����ψ����������Ⴂ�܂������j�E�����E�`�������킹�A�������邢�̓z�X�s�^���e�B�A�������������𑍍̂��I�ɑg�ݍ��킹���ό��A���������Ӗ��Ŏ��p�n�悪��̂ƂȂ��Ď��g�ނƂ����l�������玭�p�ό��Ƃ����\������ꂳ���Ă��������Ă���܂��B������̓I�Ɏ������ƂƂ����̂͂��ꂩ�狦�c���ċ�̓I�Ȑ���Ŕ��f���Ă������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�i�r�c�ψ��j�O�X����\�a�c��������A�g�����ό��ł������Ƃ����b�ł������̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv���̂ł�����ǁA��������A���̊ό��ɂ��Ă͕�������]�����Ă����Ƃ����l���Ȃ̂ł����B���̕ӂ͂ǂ��ł��傤�B
�i���������ǒ��j�����ϊ��Ƃ��������A����܂ł��\�a�c���������������𒆐S�Ƃ����ό��U����}���Ă��܂������A�ˑR�Ƃ��Ă��̑ؗ����Ƃ��A�����������_�Ŋm���Ɋό����s���邢�͊ό������Ƃ��������z�����Ȃ��ł��Ă���܂��B���ꂩ��͏\�a�c�����������������ꂪ���R���S�ƂȂ��Ă����̂ł����A��͂肻���ɒn��ɏZ�ސl���Z�݂₷���A���邢�͊y������点��A�����������Z�݂₷���Ƃ������̂�����������邱�Ƃɂ���āA��������A���q�l���\�a�c�����������������܂߂����p�n��֑������z��������A���������l�����ł���܂��B
�i�r�c�ψ��j�\�a�c�ƌ����Ώ��⒬�ł��B�������ƌ����Ύ��p�s����ł����A�����������Ƃɂ���Ĉ�s�꒬�ō��������ꍇ�́A��������グ�Ċό����o�q���Ă������Ƃ������Ƃ����܂ł̎�|�ł������̂��ȂƎv���Ă��܂����ǁA�������邱�Ƃɂ���āA���p�Ƃ������Ƃɍi�����ꍇ�A���⒬�͂ǂ��Ȃ邩�Ǝ��B�͍l����̂ł����B��͂莄�Ƃ��Ă͎��p�Ƃ����ό��ɂȂ��Ă��̂ł���Ώ��⒬�͂ǂ��Ȃ�̂��Ƃ������Ƃ��l���Ă��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���̂ł����A���̓_�͂ǂ��l���Ă��܂����B
�i������j�b���A�x�e�������܂��B
�i������j�ĊJ�v���܂��B
�i������j����ł́A���̌��Ɋւ��ẮA����܂łɕ��͕\���ɂ��ďC������Ƃ������Ƃł�낵���ł����B
�i�S���j�ًc�Ȃ��B
�i������j����ł́A���̂悤�ɂ��Č��Ă̂Ƃ�����������܂��B
�����āA���c�đ�11���u�����V�~�����[�V�����ꎟ���Z�ɂ��āv�����肢�܂��B
�i�r�c�ψ��j�c���A11���c�Ăɓ���O�Ɏ��₵�����Ǝv���܂��B
���͂ł��ˁA���O�ɓn���ꂽ�V�~�����[�V�����c�ĂƂ��Ƃ���o�Ă��������V�~�����[�V�����c�Ă̍����啪�o�Ă��Ă���킯�ł����A�ǂ������킯�ł����Ȃ����̂��B����͎�Ⴂ�Ƃ����낢�날�����Ƃ������Ƃł������A���ꂾ���ł́A���͔[�������Ȃ��̂ł����B��̓I�ɂ����������ł���������A�����Ȃ����Ƃ����������K�v���Ǝv���܂��B���O�ɓ͂������̂Ƃ���3����ɓ͂������̂ł��Ȃ荷���o��ƂȂ�ƁA2�C3���̊Ԃɂ���Ȃɐ������Ⴄ�ƂȂ�A����y��ɂ��Ă��̃V�~�����[�V��������������A���̕ӂ��͂����肵�Ă��������Ȃ��Ǝ��͔[�������Ȃ��Ǝv���܂��B���̕ӂ���̓I�ɍׂ₩�ɐ����肢�����Ǝv���܂��B
�i���������ǒ��j���ꂩ��A�����V�~�����[�V�����̍l�����������������Ă��������܂�����ǂ��A����A�`���Ő\���グ�܂����̂�2��ɕ����Ď����̑��t�������Ƃ������Ƃ́A���������肵���V�~�����[�V�����̎��Z�ɕt���܂��ẮA������\���グ�܂�������ǂ����Z�����ł̐ݒ�����Ƃ��đ��̑����̍������c��ݒ�����Ƃ��đg�ݍ���ł�����̂����p�s�E���⒬�C�Ӎ������c��̓����̎��Z�����Ŏ�点�Ă��������܂����B�܂�����͑�و�s�O���̍������c����قړ����悤�Ȑݒ�����ł������Ƃ������Ƃł���܂��B��r�����őS���ݒ�������Ⴂ�܂��Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃɔz��������Őݒ�������قړ����悤�Ȍ`�Ŏ��Z�������ʂ������̎����ɂȂ�A�Γ��A�Ώo�̍��̐��l�ƂȂ��ĕ\��Ă���܂��B���̌�A19���̊�����ɂ����܂��āA���ۂɍΓ�����t�łŌ��z�A�������Ă���̂ɍΏo�̂ق��̕��ʌ��ݎ��Ɣ���ꂪ�����̑O��ł�15�N�x�̌��Z�����݂͌Œ肵���`�ł���A�����������Ă���̂Ɏx�o�����̂܂܌Œ�ł͂�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A��͂��t�ł�����̂�����A������̗��Ō��炵���`�̐��v���K�v�ł͂Ȃ����Ƃ������ƂƁA���ꂩ��A����13�N�x����15�N�x�܂ł�3���N����̍�������A���Z�ł̒i�K�ł͍������t�����Ƃ����ߒ��Ŏ��Z���Ă���܂��̂��A��s���s�����Ȓ��ł����ƌ��Ă����͓̂K���łȂ�����������̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��ꍇ�����Z���Ă݂�K�v������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ������ƂŁA�lj��̎����Ƃ���2�̃p�^�[�����������`�ł����肳���Ă��������Ă���܂��B�]���܂��āA���ꂼ��ݒ������������`�Œ�߂Ă���܂��̂ŏ����I�ȍΓ��A�Ώo�̃v���X�A�}�C�i�X�̊z������Ă��Ă���킯�ł������܂��B
�i�r�c�ψ��j����Ƃ���͂ǂ��Ⴄ���Ƃ������Ƃ��͂����茾���Ă��������B
�i���������ǒ��j���ꂩ��A���̃V�~�����[�V�����ׂ̍������������܂��̂ŁA���̓_�̈Ⴂ�ɂ��Ă��S�̂������Ⴄ�Ƃ������Ƃł��b�����Ă������������Ǝv���܂��̂ł������������������Ǝv���܂��B
�i���}�������Lj��j���c�đ�11���ɂ��Ă������\���グ�܂����A�����V�~�����[�V�����ꎟ���Z�A�V�~�����[�V�����p�^�[���Վ�������������ꍇ�A������̃p�^�[���A�Վ��������i�K�I�Ɍ��������ꍇ�Ƃ������ƂŁA�{�����z�肢�����܂��������̒��Ő��������Ă��������܂��B
���O�ɗՎ�������ɂ��Ă����������Ă��������܂��B
�Վ�������́A�n����t�ł̍����s����₤���߁A�n���̔��s���s�����̂ł��B���̗Վ�������̔��s�́A��������s����邩���̕��ŕ��j�������Ă���܂���̂ŁA����A�Վ�������������ꍇ�ƌ����܂Ȃ��ꍇ�̗����̃V�~�����[�V�������쐬���Ă���܂��B
�͂��߂ɁA���̍����V�~�����[�V�����́A���݂̍����K�͂ɂ����āA���㗼�s���̐l�����v���芪���Љ��ɂ���āA�ǂ̂悤�ɐ��ڂ��Ă������V�~�����[�V�����������̂ł��B����āA���s���Ƃ����l�̐ݒ�����ɂȂ��Ă���A����̗��s���̎{����������Ă���܂���̂ŁA���s�����Ǝ��ɃV�~�����[�V�����������e�ƈقȂ邱�Ƃ�\���Y���܂��B
�@�͂��߂ɁA1�y�[�W�ڂ́u�Վ�������v���������������ꍇ�̍Γ��ݒ�����ɂ��Ă������������܂��B
�@�n���łɂ��ẮA�����̐l�����v�Ɋ�Â��Ď��Z�������s���̒n���ł̍��Z�l�Ƃ������܂����B�n�����^�ł���n�������t���܂ł͗��s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B�n����t�łɂ��ẮA��������ɂ���āA������10�N�Ԃ͗��s���̎��Z�z�̍��Z�l�ƂȂ�A���̌�5�N�Ԃ͌����ɘa�[�u�Ƃ��ď��X�Ɍ��z����܂��B������15�N��ɂ͐V�s�{���̒n����t�łƂȂ�4,513,000��~�Ƃ������܂����B
�@�܂��A�Վ�������̏��Ҋz�͒n����t�łɎZ������܂��̂ŁA���̊z�����Z���Ă���܂��B
�@��������������Ƃ��āA������̗Վ��I�o��Ƃ��ăV�X�e������Ȃǂ̍s���̈�̉��ɗv����o��Ƃ���66,000��~��5�N�ԁA�V���Ȃ܂��Â�������̕��S�i���������ɗv����o��Ƃ���1�N��215,000��~�A2�N��129,000��~�A3�N��86,000��~���A�܂��A������̂܂��Â���Ɏ����邱�Ƃ��ł��鍇������̏��ҋ���70���͒n����t�łő[�u����܂��̂ŁA��������̏��Ҋz��70�����v�サ�Ă���܂��B
�@��ʈ��S�����ʌ�t������g�p���y�ю萔���܂ł͗��s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B
�@���Ɏx�o���́A���s���̍��Z�l�Ƃ������܂������A��������Ƃ��āA������̍s�����^�c�̍������ɗv����⏕���Ƃ���80,000��~��3�N�Ԍv�サ�Ă���܂��B
���x�o�������t���܂ł͗��s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B
�@�J�����́A�Γ��Ώo�����z���}�C�i�X�ƂȂ������_�ŁA�J����\�Ȋ������}�C�i�X�z���J�����Ă���܂��B
�J�z���́A�O�N�x�̍Γ��Ώo�����z���v�サ�Ă���܂��B
�������͗��s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B
�n���ɂ��ẮA���s���ŕ��ʌ��ݎ��Ɣ�̎؋��̎ؓ��������Ⴂ�܂��̂ŁA������̎s�̋K�͂Ɨގ�����c�̂��Q�l�Ƃ��A�ؓ��z�ʌ��ݎ��Ɣ��47.8���Ƃ������܂����B
�Վ�������́A�n����t�ł̌��z���ɑ��Ĕ��s����邱�Ƃ���A���s���̍��Z�l���x�[�X�Ƃ��āA�n����t�ł̌��z��80�������Z���Ă���܂��B
��������̌��ݎ��ƕ��ɂ��ẮA�ؓ��\���x�z��95�D5���~�ł���܂��̂ŁA10�N�ԋϓ���950,000��~���A������Ƃ��Ďؓ��\���x�z��12.8���~�ł���܂��̂ŁA5�N�ԋϓ���256,000��~���v�サ�Ă���܂��B
�����āA2�y�[�W�̍Ώo�ݒ�����ɂ��Ă������������܂��B
�l����ɂ��ẮA������͎A�����A�������A���璷�͊e�X1�l�ƂȂ�܂��̂ŁA���p�s�Ɠ��z�Őݒ肵�Ă���܂��B�c����V�Ɋւ��ẮA����������ő�����p���A�܂�������̒萔��26���ɐݒ肵�Ă���܂��B�E���ɂ��ẮA�e�N�x�̑ސE�\��҂f���A������10�N�ڂɂ͗ގ��c�̂Ɠ����ƂȂ�悤��[����25���ɐݒ肢�����܂����B
������ɂ��ẮA������10�N�ڂ̕���26�N�x�ɗގ��c�̂Ɠ����̐����ɂȂ�悤�ݒ肵�A����Ȍ�͌Œ�Ƃ������܂����B
�ێ���C��ƕ}����ɂ��ẮA���s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B
�⏕��ɂ��ẮA������10�N�ڂ̕���26�N�x�ɗގ��c�̂Ɠ����̐����ɂȂ�悤�ݒ肵�A����Ȍ�͌Œ�Ƃ������܂����B
���ʌ��ݎ��Ɣ�ɂ��ẮA���s���̍��Z�l���x�[�X�Ƃ��āA����27�N�x�ȍ~�͗ގ��c�̂Ɠ����̐����ɂȂ�悤�N��30,000,000��~�ŌŒ肢�����܂����B�܂��A�������ᕪ�Ƃ��āA����������ݎ��ƕ�100���T�疜�~�A�Վ��I�o�3��3�疜�~�A���ʌ�t�ő[�u��4���R�疜�~�A�����s�����⏕����2��4�疜�~���v�サ�Ă���܂��B
�ЊQ������͗��s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B
����ɂ��ẮA�����s���͗��s���̎����Ɋ�Â��ݒ肵�A�V�K���s����15�N����3�N���u�A1.5���̌����ϓ��Ƃ������܂����B��������ɂ��ẮA���ԋ@�ւɂ�鉏�̍ł��邱�Ƃ���10�N����2�N���u�A1.8���̌����ϓ��Ƃ������܂����B
�ϗ����́A�J�z�����������ꍇ��1/2���v�サ�A���̂ق��A�����s�����U�������270,000��~5�N�Ԑςݗ��ĂĂ���܂��B
�����o��������J�o���܂ł͗��s���̍��Z�l�Ƃ������܂����B
�ȏ�̐ݒ�ɂ��A3�y�[�W����5�y�[�W�ɍ�����̍����V�~�����[�V�����������Ă���܂��B
��͂荇����10�N�Ԃ͍��̍����x���ɂ������ɑ傫�ȗ]�T�������܂����A����[�u���I������15�N�ڂ̕���32�N�x������x�o�����X�����X�Ɍ������Ă������Ƃ��\�z����邱�Ƃ���A������10�N�Ԃō��������b�g���������Ď��Ɣ�̈��k�A�R�X�g�_�E�����K�v�ł���Ƃ��������܂��B
���A�Վ������������������̍����V�~�����[�V�����������Ă���܂�����ǁA���̃V�~�����[�V�����ŕ��ʌ��ݎ��Ɣ�����X�Ɍ��z���Ă���܂��B���̌��z�����ɂ͒n����t�łł��Ƃ��A�����C�ӂɌ���܂��̂ł���ɍ��킹�čΏo�����炷���Ƃ��l���ăV�~�����[�V�������Ă���܂��B���̎��������n������O��17���ɗX�������Ă��������܂����V�~�����[�V�����ɂ��܂��ẮA���̕��ʌ��ݎ��Ɣ�����z�������܂���ł����B�S�����̂܂܂��̂悤�ɐ��ڂ���Ƃ������ƂŃV�~�����[�V���������Ă��������Ă���܂��B�ł��A���̃V�~�����[�V�����͕��ʌ��ݎ��Ɣ�����݂̂܂܌Œ肵�Č��z���Ȃ����z�ŃV�~�����[�V���������B���A�m�F�������͍̂Γ������X�Ɍ��邱�Ƃɑ��čΏo�͕��ʌ��ݎ��Ɣ�����X�Ɍ��z�������B�����������V�~�����[�V�����̈Ⴂ�ł���܂��B
7�y�[�W����Վ�������������ꍇ�̗��s�����������Ȃ������ꍇ�̍����V�~�����[�V�����������Ă���܂��B
�n���łɂ��ẮA����15�N�x��15����64�̐��Y�N��l��1�l������̌l�s�������ł��Z�o���A�����̐��v���Y�l���ɏ悶�Ď��Z���Ă���܂��B
�n�����^�ł���n�������t���܂ł́A����15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵�Ă���܂��B
�n����t�ł͉ߋ��̕ω����A�������o�Ϗ܂��āA�N�|3���̌������������̂Ɛݒ肵�Ă���܂��B�܂��A�Վ�������̏��Ҋz�Ɠ��z�̒n����t�ł����Z���Ă���܂��B
��ʈ��S�����ʌ�t�������t���܂ł�,����15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵�Ă���܂��B
�J�����́A�Γ��Ώo�����z���}�C�i�X�ƂȂ������_�ŁA�J�����\�Ȋ������}�C�i�X�z���J�����Ă���܂��B
�J�z���́A�O�N�x�̍Γ��Ώo�����z���v�サ�Ă���܂��B
�������́A����15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵�Ă���܂��B
�n���Ɋւ��ẮA�ߋ��̗��s���̎��тɊ�Â��A���p�s�ł͕��ʌ��ݎ��Ɣ��41.6�����A���⒬�ł�43.5����n���Ƃ��Čv�サ�Ă���܂��B
�Վ�������͕���15�N�x�̎��т��x�[�X�Ƃ��āA�n����t�ł̌��z����80�������Z���Ă���܂��B
�����āA8�y�[�W�ɍΏo�̐ݒ�����������Ă���܂��B
�l����́A���s���Ƃ��ސE�\��҂f���A���p�s�͉ߋ��̎��т���80���̕�[���Ƃ��A���⒬�́u���⒬�s�����v��ԁv�ɂ�蕽��20�N�x�܂ŕ�[����40���Ƃ��A����Ȍ��80���̕�[���Ɛݒ肢�����܂����B
������́A����15�N�x�̌��Z�����z���x�[�X�Ƃ��āA�E���������f���Ă���܂��B
�ێ���C���⏕��܂ł́A����15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵�Ă���܂��B
���ʌ��ݎ��Ɣ�ɂ��ẮA����15�N�x���Z�����z���x�[�X�Ƃ��āA�n����t�łƗՎ�������̌������̓����ɂ���Đ��v���Ă���܂��B
�ЊQ������ɂ��ẮA����15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵�Ă���܂��B
����ɂ��ẮA�����s���͗��s���̎����Ɋ�Â��ݒ肵�A�V�K���s����15�N����3�N���u�A1.5���̌����ϓ��Ƃ������܂����B
�ϗ����́A�J�z�����������ꍇ��1/2���v�サ�Ă���܂��B
�����o��������J�o���͕���15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵�܂����B
�ȏ�̏����ݒ�ɂ����āA9�y�[�W����12�y�[�W�܂łɎ��p�s�̍������Ȃ������ꍇ�̍����V�~�����[�V�����ɂ��Ď����Ă���܂��B
��͂�N�X�������n���ł�n����t�ł̌����ɂ��A����21�N�x������x�o�����X���Ԏ��ɓ]���邱�ƂƂȂ�܂����B����́A�����̕s�������Ƃ��A�Ώo���Œ�l�Ƃ������ʂ���}�C�i�X�ɓ]���܂����̂ŁA�Ώo�̗}���E�k���ɂ�萄�v�͂���邱�ƂɂȂ�܂��B
13�y�[�W����16�y�[�W�ɏ��⒬�̍������Ȃ������ꍇ�̍����V�~�����[�V�����������Ă���܂��B
��͂蓯�����A�������n����t�ł̌����ɂ��A����17�N�x����Ԏ��ɓ]����Ƃ����V�~�����[�V�����ɂȂ�܂����B�������Ȃ���A���̃V�~�����[�V�����ł͕���28�N�x����29�N�x�ɍ����ɓ]���܂����A���̎����ɕ���14�N�x�܂łɎ���ꂽ�n���̏��҂��I�����邱�Ƃ���A�ꎞ�����ɓ]���Ă���܂����A��͂肻�̌�͐Ԏ��ɓ]����Ƃ����V�~�����[�V�����ɂȂ��Ă���܂��B
�����܂ŁA�Վ����������������̍����x���������Ƃ������Ƃ����z���ė��Ă��V�~�����[�V�����ł��B
�Â��āA17�y�[�W����͍��̍����s���ɑΉ������Վ���������i�K�I�ɔp�~���ꂽ�ꍇ�̃V�~�����[�V�����������Ă���܂��B
17�y�[�W��18�y�[�W�ɍ��������ꍇ�̐ݒ�����������Ă���܂����A�Ⴂ�́A�Վ��������16�N�x�͕���15�N�x���Z�����z�Ɠ��z�Ƃ��A����20�N�x����O�Ɛݒ肵�Ă���܂��B
���̌���19�y�[�W����21�y�[�W�ɗՎ���������i�K�I�ɔp�~���ꍇ�������ꍇ�̍����V�~�����[�V�����������Ă���܂��B
�Վ�������������܂Ȃ��ꍇ�́A��10�����~�̍Γ����s�����܂����A��������[�u�ɂ���č�����10�N�Ԃ͎��x�o�����X�������Ő��ڂ��܂��B����29�N�x����Ԏ��ɓ]���A�������̌J�����ɂ���Ď��x�o�����X���[���ɕۂ��Ă���܂��B����ėՎ�������������܂Ȃ��ꍇ�͂���w�̎��Ƃ̏k����R�X�g�_�E���ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����������܂��B
23�y�[�W����́A�������Վ���������i�K�I�ɔp�~���ꍇ�����Ȃ������ꍇ�̃V�~�����[�V�����������Ă���܂��B
�������Վ��������19�N�x�܂łɒi�K�I�Ɍ����A����20�N�x����[���Ƃ������܂����B
25�y�[�W���玭�p�s�̍������Ȃ������ꍇ���V�~�����[�V�������Ă���܂����A��͂�A�Վ���������Ƃ��Ė�10���~�̍Γ����������邱�Ƃ���A����19�N�x����Ԏ��ɓ]����Ƃ����V�~�����[�V�����ɂȂ��Ă���܂��B
29�y�[�W����͏��⒬�̍����V�~�����[�V�����������Ă���܂����A������3���~���̍Γ����������邱�Ƃ���A����16�N�x����Ԏ��ɓ]����Ƃ����V�~�����[�V�����ɂȂ��Ă���܂��B
�Ȃ��A����̃V�~�����[�V�����ł́A�L��s���g���̌o��͂��łɕ⏕��Ɋ܂܂�Ă���܂����A�V���ȑg�D�ƂȂ����ꍇ�ǂ̗\�Z�敪�ɕ��ނ���邩���̃V�~�����[�V�����͍s���Ă���܂���B
����̓��Z�ł́A��{���j��헪�v���W�F�N�g���������Ď��Z���邱�ƂƂȂ�܂��B
�ȏ�ŁA�����V�~�����[�V�����ꎟ���Z�̐������I���܂��B
�i������j�������܋��c�đ�11���̐������I���܂����B���̋��c�Ăɂ��܂��āA������A���ӌ�������܂����炲�����肢�܂��B
�i�����ߗY�ψ��j���{�������߂Ă���A������O�ʈ�̉��v�A���Ȃ킿���ɕ⏕���̍팸�A�n����t�Ő��x�̌������A�n���ւ̐Ō��ڏ��ɂ��Đݒ���������܂��ƍ��ɕ⏕���ɂ��Ă͎s���̍��Z�l�A���ꂩ��n����t�łɂ��Ă͔N�|3���Ƃ���������ł���܂����A�m���ɍ��A�n���̐ō����������߂Ȃ�����ł͂�ނȂ��Ǝv���܂����A��������3�̎�ڂ͑�ρA���z���傫���킯�ł��ˁB�]���Đ��v����ł͍����v��S�̂ɑ傫�ȉe�����o�Ă���Ƃ������Ƃ��\�z�����킯�ł����A���̎�舵���ɂ��č����邢�͌��̈ӌ����悵���Ƃ������Ƃ�����܂����B�S���A������̍l�����ł�����̂ł����B���̂�������m�F�������̂ł����B
�i���}�������Lj��j�����V�~�����[�V�����ɂ��Ă͌��̍����x�����Ƒ��k�������܂����B�V�~�����[�V�����ݒ�����ɂ��܂��Ă͂��̋��c��Ǝ��ɂ��C������Ƃ������Ƃł����B�����A������A�@�苦�c��ɂ����č����V�~�����[�V������g�ޏꍇ�́A��͂�Վ��������g�܂Ȃ��Ɨ\�Z�͑g�߂Ȃ��Ƃ������ƂŗՎ�������������`�őg������낵���ƁA�w���ł͂Ȃ��̂ł����A�����������b�ł���܂����B
�i�����ߗY�ψ��j����2�_�قǂ���̂ł����A�悸�����̃����b�g������Ƃ����ϓ_����E���萔�������Ƒ����N�x�Œ����ł��Ȃ��̂��Ƃ�������������킯�ł��B�����̃����b�g�͋c�������邢�͐E����������Ƃ����Ƃ���ɑ傫�������b�g������킯�ł��ˁB���̕ӁA�l��������܂��Ƃ����ƌ��点��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B���Ɏ��p�s�̏ꍇ����������550�l�̐E���������킯�ł����A15�N��4��1���ł�361�l�Ƃ������ƂŖ�190�l�������Ă���킯�ł�����A���̐l����̐ߌ����͖�10���~���Ǝv���܂��B��������ƍ���̍����^�c�̂Ȃ��ɂ�����l����̍팸�͔��ɑ傫�ȗv�f������킯�ł��̂ň�̍l�����������B������͐����ʍΏo�̒��ł��}����Ƃ����̂͑�ρA�傫�ȃE�G�C�g���߂�o��Ȃ킯�ł����A���̒n��̍����������̎����Ō��܂���17�N�x��27�N�x��4.4���㏸����Ƃ������v���o����Ă���킯�ł����A�����ŕ}����̐ݒ���������܂��Ɨ��s���̍��Z�l�Ƃ����Ƃ���̂ł����A�ߏ��Ȍ����݂ɂȂ�Ȃ����Ƃ����C�����܂����A����2�_�ɂ��Ă��f���������Ǝv���܂��B
�i���������ǒ��j�E�����̌��ɂ��Ăł����A����ɂ��܂��ẮA�����݁A���c��C�ӂł���Ƃ������Ƃŋc���̒萔���܂߂܂��Ē萔�W�ɂ��Ă͖@�苦�c��̕��ł����c���������āA���̒��ł͂����肵���ݒ�l��ώZ���ł���Ƃ����l�����Ŏ����ǂ͂����߂Ă���܂��B�}����ɂ��܂��ẮA���A�����c�����猾��ꂽ�悤�Ȍ��O����镔��������킯�ł�����ǁA�ǂ��܂Ō��邩�Ƃ������Ƃő��̂ق��̎���ׂĂ݂��̂ł����A�قƂ�ǂ̂Ƃ��낪�ߋ��̉��N���̕��ϒl���Œ肷�邠�邢�͌��Z�����݊z�ŌŒ肷��Ƃ����`�Ő��v���Ă�����̂ł�����A�����������܂Ő����f�����邩�Ƃ������Ƃ��ׂ����ώZ�ł��܂���ł����̂ŁA���̂ق��̗�ɂȂ�����Ƃ������Ƃ��������������������Ǝv���܂��B
�i������j���̌��Ɋւ��Ă��������ψ��̊F�l�̈ӌ��������̂ł����B���̓��قł͔C�ӂ̋��c��Ȃ̂ł��̂悤�Ȍ`�ɂ����Ƃ������ƂȂ̂ł����B
�i�r�c�ψ��j�l����팸�ɂȂ��Ă���̂ł����A�����팸�Ƃ������ƂŌv�Z���Ă��܂����B
�i���}�������Lj��j���݂̐E���������ƂɊe�N�̑ސE�\��҂������݂܂��āA���������ꍇ�͂��̕�[����25���A���Ȃ��ꍇ�͎��p�s�̏ꍇ��80���A���⒬�̏ꍇ�͍s�����v��Ԃ�����܂��āA��[����20�N�x�܂ł�40���A����21�N�x�ȍ~�͎��p�s�Ɠ���80���Ƃ����O��ŐώZ���Ă���܂��B
�i�r�c�ψ��j�ЊQ������[���ɂȂ��Ă���̂ł�����ǁA�Ȃ��ł����B���N�A�ЊQ���Ȃ����p�͈��肵�Ă���Ƃ������Ƃł����B
�i���}�������Lj��j�ЊQ������ɂ��܂��ẮA���s���̍����S���҂Ƌ��c�����̂ł����A����A�ЊQ������ǂ̂悤�ɐ��ڂ��邩�킩��Ȃ��A���Ƃ͍Ώo�C�R�[���Γ��œ����Ă���Ƃ������ƂŁA���̏����ɂ͐ݒ肵�Ȃ��Ă������Ƃ������ƂŖ{���A���̐ݒ�����̂Ƃ���ЊQ������͍����܂Ȃ��Ƃ������Ƃ������̂ł����A����10�N�x����15�N�x�܂ł̎��тɂ�����܂����̂ł��̂悤�ɏ������Ă��������܂����B
�i�r�c�ψ��j14�N�x�܂ōЊQ�͂Ȃ������Ƃ������Ƃł����B
�i���}�������Lj��j14�N�x�܂ō������Ȃ������ꍇ�ł�����ǎ��т��f�o�����Ă��������Ă���܂��B
�i�r�c�ψ��j14�N�x�܂ł͍ЊQ�͂Ȃ������Ƃ����悤�Ɍ����̂ł����Ƃ������Ƃł��B14�N�x���p�����Ă�����݂��Ƃ������Ƃł���B���̕ӂ͂����肵�ĉ������B
�i���������Lj��j������9�y�[�W�ł�����ǂ��A�������Ȃ��ꍇ�̐��v�Ƃ����Ƃ���Ŏ��p�s�̕���10�N�x����14�N�x�܂ł̊z���ڂ��Ă���܂����A���̃y�[�W�̍Ώo��7�ԍЊQ������10�N�x�ɂ��ẮA40�420��~�A12�N�x�A13�N�x�A14�N�x�ɂ��Ă����т��f�o���Ă���܂��B15�N�x�ɂ��Ă͌����z�Ƃ������Ƃō��̂Ƃ���[���ɂȂ��Ă���܂��B���⒬�����������ł���܂����A15�N�x���Z�����z�ŌŒ肵������16�N�x�ȍ~���[���Ƃ��������ɂȂ��Ă���܂��B
�i�r�c�ψ��j��������ƁA���̂����������Ă��Ȃ������͍ЊQ�̕������ł��Ȃ��Ƃ������Ƃł���ˁB
�i���������Lj��j�ЊQ������̌����݂ɂ��܂��ẮA���̔N�x�ōЊQ������ǂ̂��炢�����邩�킩��Ȃ��킯�ł�����ǁA���̕��ɂ��čΓ��̂ق��ɓ����Ă��܂��̂ŁA���̕��A�Ώo�̏ꍇ�A�Γ��̂ق��������܂Ȃ���Γ������ɂȂ�܂��̂ŁA���̏ꍇ�A���v���[���ɂ��Ă���܂��B
�i�r�c�ψ��j�ЊQ������͍ЊQ���N������A�����������Ă��Ȃ������͎d�����ł��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł����B
�i���ʑ��������j�ЊQ������͌����̗\�Z�ł��Ƃ��ĂȂ��ł��B���܂��Ă���\�Z�c�������������Ă���܂��B���̂��ߍ���̓[���ɂȂ��Ă��܂��B
�i���������Y�ψ��j���肢�ɂȂ邩�Ǝv���܂�����ǁA���������������i�K�ł͗Վ��������i�K�I�Ɍ������������̂ō��������ꍇ�Ƃ��Ȃ��ꍇ�A���Ɍ��������ꍇ�A���Ȃ��ꍇ��16�N�x����\�Z�Ґ��ł��Ȃ��B���p�s��4�N��ɂ͗\�Z�Ґ��ł��Ȃ��B�Ƃ����ł���܂�������Ɍ����������ł���܂��B��͂�����̍d��������E�p���邽�߂ɂ͔��ɐ؉H�l�������Ƃ�������Ă��܂��B�����A�C�Ӌ��c��̈ψ��Ƃ��Č���ꍇ�͎�������Ă��炤�킯�ł�����ǁA��͂�n���ɋA�����ꍇ�͏��⒬����ɂ���A�c���̊F����ɂ����ԕȂ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��`��������킯�ł��B���������ꍇ�A���̐��l���O���t�����Ă�������ق������Ɍ��₷���Ǝv���̂ł��B�Ⴆ�A�Վ�������������������Ă������̂ƁA���Ȃ������ꍇ�Ƃ����̂͗Ⴆ��10�N���17�N�͍Γ��S�̂�63��������Ă���Ƃ��������Ƃ����ɑΔ䂵�₷���Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����B����ɂ����Ă��O���t�Ō�����Ƃ������Ƃ͎{��̓W�J�A�V�s�\�z�v��ɂ���đ�̍����V�~�����[�V�������傫���ς���Ă���킯�ł��B����ɂ���Ă��A���݂̃V�~�����[�V�����͂���������ǂ��A�V�����V�s�A�܂��Â���ɂ���āA���������ӂ��ɕω����Ă���Ƃ����̂��O���t�Ŏ����Ă���������Ή�X����ϐ������₷���Ȃ邵�A�����������ł���悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����ǁA�������ł��傤���B
�i���������ǒ��j���A����ꂽ���Ƃ��ӂ܂��܂��č���̎����쐬���ɂ�����܂��Ă��A�ł��邾�����o�Ƃ����_���d�����܂��Ă킩��₷���������ɓw�߂����Ǝv���܂��B
�i���������Y�ψ��j����A���肢���܂��B
�i������j�ق��ɂ������܂��B
�i�����ߗY�ψ��j���̎��Z���ʂɂ��܂��ƁA���A�s�̋c���̂ق�������b���������킯�ł������������ꍇ�ɂ���߂ėL���ȍ����^�c���\�ɂȂ�Ƃ������Ƃ����m�ɂȂ����킯�ł����A���������č����^�c�ォ�猩�������̃����b�g�͔��ɑ傫���Ƃ������Ƃ����Â������܂����B���������ꍇ�ɂ�3�N��ɂ͖�10���~��A5�N��ɂ�20���~��̗]�T������������Ƃ������v�ł��B�������Ȃ������ꍇ�̐��v������Ǝ��p�s�̏ꍇ��21�N�x�ȍ~�A���邢�͏��⒬����̏ꍇ��17�N�x�ȍ~�A���ꂼ������s���𗈂����Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B������܂����Z���o�Ă���Ǝv���܂�������A���ꂽ���Z�ł͂����������ƂɂȂ�B�O�i�A�\���グ�܂����Ƃ�������ʏォ�猩�������Ƃ����̂͑傫���ȂƂ������Ƃ������܂����B���ꂩ�獡�A�c�����炨�b������܂������A�O���t�łȂ��Ă��Ⴆ�A�\���͗Ց������ꍇ�A���ꂩ�������͗Փ���i�K�I�Ɍ��������ꍇ�Ƃ����ӂ��ɁA�\���̂ق��́@�@��͍��������ꍇ�A�V�s17�N�x��26�N�x���r���Ă݂āA���ꂩ�獇�����Ȃ��ꍇ��������݂��āA�����Ď��p�s17�N�x��26�N�x�A���⒬17�N�x��26�N�x�Ƃ��������ӂ��ɏ����ƁA�O���t�łȂ��Ă����m�ɂ킩��܂�����A����A���ꍇ�͂����������Ƃɓ���č�����ق��������Ǝv���܂��B
�i������j�ق��ɂ������܂��B
�@����ł́A���A�b���ꂽ�Ց������ꍇ�Ƃ������܂Ȃ��ꍇ�Ƃ������������A�����ł�낵���ł����B
�i���������Y�ψ��j�����ǃT�C�h�ł���Ă݂āA����͐������₷���A�������₷���Ƃ����ϓ_�Ō������Ă݂ĉ������B
�i������j����ł́A���̂悤�ɂ��肢�\���グ�܂��B
�i�ɓ��q�q�ψ��j�����̋��c�ɂ͒��ڊW�̂Ȃ����Ƃł����A������3��ڂ̋��c��Ƃ������ƂŁA���͏Z���Ƃ������Ƃł����ɎQ�����Ă���܂����A�������S���Ă���܂��͔̂��ɂ�������Ƃ����������o���Ă��ē��ɍ����͍����V�~�����[�V���������������܂��āA�����������Ƃɂ��đf�l�̎����ɂ��킩��Ղ��S�z��Ƃ����܂����p�ꓙ�̉�����ڂ��Ă����肵�܂����B���Ƌ��c�Ă̓��e�ɂ����܂�����ǁA�V�s�̏����\�z�Ƃ������Ƃł������܂����̂ŁA���̒��g�����͕\���ɂȂ��Ă���܂����̂ŏZ���Ƃ��܂��Ă͔��Ɏ���Ƃ����܂����A�b�����������ɂȂ�₷���Ƃ������̂ł������Ǝv���܂��B�����͂����������s���̃v���̊F�l���Ɠ����y�U�ɏ���Ă���킯�ł��āA�v���̊F�l�ɂ͈�ڌ��Ă킩�邱�Ƃ��킩��ɂ��������肷��킯�ł��ˁB�����������ۂɖ{���̏ꍇ�͋��c�Ăɂ����܂�����ǁA�������������ł��Ɣ��ɂ킩��Ղ��ł����A�Z���̈ӌ����q�ׂ₷���Ǝv���܂��̂ŁA����A�킩��Ղ��������Ƃ������b���������܂�������ǁA����Ƃ��A�����������Ƃ��l�����킹�Ă��������Ă�낵�����肢�������Ǝv���܂��B
�i������j����������Ȃ��������������āA�C�y�ɂ��b�肦����肪�����ł��B
�ȏ�������܂��āA�{���̈Č��͂��ׂďI���������܂����B�����Ԃɂ킽��T�d�R�c���肪�Ƃ��������܂����B
���ɁA���ɂȂ���c���E���������Ă��������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
�i���ʑ��������j�ǂ������肪�Ƃ��������܂����B
����������܂��āA��3�Â̒n��C�Ӎ������c������Ă��������܂��B
�Ȃ��A��4��̋��c��́A�V�s�܂��Â���̗��O�Ə������A��{�I�����ɂ��Ă��R�c���������\��Ƃ��Ă���܂��B��낵�����肢�\���グ�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|