 |
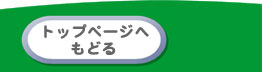 |
|
���Â̒n��C�Ӎ������c��@��S���c�L�^
|
| ���Â̒n��C�Ӎ������c��@��S���c�L�^
�Q�@�J�Ïꏊ�@�@�@����z�R������ �R�@�o�Ȏҁ@�@�@�ψ��E�E�E�E�@14���i�S���o�ȁj �S�@��c���� �Z���c �T�@��c�L�^ �i������j���͂悤�������܂��B�F�l�ɂ͑�ς��Z�����Ȃ����o�Ȃ��������܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�����m�̒ʂ荡�N�A���p�̏o���H�͔��Ɍ��������̂��������܂��B9����19���ɂ͏���̒�������ƍ��̋T��_�ѐ��Y��b�ɒ�����Ă܂���܂����B�܂��A����͏H�c���m�����邢�͌��̋��ϘA����ɏo�����Ē�Ă܂���܂����B�ł��邾���A���̔�Q���ŏ����ɂƂǂ߂邽�߂���肽���Ƃ����C�����ł���܂��̂ŊF����ɂ���낵�����肢�\���グ�܂��B���ĔC�Ӌ��c��ł������܂�����4����}���܂����B���c�Č��̐V�s�����\�z���邢�͏����s�s���ɂ��Ăł���܂��āA���ɏd�v�ȕ����ɓ����Ă����Ƃ����ӂ��Ɋ����Ă���܂��B�ψ��̊F�l�̐ϋɓI�����ݓI�Ȕ����ŏ��ψ���邢�͊�����Ō������ĉ��������������X�ɐ[�߂Ă������������Ƃ����ӂ��ɂ����҂�\���グ�܂��Ĉꌾ�����A�ɂ��������Ă��������܂��B
�i������j����ł͂��ꂩ���4�c����J�Â������܂��B �i���������ǒ��j�{���̏o�Ȉψ��͑S�ψ�14���S�����o�Ȃ���Ă���܂��B �i������j���ɁA��c�^�����l�̑I�o�ł����A���c���c�^�c�K����5���3���ɂ��c�����w�����邱�ƂƂȂ��Ă���܂��B �i���������ǒ��j��11���ɂ��Ă����������Ă��������܂��B
�i���������ǒ��j���c�đ�12���ɂ��Ă���������O�Ɏ����ǂ̂ق����炨�l�т������܂��B���茳�̎����̖ڎ����t�ɕ����Ă���܂��B��ρA���炢�����܂����B���ꂩ��V�s�����\�z�i�āj�̕����ɂ����܂��āA�{��1������12���܂ł́u��N�v�ŕ\������Ƃ����4�����痂�N3���܂ł́u�N�x�v�ŕ\�����Ă���ӏ�������܂����B����̑�5�c��܂łɏC�������Ă������������Ǝv���܂��B��̓I�ɂ́A22�y�[�W����27�y�[�W�܂ł́u��v�w�W�̏������ʂ��v�̕����ł������܂��B �i���������Lj��j����ł͋��c�đ�12���u�V�s�����\�z�i�āj�v�ɂ��Đ��������Ă��������܂��B �i������j�������܋��c�đ�12���̐������I���܂����B���̋��c�Ă��܂��āA������A���ӌ������������܂����炲�����肢�܂��B �i���������Y�ψ��j���A�������������܂�������ǂ��A��ρA���k�ł������܂����O��̂��ƂɎ�A�߂点�Ă��������܂�����ǂ��A�s���̕��z�����ɂ��Ă��̑O�A���₵�Ĕ[���������肾�����̂ł����A27�y�[�W�́u���̎s�������z�����̐��v�ɂ��ƁA�{�n��̎s�������z�����͑����X���������A�����V�N�`12�N��5�N�Ԃ�2.09���̑����������Ă��܂��B�v����ɂ����17�N�A22�N�A27�N�A32�N�𐄌v���Ă���܂����A�܂���͂V�N����12�N��5�N�Ԃ͂��̂܂܂ł�낵���̂��B�܂�7�N����ɂ���8�N����12�N�܂ł�5�N�ԂɂȂ�Ȃ��̂��B���ꂩ��A���̎�����13�y�[�W�ł����A�Y�ƕʂ̎s���������Y�z�̕���8�N����12�N�܂Ŗ�100����������ł��܂��ˁB���ꂩ��s�����z�����ɂ��܂��Ă�8�N�x����12�N�x�܂�5���N��62��5��600����������ł���B�p�[�Z���e�[�W�ɂ����5.7���B9�N�x����12�N�x�܂łł�51���~��������ł���B������4.72���B10�N�x����12�N�x�܂łł�16���~�B������1.62���B11�N����12�N�x�̈ꃕ�N�ł悤�₭�v���X2.09���A20���~�����킯�ł�����ǂ��g�[�^���I��8�N����5�N�ԂŃ}�C�i�X������129���A�v���X������20���Ń}�C�i�X109���~�ɂȂ�킯�ł����A����ł�����5�N�Ԃ�2.09�����p�̎s����������������Ƃ������f�͂ǂ�����o���̂��ƁA�ǂ����Ă����͔[���ł��Ȃ��̂ł�����ǂ������ł���ł��傤���B �i������j�������܂̔����ł����A���c�Ăł͂������܂����̎���ɑ��Ă������肢�܂��B �i���������ǒ��j����ɂ��܂��āA���̐��v�̎x���Ɩ������Ă��������Ă���ϑ��Ǝ҂ɂ��O����w�E������܂��Ă��b���������Ă���̂ł�����ǁA���������\�����������Ƃɂ��Ă̖��m�ȍ��������������Ă��܂���̂ŁA�������������Ԃ��������������Ǝv���܂��B�m���ɍ��A�����܂����悤�ɌX���Ƃ��������ł����Ɖ������Ă���B�����N�����オ���Ă���ł���܂��̂Ő������Ƃ��������ŋ^�₪���邩�Ǝv���܂��̂ł����������������Ԃ��������B �i���������Y�ψ��j�s���ɕ��z������5�N��A15�N�ケ�̂悤�ɂȂ�̂��Ǝ��������̂͂킩��܂�����ǁA��͂茻��܂������l����X���F�����Ă����Ȃ��ƁA�o���F�������Č�ł܂��������Ƃ����킯�ɂ͎��͂����Ȃ��Ǝv���̂ł���B������ł͂Ȃ��A�s���S�̂�����5�N�Ԏs���������㏸���Ă���̂��Ƃ����F�����Ȃ��Ǝv���̂ł��B���������s���ɐ������邽�߂Ɏ����g���[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŎ���܂łɂȂ�Ƃ������ł���悤�ɂ��ĉ������B �i���������ǒ��j���A���b����܂��������V�N����12�N�܂ł̂T�N�ԂƂ����\���ɂ��܂��Ă������Ċm�F�A�����������܂��Ă��������Ǝv���܂��B �i������j����ł͋��c�đ�12���ɂ��Ă̎��^�����肢���܂��B �i�p�ψ��j�w�Z����̏[���Ƃ������Ƃ�36�y�[�W�ɂ��镔���Ɋ֘A���Ă̈ӌ��Ǝ����v�������Ǝv���܂��B���S�T5�������X�^�[�g����2�N�ڂɓ�����킯�ł����A�������ۂo�s�`�Ɍg���l�ԂƂ��Ċw�Z�̌���A�����Ďq���B�̘b���Ă���܂����A���S�T������Ƃ�̋����ڎw�������x�𐭕{���l�����킯�ł����A���S�T�����ɂ�镾�Q�������ɗ��Đ����o�Ă���Ƃ����ӂ��Ȋ��G�������Ă���܂��B�܂��A��ɂ͂��̎����̒��ɂ�����܂��悤�Ɋj�Ƒ������i��ł���܂��B�]���܂��āA��g�̕v�w���q��Ă�����ꍇ�ɂ����ċ��҂����~�ނȂ��Ȃ�킯�ł��āA�q���B���t�ɓy�j���A���j���A�e�̖ʓ|�ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���������ӂ��Ȗ�肪�����܂��B����ƁA�w�Z����ɂ����܂��Ă̓J���L�����������Ƀn�[�h�ȃJ���L�������ɂȂ��Ă���܂��āA���ۂɂ͒n�敶���A�n��Ƃ̌𗬂Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���Ă���܂����A���̂悤�ȁu��Ƃ�v�̎��Ԃ��t�Ɏ��ĂȂ��Ȃ�A�l�X�Ȋw�Z�s���ɂ����ẮA�d���Ȃ��s�������~�߂�Ƃ����悤�Ȍ��������܂��B���̂悤�Ȋw�Z�T�����̕��Q���s���̕��X���A�ǂꂭ�炢����̂��Ƃ�F������Ă���̂��A���̕ӂ����������l���Ă������������Ƃ����̂���ł���܂��B �i������j����́A�S���ɕ������Ă������������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�F�łǂ̂悤�ɂ��Ă������Ƃ����b�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A���Z�̂����鑶���̎d���Ƃ����̂͌��̋���ψ���̕��ł��낢��ƌ����A���c����Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂����A�n���̕��ł�����������ق��������A��������ׂ����Ƃ������͂ǂ�ǂ�o���Ă������ق��������̂ł����A���̏�ʼn��ɂǂ������ӂ��ɂ��Ă������Ƃ����̂͂�����Ɠ�����ȂƂ����������������܂��B�w�Z�̂T�����Ɋւ��Ă��n���̐l�����̒��ō��̏�Ԃ��ǂ��������̂ł���̂��Ƃ������b�͂���܂������A���̂��Ƃɑ��Ă��F�ŁA�ʂ����Ă��̂܂܂ł悢�̂��Ƃ������Ƃ͂��ꂩ��b�����Ȃ�����P���Ă������͉̂��P���Ă����A�Ƃ����ӂ��Ȋ����Ői�߂Ă����������悢�̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���܂��B����Ɋւ��ĂǂȂ������ӌ��������܂��B �i����ψ��j���p�R�Z�̋�̓I�Ȃ��b���ł��킯�ł����A��͂菭�q����Ƃ��������I�Ȑ��l���\���ł���킯�ŁA���̂Ȃ��ŊF������ʂ����ď����A�ǂ������ʒu�t���ő������ǂ��Ȃ�̂��A����͒n��ɂƂ��Ă͑傫�Ȗ�肾�Ǝv���܂��B��͂�A�ǂ�ǂ�o�čs���̂ł͂Ȃ��āA���͂���w�Z�������Ă悻������A��ė���悤�Ȃ��������������Z�ł͂���܂����A�������Ȃ��Ɛ����c��͓���Ǝv���܂��B �i������j���c�ĂƂ��Ă����ŐG���ׂ����ǂ����Ƃ������Ƃł����B �i�ޗLjψ��j�Ⴆ�ł��ˁA3�Z�̊w�Z�̑I���̊W�ł����A�ۈ牀�ɗႦ��A�F�ۈ牀�̏ꍇ�A�ی�҂��ۈ珊��I�ԁB�����āA�����̐����ɍ����ۈ珊�ɒʂ킹�Ă悢����ł��B�O�͒n�������Ċw�Z�̂悤�ɕ����Ă���Ă����B���N����ł����A�ی�҂��I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��܂����A�{�݂��������Ȃ�������Ȃ����A���e���������Ȃ�������Ȃ��B���ꂩ��A�����Ƃ̐܂荇�������߂Ă����Ƃ����悤�Ȋ֘A���o�ė��Ă���܂��̂ŁA�����w�Z�́@�������߂����Ƃ́A�S�������͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ������Ȃ���A���������X�������邱�Ƃɑ��āA���ǂ��͂ǂ��l���邩�Ƃ������Ƃ́A��x������Ȃǂɂ��낵�Ă���������Ǝv���̂ł����B �i������j������Ō������Ă������������Ƃ������Ƃł�낵���ł����B �i�p�ψ��j�d�˂ĕ⑫�����Ă��������܂����A�܂��A�X�|�[�c�U���Ƃ����ʂ���l���܂��Ă��A�����v���̂ɁA��苭���Ȃ肽���A��荂�����̂�ڎw���X�|�[�c�I��́A��͂�A����Ȃ�̊���ڎw���Ď����̐i�H�����肷��Ǝv���킯�ł��B�����������Ɏ��p�̍��Z3�Z�̂Ȃ��ŁA���������ӂ��ȓ��F���鍂�Z�Ƃ��Ă̕����������o���Ă����Ȃ��ƗD�G�Ȑl�ނ����p���痬�o���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ȂƂ����̂����̌��O�ł������܂��B�܂��A�i�w��ڎw���҂ɂ����܂��Ă��A���ɖk���n��̍��Z�ɂ����܂��Ă͊w�Z5���������܂��ēy�j���o�Z���펯�ɂȂ��Ă���܂��B�܂��A�w�悪��蕥���邱�Ƃɂ��܂��āA��͂�A��背�x���̍����i�w�Z��ڎw���Ďq���B�͂����ڕW�Ƃ��āA��������Ύ��p���痬�o����\��������Ǝv���܂��B���̕ӂ����p3�Z�̍��Z�̑������l�����ꍇ�ɁA��͂���F���閣�͂���w�Z��n��A�w�Z�̗��n��Ƃ����肢�������Ǝv���܂��B �i������j�������܂̈ӌ��𗈌��̊�����Ō������Ă������������Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j�O��̏C���Ă��o�Ă��܂�����ǁA�C���Ă��o���Ă���ꖇ�̎��ƁA�����i�V�s�����\�z�i�āj�j�ɏ�����Ă�����e���ς���Ă���Ƃ��낪����̂ł������A�C���Ēʂ菑����Ă��Ȃ��͉̂��̂Ȃ̂��B�C���ĂƂ��ďo���ꂽ�ړI�͉��Ȃ̂��B�C���Ă̕��͂̓��e���ς��Ƃ������Ǝ��̂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł������̕ӂ͂ǂ��Ȃ̂ł����B �i�r�c�ψ��j����A���̕��ł͋c���̑S�����c��݂����Ȃ��̂��J���܂����B���̕��͂����āA���⒬�̃C���p�N�g��������Ɣ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������z���������ψ�����������܂��āA������������
13�N�x����10�N�Ԃ̑����v��𗧂ĂĂ���̂�����A����������ꂽ�Ȃ��ōl���Ă��炦�Ȃ��̂��Ƃ�������������܂����B�����������Ƃ��炵�āA���������l���Ă������������Ǝv���܂��B�������܂̒��S�X�̖��ł�����ǁA����Ƃ��}�C�������h�𒆐S�Ƃ���ƂȂ�A������ƕςł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �i������j�܂��A�ŏ��̖��ł����A����̋��c��Řb���ꂽ���̂͋�̓I�ɂǂ��������̂����邩�b���Ă���������A���Ɏ����ǂ̕��ł����g�݂₷���Ǝv���̂ł����B �i�r�c�ψ��j��̓I�Șb�͂�����Əo�Ȃ������̂ł����A���̕��͂ł̓C���p�N�g�������̂ł͂Ȃ����Ƃ�������������܂��āA�命���̐l�������Ă���Ƃ������Ƃł����A����Ɗm���ɂ����ւ�悭�܂Ƃ߂��Ă���̂ł�����Ǐ������Ƃ��ẮA�i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA���������������Ƃ����Ȃ��猩���Ă��Ȃ��Ƃ�������������܂��āA����������̓I�ȍl�������o���Ă��������Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ����b������܂����B�����39�y�[�W�ł����A�@�ƇA���t�ɂ��ćA�̂ق�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u�Z���Q���̑��i�v�̕�����ł͂Ȃ����Ƃ�������������܂����B���̕ӂ͂ǂ̂悤�ɍl���Ă����̂��F��������ӌ������肢���܂��B
�i�ޗLjψ��j���́A�u�H�v�ƎQ���őn��܂��v�Ƃ����O��ł������������ɂ����Ǝv�����A�R�~���j�e�B���Z���Q���̑��i�ƂȂ�A�������������ł��傤���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���Ԃ�ς���Ɣ��ň͂��������̏������Ђ�����Ԃ�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����Ȃ�Ɍ�������Ĉʒu�t�����Ȃ��Ă���Ǝv���̂ŁA���͑Ó��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �i�I�R�ψ��j���̏��ԂɊւ��܂��ẮA�����炭�����ǂ̎����Ƃ��Ă̂����܂ŏ��Ԃł����ā@�D�揇�ʂƂ��̈Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�t�ł��ʂɍ\��Ȃ��Ǝv���܂����A�����܂Ŏ����̃Z�N�V�����̇@�A�A�Ƃ������������Ǝv���̂ŁA�����͖��ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j�c��ł̈ӌ��Ƃ��ďo���̂����玄�͂����b���������̂ł����āA�F������ł����Ƃ������Ƃł���Ύ��̕��͂���Ȃ�ɗ��������Ă��������܂��B �i���������Y�ψ��j���Ɏ����ƘA�g���珇���܂Ƃ߂��āA���ψ���̂Ȃ��ł́A���ԓI�ł͂Ȃ����Ƃ����낢��Ȉӌ����o���ꂽ�Ƃ������Ƃł�����ǁA���́A����͂���Ƃ��Ă�����Ƃ��݂��݂܂ōl����ꂽ�̂��ȂƂ����C�����܂��B�������ψ���̈ӌ��ł������ꂽ�悤�Ɏ����s���Ƀp�b�ƕ�����Ղ����邽�߂ɂ́A3��4�ɂ܂Ƃ߂Ă��̐V�����s���A���̂S�����͊m���ɐ��i���Ă����̂���Ƃ����Ȃ\�����K�v�Ȃ̂��ȂƂ����C�����܂�����ǁB����ɏ��ψ���Ȃ�A������Ȃ�Ō������Ă��炢�����Ǝv���܂��B �i������j���ψ���A������������ł����A���̋��c��̈ψ��̊F�l�����̓I�Ȃ��̂��o���Ă������������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂����B �i���������Y�ψ��j��͂莭�p�s�E���⒬������܂Ŏ��g��ł����Ⴆ�A�ό��A���T�C�N���������������̂͑S�ʓI�ɏo���Ă����B���ꂩ��A���̔_�n���A�����ւ������Ă����Ȃ��_�n����͂芈�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA��͂�A���ꂩ��̌�����������Ă������߂ɂ͍s�������v����͂�����Ƃ����ƃV�r�A�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������S�_���炢�͑S�ʂɉ��o���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����ȂƂ����C�����܂��B �i������j�T�c�ψ��B��������܂����B �i�T�c�ψ��j�O��̋��c��ł��b������܂�����������ʂƂ������ƂŁA���p�s�̗ǂ��Ƃ���A���⒬�̗ǂ��Ƃ���B���ꂼ����o���Ƃ������Ƃł�����ǁA���ہA���̒��ɑS���ڂ��Ă���̂ł���ˁB���Ƃ���Ύ����ǂ̐����̂Ȃ��ɗႦ�A(1)�́u���R�Ɩ��͂����ӂ��܂��v����������ꍇ�ɇA�́u�ό��E���N���G�[�V�����̐U���v�Ȃ�Ƃ����̂́A���p�s�̓}�C�������h�A���⒬�͍z�R�������Ƃ��A���̏��⒬�Ƃ����p�s�����Đ�������ƕ����₷���A���p�s�̗ǂ��Ƃ���A����̗ǂ��Ƃ���Ƃ����悤�ȕ������ł���Ǝv���̂ŁA��������i�ōH�v���Ă�������������̂��ȂƎv���܂��B �i�H�{�ψ��j��Ԍ�̎����ł��ˁA�����v����r���������ł�����ǁB����ł͐헪�I�{��Ƃ������ƂŁA�����Ɍf���Ă���킯�Ȃ̂ł����A����������Ƌ������Ă��炦�Ȃ����ȂƂ������Ƃ�����܂��āA���̂��Ƃ������Ƃ��̒��ɏ�����Ă��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B �i������j����̈ψ�����ϋɓI�Ȉӌ����o�܂�������ǁA�ق��ɂ������܂��B �i�����ߗY�ψ��j35�y�[�W�ł����A��ʖԂ̐����ł���܂��B���k�n��͋�`���n�ߍ������H�̂����鍂����ʖԂ���������Ă���܂�����ǁA�������A����ɐڑ��������H�Ȃ�A���邢�͒n�擹�H�Ԃ̐������x��Ă���悤�Ɏv���킯�ł��B���n��͂����܂ł��Ȃ������L���̊ό��n�ł������܂��B�n�擹�H�Ԃ̐����̐i�W�ɂ���Ċό��Y�Ƃ����ɂ����n��o�ς̔g�y���ʂ��傫�����҂ł�����̂��Ǝv���킯�ł��B���A�m���ɍ��͐[���ȍ����̎��Ԃɂ���킯�ł�����A����̌������Ƃ͗}�������Ƃ������������ɂ���܂�����ǁA��͂蓹�H�����͒n��o�ς̔��W��}���ł͕s���Ȃ��̂ł���B�����v���܂��B���̂悤�Ȋϓ_���炻�̍\�z�Ȃ�A���邢�͐V�s�̌��v��ɂ����āA���̕K�v���Ƌ�̍�������ƑO�����ɋ����\���ɂ��Ăق����B�����v���킯�ł����������ł��傤���B
�i���������ǒ��j���̍��ی𗬁A�n��Ԍ𗬂��܂��ẮA(3)�̕��̓��e���炢���܂��ƁA��ʂ̐����A���ʐM�̐����Ƃ�������ɂ����Ƃ��낿����Ɠ��肫��Ȃ��ʂ�����܂���(4)�̕��́u���y���Ƃ�Ƃ����Ă�܂��v�̕��֎��グ���o�܂��������܂��B�ł�����A���A�����ψ����猾��ꂽ�悤��(3)�̕��łȂ����ƌ�����Ƃ����ł͂Ȃ��Ƃ�������Ȃ��������m���ɂ���܂��B �i������j�ق��ɂ������܂��B �i�p�ψ��j17�y�[�W�ɂȂ�܂����A���q����ւ̑Ή�(2)�̍Ō�̍s2�s�ɂȂ�܂����A�u����A���̂悤�ȏɑΉ����邽�߁A����w�̐��I�Ȑl�ފm�ۂƍ����I�Ȋ�ՂÂ��肪���߂��܂��B�v�ƌ���ł���܂����A�����A������ɂ��Ă͐��I�Ȑl�ށA�����I�Ȋ�ՂƂ����̂����̖ڂɂ�������킯�ł����A���q����ɂ��āA�������炱�������ӂ��Ȑ��I�Ȑl�ދy�э����I�Ȏx���B���⒬�Ƃ��܂��Ă͏o��A�ӂꂠ���̏�Ƃ������ŔN���A�Ώ�V���Œj�����J�b�v�����O������Ƃ������Ƃ�����Ă���܂����A���̂悤�Ȏ��Ƃ����p�s���ł͍s���Ă���܂��ł��傤���B �i���������ǒ��j���������J�b�v�����O�Ɋւ��܂��Ăł��ˁA�Ώ�V���Ƃ������������C�x���g�I�Ȃ��̂͂Ȃ��ł�����ǁA�������k���Ƃ�������u���Ă���A���������J�b�v�����O�ɓK���ǂ����͂킩��܂���ǁA�����������I�Ȃ��Ƃ͂��Ă���܂��B �i������j�Ώ�V���Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ��ǂ��A�C�f�A�ł��ˁB �i�p�ψ��j�����K����̒j�����A��͂肻�������ӂ��ȊO��������������Đ���Ƃ������ɓ����Ă��������āA�����͎q����݂��Ă��炤�Ƃ����ӂ��ȍs���I�ȉ�������x������Ƃ��Ă��������Ȃ��Ə��q������A�����̕�����ɖڂ����s�������Ȃ킯�ł����A���t�͈����ł��������͐��Y���������܂���B��͂�Ⴂ���́A���ꂩ�琶�Y�����グ�Ă����q��Ă̂ق�������������̓I�Ȏx����������\�z�Ƃ��Đ���Ƃ����荞��ł������������Ǝv���܂��B �i������j���̑��ɂ���܂��B �i���������Lj��j���c�đ�13���u�V�s�̏������v�ɂ��Đ��������Ă��������܂��B �i������j�ψ��̊F�l���炲�ӌ����������������Ǝv���܂��B �i�I�R�ψ��j���̏��ψ���ł��A���Љ���������ʂ�ł����A�\�a�c�������Ƃ������t�͌������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��͂荡��̏��⒬�Ǝ��p�s���ꏏ�ɂȂ�Ƃ�����ԑ傫�ȗ��_�͏\�a�c�Ɣ���������ɂȂ��B�S���I�ȃC���[�W�Ƃ��܂��ď\�a�c�͐X���A�������͊��Ƃ����ӂ��ɂ悭�����Ă��܂��B����̍�����������������Ƃ������ƂɂȂ�Ώ\�a�c��������L����s���n��ɂȂ��Ƃ������Ƃŏ\�a�c�������Ƃ����͍̂����̈Ӗ����炵�Ă��������Ȃ��Ǝv���܂��B �i������j�������܁A�u�\�a�c�������v��S�ʂɑł��o���ׂ��Ƃ������ӌ��ł����A���ɂ���܂��B �i�ޗLjψ��j���͂��̑O�A10���ɏ��ψ������܂��āA���ψ���ł̎�Ȉӌ��Ƃ������Ƃŏ�����Ă���܂�����ǁA�\���������ɂ����Ă��炾�炾��Ƃ���̂́A�D�܂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B������x�܂Ƃ߂ăC���p�N�g������\���ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͘b�������Ă���܂��B���������Ă��������������ł����Ƃǂ̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�̂��ψ��̊F����o���Ă������������Ǝv���܂��B�u�����Ƃ��Ă͂��̒��x�ł悢�̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��u�V�s�̖��͕̂K������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�u�V�s�̖��̂͂���Ȃ��v���Ƃ��B �i�p�ψ��j�����ǂ̐����ł���͊m�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����O�u�����������̂ł����A��������܂��Ƈ@�ƇB�A�C�ɕ����ꂽ�Ƃ����\����3���g���Ă���܂��B����قǕ����ꂽ�Ƃ��������g�����Ǝ��́A���͂�����x�A�����B�̒u����Ă�����Ɏ��掩�^���āA����Ŗ������Ă���̂ł͂Ȃ����ȂƂ����C����킯�ł��B�����ƊO�ɍU�߂�悤�ȗ͋����\��������Ƃ��V�s�����\�z�̂Ȃ��ɂ͈�����Ă������������Ǝv���܂��B �i���������Y�ψ��j���A�ޗǂ����b���ꂽ�悤�ɁA�Ⴆ�A��Ȃ̉ԉA���ǂ��̈��㒬�A�S���Z���ăC���p�N�g�������ł��B�������������̂�~�����̂ł�����ǁA�ł͉����ƌ�����ƁA�C���p�N�g�̋������̂��܂��A�o�Ă��܂���ǂ��B��̘b��ɂ��Ă����������炢���Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j�����܂�4�������Ă���̂ł�����ǁA���̒������I�ԂƂ������Ƃł����B �i������j����A�������������ʂ�A����́A�����܂ňĂł����Ă����ɂƂ���Ȃ��ŁA���������̂��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂�����Α傢�Ɋ��}�������܂��B �i�r�c�ψ��j4�̈Ă��o���Ă���̂ŁA�������ɍi��Ƃ������ƂȂ̂ł����B����Ƃ��A���̑��ɗǂ��Ă����������ɂȂ邩������܂��A�������ĂƂ��Ă͈�ɍi���Ă������Ƃ������ƂȂ̂ł��ˁB �i������j�����ł��B �i�r�c�ψ��j�V�s�̖��̂���ɍi��ƁB �i������j����A�V�s�̖��̂���ɍi��̂ł͂Ȃ��āA�������Ƃ������̂���f���悤�ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA������A���ψ���ł��ӌ����o���̂�����ǂ��A���������ӂ��Ȃ��͍̂ŏI�I�ɂ͋��c��Řb�������Ƃ������ƂŁA���A�c��ɏ���Ă���킯�ł������܂��B �i������j�V�s�̖��̂Ƃ������A�������̂Ȃ��Ɂu���p�v�Ƃ����̂ł́A�����_�ł͂���͂�����Ƃ܂����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁZ�Z�ɂƂ����̂ł����āA��������ł悩�����̂��ȂƎv���Ă���܂��B����͐V�s�̖��̂����Ȃ��Ă��A������̓s�s���Ƃ��ẮA������͋����Ƃ��A�����Ȍ`�̌��t������̂ł͂Ȃ����B�����ĐV�s�̖��̂�����K�v���Ȃ��ł��B �i�����ߗY�ψ��j����(�@)�ɐV�s�̖��̓��Ƃ���Ƃ������Ƃł����A�������ꂽ�Ƃ���A�Ⴆ�A�B�ł���u�\�a�c�������ɕ����ꂽ��������s�s���p�v�ƂȂ�܂��B����ł́A��͂茻���_�ł͒�R������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃňӌ����o�Ă���܂��B�ł�����A�����Ƃ����ƁA������̍������c���i��ł����ĐV�s�̖��̂����܂�Ƃ������A�ǂ��������̂�t���邩�A����ɂ���ĕς��Ǝv���܂��B�������̎����̗̂������ƁA�����̖̂��̂��t���Ă���̂��A���Ȃ葽���ł��B�ł����玖���ǂł͂����ɐV�s�̖��̓�������̂́A��������ȂƂ������Ҋ��������Ă����Ǝv���܂��B �i�I�R�ψ��j���A�Z�Z�̂Ƃ���ɐV�s�̖��̂��Ƃ����b������܂����B�Ⴆ�A�V�s�̖��̂��\�a�c�������s�ƂȂ����ꍇ�͇B�ɓ��Ă͂߂�ƇC�ł������ł����A�\�a�c�������ɕ����ꂽ��������s�s�\�a�c�������ɂȂ��Ă��܂��킯�ł��ˁB�����_�łǂ��܂ł�����m�肷��̂��킩��܂��A��͂肻�������Ƃ�����l�����Ă���������ƂӂƋC�����܂����B �i������j�V�s�̖��̂͂�͂�@��̋��c��ֈڍs���Ă���̘b�ɂȂ�Ǝv���̂ł����A�������̂����܂����ꍇ�ɁA����͓����̂��Ƃ������ƂŁA���̑O���͘b�������Ă����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃŋ��c���Ă��������Ă���܂��B �i�p�ψ��j�O��̈ψ���̎��ɂ��A�\�����Ǝv���̂ł����B���A��͂�X���̏\�a�c�s�Ə\�a�c�Β��������悤�ȍ�Ƃ�i�߂Ă���܂��B���̂Ȃ��ŁA�������ɐV�s�����\�a�c�Ύs�Ƃ��悤����Ȃ����Ƃ����C�^���������܂��Ă���܂��B����Ƃ��A��X�n��ɂ͏\�a�c����������킯�ł�����X���ɉ������邱�ƂȂ��A���̏\�a�c�Ƃ����\�a�c�Ƃ��������l�[���u�����h�������̐V�s�ɂ͎��͓���Ăق����Ǝv���܂��B �i������j�V�s���łȂ��Ĉ�s�s���̂ق��̈ӌ����������������Ǝv���܂����B �i����ψ��j�B�C�A���ꂪ�Ⴆ�Z�Z���\�a�c�������Ƃ������F���o���āA�s�ł��܂��ł����p�ł���C�͂悢�ł���ˁB���Ⴀ�Ⴆ�·A������܂����A�A�̂Ȃ��Łu���j�E�����E���R���ʂ�������s�s�v�Ƃ���܂����A�Ⴆ�Ζ��O���\�a�c�������s�ɂȂ����Ƃ���A�������s�s�\�a�c�������s�B���̂Q�̃C���p�N�g�͋����Ǝv���܂��B���̕ӂ܂ōi���Ă���������A���ƐV�����s�̖��O�Ƃ������C���킹�ƌ����₷���悤�ȃC���p�N�g�̋������O�Ƃ����̂������ƌ��܂��Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�����Ă����ōi�荞�܂Ȃ��Ă������̂ł͂Ȃ����A�V�s�̖��O�ƈꏏ�ɃZ�b�g�ōl���Ă����Ƃ������ƂŁB �i������j���������Ă��������܂����A�ψ��̊F�l�������ł����B�i�u�����ł��v�̐��j �i���������ǒ��j������30�y�[�W�ɂȂ�܂����A�V�s�̏������Ƃ����Ƃ��낪�S���̂܂܂ŃT�u�^�C�g���́u�����E�����E�A�g�ɂ��w�V�����܂��x�̑n�����߂����āv�Ƃ��������Ɏ~�܂邱�ƂɂȂ�܂��B���̕ӂ̂Ƃ�������m�F�����Ă������������Ǝv���܂��B �i���������ǒ��j���̏�ōŏI����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA5��ځA6��ڂ̋��c��\�肳��Ă���܂��̂ŁA����܂ł̊��Ԃ͂܂��P�\����܂��B �i���������Y�ψ��j�����LjĂƂ������A�C�Ӌ��c��̊F����ɏh��Ƃ������낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �i������j���܂ł̂��낢��Ȉӌ��܂��āA������A���ψ���ł�낵�����肢�������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B �i�r�c�ψ��j�����̋����{���ڂɂ��Ă������������Ǝv���܂��B��͍����̕��j�ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɍl���Ă��܂����B�Γ������Ȃ̂��z�������Ȃ̂��A���̕ӂ͂͂����肵�Ă������������B���ꂩ�獇���̊����A����͒�܂��Ă���܂�������ǁA�m�F�����ł��B�V�s�̖��́A����͍��A�b�������Ă��܂������B���ꂩ��V�s�̎������̈ʒu�A���Y�̎�舵�����ǂ̂悤�ɍl���Ă��܂����B����Ɨ��N�͎��̕��̑I���ł����A�ė��N�͎��p�s�̑I���ƂȂ��Ă���܂��B�I���̎�舵���͂ǂ̂悤�ɍl���Ă��܂����B���ꂩ��A�m���Ȃ��Ƃł͂Ȃ��ł������10�N��̍l�������ǂ̂悤�Ɍ��Ă��邩�B�����Ƃ���ɂ��ƁA10�N��͂܂�2�i�K�����ō�������Ƃ����悤�Șb���������̂ŁA���̕ӂ͂ǂ̂悤�ɍl���Ă��邩�Ƃ������Ƃ���������̊�{���ڂƂ��Ċm�F�����Ă������������Ǝv���܂��̂ŁA�ЂƂ�낵�����肢���܂��B �i������j���̍��ڂ̒��g�́A�@�荇�����c��Řb���������Ƃ��啔���ł���Ǝv���܂����B �i�r�c�ψ��j����́A����ł����Ǝv���܂����A�@�苦�c��̑O�Ɍ��߂Ă�������������Ǝv���܂��B���̎��⎖���̂Ȃ��ɁB �i�����ߗY�ψ��j���̖��͍������ŋc�_����̂ł͂Ȃ��āA���������m�F���悤�Ǝv���Ă����킯�ł����A���͔C�Ӌ��c��Ȃ킯�ł��B�V�s�̌��ݍ\�z�ƍ����V�~�����[�V�����ȊO�̂��̂����ݍ��ނ̂��B����������ς�A������ƈψ���Ō��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�ł����炻�ꂪ�o�Ȃ����荡�̎���̋c�_������͓̂K���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B��ق̕��̈�s�O���̔C�Ӌ��c��ł͊�{�T���ڂɓ��ݍ��ނƂ������Ƃɂ����킯�ł��B����́A��A����̊Ԃł��낢��ӌ������Ă��������āA�ǂ����������ł����Ă������Ƃ������Ƃ��܂������Ă��������āA���̈ψ���S�̂ŋ��c����B���������̂���ԃx�^�[����Ȃ����ȂƎv���܂��B �i������j���ƕ���łǂ��܂œ��ݍ���ŁA���̋��c��ɋ��c�ĂƂ��Ă������Ƃ������Ƃ����c���܂��̂ŁA���C���肢�����Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j���͂��̍��ڂɂ��ẮA���ɑ�ق̕��ł͔C�Ӌ��c��ł���Ă���܂��B������A���ꂪ���܂�Ȃ��ŗႦ�Ζ@�苦�c��ɓ������ƂȂ����ꍇ�ł��ˁA�ǂ����̒��݂����ɂ����̂ق��ɓ���܂Ȃ��ƌ����Ė@�苦�c�����Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂ŁA��͂�\�Ȍ���c�_�_���l�߂Ă����Ė@�苦�c��ɓ����Ă����̂��K�v���Ƃ����ӂ��ɍl���܂��B����́A��͂葁�����߂Ă����āA����ς���ׂ��ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă���܂����B���낢��J�ł́A���낢��Șb���������ė���̂ŁA������Ƃ����Ή������Ă����K�v������Ǝv���܂��B �i������j����܂łɕ���Ƌ��c�������܂��Ă����܂œ��ݍ���ŋ��c�������Ƃ������Ƃ��F����ɂ����肵�܂��̂ŁA���̎��͂�낵�����R�c�������������Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j����̗\��͂��ł����B �i���������ǒ��j���̂Ƃ���̍�Ƃ̐i�ݏ�����܂�����ǁA11���̒��{�܂łɂ͊J�Â������ƍl���Ă���܂��B �i������j�ق��ɂ������܂��B �i�r�c�ψ��j���ꂪ�A�ŏI��ł����B �i������j�܂��ł��B �i�r�c�ψ��j12���c��O�ɂ͂��������Ƃ������Ƃł����B �i���������ǒ��j�S���łU��̋��c��̊J�Â�\�肵�Ă���܂��āA���A�\���グ�܂����ʂ�5��ڂ�11���̒��{�܂łɂ��Ƃ������ƂŁA�ŏI�̋��c��ɂ��܂��Ă�12���̏�{�c��O�ɂ͊J�Â������Ƃ����X�P�W���[���ōl���Ă���܂��B �i������j�ق��ɂ������܂��B �i�ޗLjψ��j8���Ɋ@�V�����Ǝv���܂����A�u�����̌��ԃC���g���l�b�g�A���Ԑ������}���������㉟���v�Ƃ����悤�ȗ[���L���ōڂ��Ă���܂����B��������Ă݂���n��̃C���g���l�b�g�����鐮�����Ƃ̂��߂ɍ��A�����⏕�̑ΏۂƂ��āA16�N�x�܂łƂȂ��Ă���̂ō��A���������邽�߂ɋ삯���ݗv�]���������Ƃ����悤�ȋL���ł����B�����A�����̈��̒n�悪�����āA�㉟���ɂȂ�x�����Ƃł���A�N�Ȃ��L���ł����A�������Ȃ��ꍇ��3����1������ǂ�������������������2����1�܂ŗ��Ƃ��B���Ȃ�傫�Ȏ��Ƃ̂悤�Ȃ̂ł�����ǁA��̓I�Ɍ��Ă݂�Ɩ{������͑�فE����E�c��E���⒬�̍������c��]�X�Ƃ����L���������āA�����Ă݂�Α�َs�Ő\������i�K�ɗ��Ă���Ƃ����悤�ȏ�������킯�ł��B�����A���̎��ɂ��Ă��킩��̕���������f���������ȂƁB�����A�����킩��Ȃ���A���̎��ł������ł��B�Б��ł͂����������ƂŃC���g���l�b�g���g���Đi��ł���B�䂪���ɂ͏��⒬�Ƃ̊W�͍L��s���g��������킯�ł����A�����ꂱ�̂܂܂Ő��ڂ��Ă����Ə��₳��͑�ق̕��Ƃ��C���g���l�b�g�A���p�̕��Ƃ��C���g���l�b�g�ƂȂ�Α�ςȂ��Ƃ��Ǝv���̂Ŏ��Ƃ̎��g�݂̂��Ƃ��킩���Ă�����ǂȂ����������������B�����A�����̎{��Ƃ��Đi�߂Ă���Ƃ���Ό��̎x�����ł����B�Ⴆ���w���Ƃ��A���Ƃ��������������̂������Ă��ǂ������̂ł͂Ȃ����B������8���̋L���ł�����A���̈ψ����7���ɔ������Ă���킯�ł��B���̕ӂ̎�������������Ǝv���̂ł����B���Ƃ��̂��̂����Ȃ��Ƃ����Ȃ�ʂł����A�����A���������w�i������Ƃ���A�K�v���Ƃ���w�i������Ƃ���Ό������Ă����K�v������̂ł͂Ȃ����B�����v���Ă��f�����Ă���̂ł��B �i����ψ��j�C���g���l�b�g��Ր������ƂƂ������ƂŁA�����Ԃ͒��̒��̖����ԁA�w�Z���܂߂āA�����13�N�x�łƂ肠�������̕��͏I����Ă��܂��B�����Ȃ̕⏕���Ƃł��܂����B �i�ؑ��������������j���A�������Ⴂ�܂����悤�Ɋe���̌��I�{�݁A��������t�@�C�o�[�Ō��ԂƂ����v��ł������܂��B��َs����͖����̒��̃p�\�R���̐�����������ƒx��Ă���Ƃ������ƂŁA����n��C���g���l�b�g�̎��ƂɎ���������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B �i�ޗLjψ��j����ŁA�킩��܂������A�������͂ł��ˁA�������㉟���ɂȂ�Ƃ��A�������邱�Ƃɂ���č��������i�����Ƃ��B�������N����16�N�x�܂łł��B�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���Ƃ���A�K�v���̖�肪���R�ł�����ǂ��A���������2����1�ɂȂ�܂���B���������w�i������Ƃ���Β������Ǝ���3����1����Ă��܂��ƍ�������Ƃ��ɂ�����͏��O�����̂��Ƃ����悤�ȋ^��_�͎c��킯�ł��B�ł���A���̎x���̏������������������Ȃ���A��͂肱�̌v��̂Ȃ��ōڂ���K�v������̂��Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��������Ă����������ق��������̂ł͂Ȃ����B�����v���Ă��܂��B �i������j�ق��ɂ������܂��B |








