 |
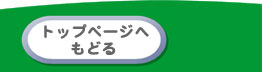 |
|
���Â̒n��C�Ӎ������c��@��T���c�L�^
|
| �P�@�J�Ó����@�@�@����15�N11��12���i���j�@�ߌ�1��30��
�Q�@�J�Ïꏊ�@�@�@���p�s�c��@�S�����c� �R�@�o�Ȏҁ@�@�@�ψ��E�E�E�E�@13���i�ɓ����q�ψ����ȁj �S�@��c���� �T�@��c�L�^ �i������j�{���͑�ς��Z�����Ȃ����o�Ȃ��������܂��Đ��ɂ��肪�Ƃ��������܂��B �i���������ǒ��j���肪�Ƃ��������܂����B
�i���������ǒ��j�{���̏o�Ȉψ��́A�S�ψ�14���̂����A�ɓ����q�ψ������p�̂��ߌ��Ȃ���Ă���܂��B���ꂩ��A�p�ψ��ɂ��܂��ẮA���p�̂��ߎ�x��ďo�Ȃ����������Ƃ����A�����������Ă���܂��B���������܂��āA�葫���ł���܂��ߔ��������Ă���܂��̂ŁA�{��c���������Ă��邱�Ƃ����\���グ�܂��B �i������j���ɁA��c�^�����l�̑I�o�ł������܂����A���c���c�^�c�K���ɂ��܂��ċc�����w�����邱�ƂɂȂ��Ă���܂��̂ŁA�{���͌I�R���L�ψ��A�p���O�ψ��̂���l�ɂ��肢��\���グ�܂��B �i���������ǒ��j����ł́A���c�đ�14���ɂ��Ă����������Ă��������܂��B �i�r�c�ψ��j���������ł������܂�����ǂ��A�@�苦�c��ɂ����Č��肷��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���܂����A���̑O�ɔC�Ӌ��c��ő��̕��ł́A���炩���߂̌����������Ęb�������Ă���܂����A������̕��ł͂���͂��Ȃ��̂ł����B �i������j����͍��A���b���Ă����������ł������܂��āA�ǂ������ӌ����o���Ă������������Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j���͂���ς�A�����ŁA�C�Ӌ��c��̒��Ō���ɂ͎���Ȃ��Ă����������A���o���ׂ����Ǝv���܂��B�Ƃ������Ƃ͕ғ�����������Ƃ������������B����ƁA������͑O�ɂ�����Ƃ��b�������ł͂Ȃ��̂ł�����ǂ����������Ƃ�����10�N��ɂ܂���������悤�Ȃ��b���������悤�Ɏf���Ă��邪�A���̓_�ɂ��ē�i�K�����ł��̂��A���̕ӂ��܂߂Ă����ي肢�܂��B �i������j����́A�����قƂ����������p�s�̕�����͑Γ��̍����ł��肢�������Ƃ����ӂ��Ȑ\����������⒬�ɂ��肢���Ă���Ƃ���ł������܂��B���ꂩ��A10�N��̓�i�K�����Ƃ����ӂ��Ȃ��b�́A�ǂȂ����ǂ������ӂ��Ȍ`�Ő\���グ�����킩��܂���ǂ��A���������b�́A���͂Ȃ����̂Ǝv���Ă���܂��B �i�r�c�ψ��j��������A���̓��������Ƃ������ƁA���ꂩ��10�N��ɍ�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������ƂŊm�F�������Ă����ł����B �i������j�i10�N��ɍ�������Ƃ������Ƃ́j�Ȃ��Ƃ��A����Ƃ��B�ǂȂ������������ӂ��Șb���������͂킩��܂���ǂ��A�����Ȑl�̍l����������̂��Ǝv���܂��B���݂̒i�K�ʼn��N��ɂǂ�����Ƃ����ӂ��Ȃ��Ƃ͂����ȎЉ��̕ω�������ł��傤���A�����������Ƃ����ɂ߂Ȃ��炢���ȉ\��������Ǝv���̂ł��B�����A���̎��_�łǂ����邱������Ƃ����ӂ��Ȕ����͂Ȃ��Ȃ��ǂȂ����o����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����͎��̎����ł������܂����A�ψ��̕��X�ł��b�������������o���Ă������������Ǝv���܂��B �i�ޗLjψ��j�P���ɍl���܂��Ăł���B10�N��Ƃ������͍��̂��̓���@10�N�̒��ŁA�Ⴆ���������ă��X�g�����A���X�g���Ƃ����ΓK�Ȍ��t�ł͂Ȃ��ł����A��������͌o�c�������y�C���Ă����悤�ȏ�Ԃɂ���Ƃ���A���͂���ς�A�E���̐��ł���Ƃ��A���ꂩ��A�ǂ�����邩�Ƃ����悤�Ȗ�肪���R�A���ʋN���Ă���B�����V�~�����[�V���������Ă������ł����B���������10�N�͍��̂��낢��Ȏ{��A���邢�͓���@���g���Ď蓖�����Ă��������āA���̒��Ōv��I�ɐE���̏ꍇ���ƍ̗p�����ꎟ�~�߂�Ƃ��A�̗p�͍ŏ����Ɏ~�߂āA���ƑސE�͂ǂ�ǂ����Ă�����10�N��ɂ͑̐����������Ƃł���B�����Čo�c�����v�ł���̂���Ƃ����悤�Ȗڈ������̂ł͂Ȃ��̂��납�B�Ƃ����ӂ��Ɏ��͎v���̂ł��B��������ƁA���ƍ���10�N��ɂ܂�����@��ʂɒ�߂�Ƃ��A�������ǂ������ӂ��ɑ��i�����邩�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ́A���̌�̍l�������낤�Ǝv���̂ł�����ǁA���ǂ��Ƃ��ẮA�����������Ƃ����҂��Ȃ���A���̂����ɂ��Ƃ���A�܂�10�N�Ԃ͂��̍����V�~�����[�V�����̂Ȃ��Ői�߂Ă����Ƃ������Ƃ��x�^�[�ł͂Ȃ����낤���Ƃ����悤�Ȏv���͂��Ă���܂��B�����A�����̑����Ȃ̐V����������ƍ������Ȃ������ꍇ��1���l�ȉ��̐l���̒����ɑ��Ă̑Ή��Ƃ����̂́A���Ȃ茵�����Ȃ�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����ԁA���Ԃɗ��Ă���悤�ł�����A����Ȃ̑Ή�������ς�A�ǂ����ł���������Ə���͂�ŁA�����čl�������܂Ƃ߂Ă����Ƃ����K�v�͂���Ǝv���܂�����A�C�Ӌ��c��œ��Njc�Ă͂��邩�����Njc�Ă͂��邩�ł͂Ȃ��ĔC�Ӌ��c��ő��݂ɊF�̎v�����c�_���Ė@��Ɏ������ނ��������܂Ȃ����Ƃ������Ƃ�b�������Ă��������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l���܂��B �i������j���̂悤�Ɏ��v�炢�܂��B�ψ��̊F����̔��������肢�������܂��B �i�����ߗY�ψ��j�Ō�̍��Y�̎戵���ł�����ǁA�u���Y��v�̎戵���ɂ��Ă͍l���ĂȂ������̂ł����B���邢�́A���̂��̕��������Y��̎戵�����܂ނƂ������߂Ȃ̂��A���̂������������Ƃ��f���������̂ł����B �i���������ǒ��j������ꕔ�����g�������܂߂Ė@�苦�c��Ō��肷��Ƃ������Ƃōl���Ă���܂��B �i�����ߗY�ψ��j���Y��̎戵�����܂ނƂ������߂ɂȂ�A�T�d�Ȕz�����K�v���Ǝv���̂ł���B�Ƃ������Ƃ͍��Y��̖@�I�ȉ��߂ɂ��ẮA�܂����Y��͓��ʒn�������c�̂ł���Ƃ������ƁB�]���č��Y��͖@�l�i�������Ă���ƁA�����������ƂȂ̂ł��B�@�l�i�������Ă���Ƃ������Ƃ�����A���Y��ɑ����邻�̍��Y�܂��͌��̎{�݂Ƃ����͎̂s�����̏��L�ł͂Ȃ��č��Y��̏��L�Ȃ̂���Ƃ������Ƃ��@�I�ȉ��߂Ȃ킯�ł��B�ł�����A���a47�N4�����������̎����A��͂���Y��͕ʓr�����ɂ��Ă��܂��B���ꂩ��A����̎�������������6�y�[�W�ڂŁA�m��ہE���Y�E�ۊ����̍������c��A����̕������Ă��������B�u������Y��͕�����Y��Ƃ��ĐV�s�Ɉ����p���v�Ƃ����������Ƃł��B�ł����玄�́A��ʍ��Y�Ǝ��L���Y�A�܂��s�����Y�Ɠ���������Ă��܂����A�����炭���⒬����̂ق��ɓ��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���̍��Y�悻�̂��̂́A��͂肱�����������ŕʓr�������Ă����Ȃ��ƁA�Ȃ��L���̂Ȃ��s������ɂ����������Ƃ����߂�Ƃ������Ƃ͎�s���߂�����Ȃ��̂��ȂƂ������������܂��B������ӂǂ��ł����B �i�O���ψ��j���Y��Ɋւ��č��A�����ψ������������Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�����̑O���ɍ��Y�悪����A����͂���ς���Y��Ƃ��Ďc��̂ł����āA���ꂪ�s�̍��Y�ɂȂ�Ƃ����悤�Șb�́A�������������Ӗ��ŏ������̂ł͂Ȃ��Ǝv���̂�����ǂ��A���������Ƃ��������Ӗ����l�����邩��A�����́A�͂����茩���͓��ꂵ�Ă����Ȃ��ƁB �i�����ߗY�ψ��j����͍��Y�ɗ��ޖ��ł�����A�悭���̕��Ƒō��������āA�ǂ������\������Ԃ����̂��A���̓_�A�ŏI��ł����\�ł����炫�����Ƃ����`�ŕ\�������Ă����Ȃ��ƁA��X�A���������Γ�����ɂȂ�Ǝv���܂�����A�����͂�����Ƃ���Ă��������B �i������j����ł́A��قǂ̂�����10�N��Ƃ����܂����A���̕ӂ̂Ƃ���̍l�����Ƃ������̂���o���Ă������������Ǝv���܂��B �i�ޗLjψ��j������̕����͂����肵�Ă��܂���10�N�i10�N��̓�i�K�����j�Ƃ����b�͂Ȃ������̂��Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j���̍����̕��@�ŁA�܂��@�����ς��܂��ς��Ǝv���܂����A����̖@���ł͂����������Ƃ͍l���Ă��܂���Ƃ������Ƃ��m�F���Ă������������ł����ł��B �i������j�����ł����B�ł́A���̂悤�Ɋm�F�������Ă��������܂��B �i�r�c�ψ��j������A�u�V�s�̖��̂̑I����@���܂߁v�Ƃ������Ƃ́A����͖@�苦�c��Ō��߂�킯�ł�����ǂ��A�����ŗႦ�Έ�ʒ�������V�s�̖��̂��W����Ƃ��A�����������Ƃ͍l���Ă��܂����B �i���������ǒ��j��قǐ\���グ�܂����̂́A�V�s�̖��̂ɂ��Ă͑I��̕��@���܂߂āA�ǂ������`�ŁA���傷��̂����Ȃ��̂��A���������g���̂��J�^�J�i��F�߂�̂��Ƃ��A�����������I��̕��@���܂߂Ė@�苦�c��ł������Ƃ����`�Ō����������������Ƃ������Ƃł������܂��B �i�r�c�ψ��j�@�苦�c��Ō��߂�̂������Ǝv���܂����A�����@�苦�c��ɓ����Ă��炱���������Ƃ�����Ă���A���܂��ܑ��̕��̗�����܂��ƁA���ꂪ���܂�Ȃ��Ŗ@�苦�c��甲�����Ƃ��A��ꂽ�Ƃ����b�����܂����ɂ��邱�Ƃ�������̂ł�����A��͂肠����x�͔C�Ӌ��c��Ō��傷��Ȃ�A�����������@��b�������Ă������̂ł͂Ȃ����ȁB���͎v���̂ł�����ǁB�@�苦�c��Ō��߂āA���ꂪ������s�������̂�����ǁA��͂肻�̎��͂������Ɏ��x���ŁA�@�苦�c����U����\���������ɂ������炸����Ȃ����ȁB�����l����Ƃ��납�甭�����Ă���킯�ł��B �i������j���̌��Ɋւ��ĂǂȂ����B �i������j���ɂ���܂��B �i�ޗLjψ��j���͂ł��ˁA��ʁA���ψ����������̂ł����A���ψ���ŏ����s�s���̂Ȃ��ɏ��������ʒu�t����Ƃ����Č����������Ă݂��킯�ł��B����������A����ς菬�ψ���̑吨���A����ς荡�A���ψ���ŐV�s�̖��O����ꂽ���̂��������̕����ɂ������Ƃ������Ƃ��ɂ߂č���B����́A�@�苦�c��ŐV�������O������Ă�������������̂�����A����ς荡�͂��̕��͂ɍ������i�̂��̂����������ق��������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ����悤�ȊF����̈ӌ��ŁA�������������ɂ����Ƃ����o�܂�����܂��̂ŁA��Ŏ����ǂ̐��������낤���Ǝv���܂����A����ς荡�A�H�{�ψ��������������悤�ɐV�s�̖��̂͂���Ȃ̂��]�܂����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ������������Ă������ƁA����͍����x���Ȃ��Ǝv���̂ł�����ǁA���ψ���A���̔C�Ӌ��c��Ō��肷�邱�ƂƂ����̂́A����ς��ςł͂Ȃ����Ƃ��������v���܂��B �i�r�c�ψ��j���͍��A�V�s�̖��̂����߂�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��B�V�s�̖��̂����߂邽�߂̕��@���������邩�ǂ����Ƃ������Ƃ�C�Ӌ��c��Řb�������K�v������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ������Ă���ł����āA�V�s�̖��̂����߂�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��B�����V�s�̖��̂����߂邽�߂ɍ��A��ʂ̎s����������̂����傷��l��������̂��Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��A���̔C�Ӌ��c��ŋ��c���邩�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�V�s�̖��̂����߂�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��B �i������j���̒r�c�ψ��̔����ɑ��āA�����閼�̂����肷����@��b���������炢�������Ƃ����ӂ��Ȃ��b���ł������܂�����ǂ��B�������ł��傤���B �i�����ߗY�ψ��j��2��ڂ̔C�Ӌ��c��̋��c�đ�9���̒��ŁA�Q�l����2�Ƃ��ĔC�Ӎ������c��̋��c�Č��Ƃ��ꂩ��A�@�荇�����c��̋��c�Č��Ƃ������̂����������ɏ����Ă���A��X�͂���ŗ�����������Ȃ̂ł��B��������܂��ƁA���̔C���ł͐V�s�̏����\�z�ƍ����V�~�����[�V�����A�������Ƃ̔�r�Ƃ��̕ӂ����e�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂩ��A���A���b���������V�s�̖��̂Ƃ����͖̂@�苦�c��ł��܂��傤�Ƃ������ƂŁA���Ȃ�̍��ڂ����Ɨ�L����Ă���̂ł����A��قǒ�Đ����̂Ȃ��ʼn�A����̋��c�ɂ���Ă���������Ă�����܂����ƁA����������Đ���������܂����B������������ĊT���I�ȕ\���ň�̊�{�I�ȕ����������������̂ł���Ƃ����ӂ��ɗ������Ă��܂��B���������āA�C�Ӌ��c��ɂ����鋦�c�Ƃ��Ă͂��̒��x�̓��e�ŁA���Ƃ���ȏ㓥�ݍ��ނƂ������Ƃ͂ǂ��Ȃ̂��ȂƎv���܂��B����͎��̈ӌ��ł��B���̒��x�ł����̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂��B �i�I�R�ψ��j������{�I�ɂ͓����l���Ȃ̂ł�����ǂ��A�������̒n��̏����Ă݂܂��ƁA�قڑS���̏ꏊ�Ō��傪����Ă���Ƃ������Ƃ��������܂��̂ŁA�������ɔ��̈ӌ����Ȃ���Ό�������邱�Ƃ��]�܂����Ƃ������x�̍l�����ō���͂܂Ƃ߂Ă͂������ł��傤�B �i������j�ق��ɂ��ӌ��������܂��B �i�T�c�ψ��j���̌I�R����̘b�Ƃ����̂͌���Ƃ����̂́A�I��̕��@�Ɋ܂܂��Ǝv���܂��B�V���ɂ��������̂����Ȃ��Ă��A��������b�����Ƃ���@�苦�c��܂Ŏ����Ă����Č��߂Ă��������̂��ȁB���͂����v���܂��B �i������j�ӌ���������Ă���܂�����ǁA�ł���̌��͂��Ȃ��Řb���܂Ƃ߂Ă������������ȂƂ����ӂ��Ɏv���̂ł����B�v�͌��傭�炢�͂Ƃ������Ƃ����߂Ă������炢�����Ȃ��̂��Ƃ������ƂƁA���ꂩ��A����͖@�苦�c��ɂ킽���āA���������C�ӂ̕��ł͂��̂��炢�̂Ƃ���ł����̂ł͂Ȃ����Ƃ���2�̈ӌ����o�Ă��܂����B �i���������Y�ψ��j���A2�̈ӌ����o����Ă��܂�����ǂ��A���̒i�K�ł͑I��̕��@���܂߂ĂƂ����Č��������Ă��܂��̂ŁA�@�苦�c��ݒu����ĐV�s�̖��̂��c�_���ꂽ�i�K�ł܂����ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ����̂�����̂ł�����A���i�K�ł͌���̂܂܂ł�낵���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂����B �i������j�ɓ��q�q����B �i�ɓ��ψ��j���������ψ��Ɠ����ӌ��ł��B �i������j�����������ƂŁA�@��̋��c��̕��ł��Ƃ������Ƃɂ��肢��\���グ�܂��B �i�H�{�ψ��j���́A���̊Ԃ̂����i���⒬�j�̕��̒n���������k��̂Ȃ��ŁA�����ł��镽��17�N3��31���ȓ����Ƃ�������������܂����A����́i�u�ȓ��v���j�u�ȑO�v�̕��������̂ł͂Ȃ����ȂƂ����ӌ����o�܂�������ǂ��A����͂������ł��傤���B �i���������ǒ��j���Ɏ����ǂ̕��ł́A�u�ȓ��v�u�ȑO�v�Ƃ������Ƃňӎ������킯�ł͂������܂���̂ŁA�ŏI�̊�����3��31���Ƃ������Ƃő����Ă���܂��̂ŁA���̓��������āu�O�v�Ƃ����悤�ȕ\���ɂȂ�Ǝv���܂��̂Łu�ȑO�v�ł������x���Ȃ��Ǝv���܂��B �i�H�{�ψ��j���������ӌ����������܂����̂ŁA�ꉞ�A���̏�Ŕ������Ă��������Ǝv���܂��B �i�����ߗY�ψ��j����ς�A�u�ȓ��v���u�ȑO�v�̂ق���������������܂���ˁB �i���������ǒ��j�u�ȑO�v�Ƃ����ӂ��ɒ��������Ă��������܂��B �i������j���̂悤�ȕύX���܂߂Č��肵�Ă�낵���ł����B �i���������Lj��j����ł́A���c�đ�15���u�V�s�����\�z�i�āj�v�ɂ��Đ����������܂��B �i���}�������Lj��j������57�y�[�W�ȍ~�̍����V�~�����[�V�����ɂ��Ă������\���グ�܂��B �i������j�������܁A���c�đ�15���ɂ��Đ���������܂����B�܂��A�C�����Ȃ��ꂽ�����Ɋւ��Ă��ӌ��E�����₪����܂�����A�������肢�܂��B �i���������Y�ψ��j���[�f�B���O�v���W�F�N�g������ɂ킽���Ă܂Ƃ߂��Ă���킯�ł�����ǂ��A���̔C�Ӌ��c��͂������c���݂̂Ƃ����\��ɂȂ��Ă���܂��āA�����̖k���V���Ƃ��A���邢�͑�ق𒆐S�ɂ����C�Ӎ������c��ŏ��⒬�̓����Ƃ������ƂŁA12���ɏZ��������A���邢�͂܂��A�c���Ƃ̋��c��܂��āA�����āA�@�苦�c��ɖ]�ޑԓx�Ɛ\���܂����A���ꂩ��A���邢�͎��������蓾��̂��ȂƂ����悤�ȃj���A���X�̕��o����Ă���킯�ł��āB���͒n��̏Z��������ɖ]�ނɂ������āA�܂菬�⒬�̒����̗��ꂩ��A���邢�͋c��̗��ꂩ��A�����Ē�������̗���Ƃ��āA���N�|���Ă������⒬�̂��ꂾ���͂ǂ����Ă����̃v���W�F�N�g�ɓ���ĐV�s�̒��ł����͂ɐ��i���Ă������������Ƃ��������ڂł���A�������������̂�����ɏo����Ă����A���͏Z���ɔ��ɃC���p�N�g��^����������o���邾�낤���A���̔C�Ӌ��c����X���[�Y�ɖ@�苦�c��ւ����Ă������߂ɂ����͕K�v�Ȃ̂��ȂƎv���킯�ł�����ǂ��B�������������̂���������Ă��ꂪ�o�Ă����Ǝv���܂�����ǁA���ɂ��̒��ŏ��⒬���������ꂽ���̂Ƃ��������̂�����̂ł��傤���B���ꂩ��Ⴆ�A���ꂼ��̒����̊F�l�A�r�c�c������̗���A���邢�͒�������̗���ŁA���̒��ɐ���Ƃ�����Ă����āA�������Ȃ��V�s�̂Ȃ��ł��ꂾ���͌p�����Ă���Ă������Ƃ��������̂�����̒����ɗ����邽�߂ɂ����͋������Ă��ꂪ�����Ă����̂��Ƃ������Ƃ�����Η������₷���̂ł͂Ȃ����ȁB�����v���܂�����ǂ������ł��傤���B �i���������Lj��j���̃��[�f�B���O�v���W�F�N�g7�قNj����Ă������܂��B���̂����̂P�Ԃ̃G�R�E�~���[�W�A���A2�Ԃ̃[���G�~�b�V�����s�s�Ƃ���܂����A���⒬�G�R�^�E���̌v����L�q�������̂ł���܂����A�܂��_�ƂƃA�O���r�W�l�X���i�v���W�F�N�g�A���̒��ł��L�@�_�Ɠ��Ƃ��Ă��̕ӂ͂��Ȃ����O���ɂ����ď��⒬�Ŏ��g�܂�Ă��镔���ŐV�s�ɂ����Ă����ꂼ����L�߂Ȃ�����g��ł����悤�Ȏ��ƂƂ��Čf�ڂ����Ă�������������ł������܂��B �i���������Y�ψ��j�������̂悤�Ɍ��Ă��܂�����ǂ��A�����A�ی���ÁA�Y�ƁA����A��ʖԂƂ��ׂĂ������Ă͂���킯�ł�����ǂ��A���̒��ŃG�R�^�E���Ƃ��������������Ƃ������������̂ɑ��āA���ɏ���ƈꏏ�ɂ���Ă������Ƃ����z�������͂���Ă��邵�A���R���ꂩ��̎Љ�̒��Ŏ��グ�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�f���Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�������������̂��Z��������̒��Ő������Ă��������āA�����āA�@�苦�c��̕��ɃX���[�Y�Ɉڍs���Ă������������Ȃ��Ǝv���Ă��b�����킯�ł�����ǂ��B�������Ȃ��̂ł��傤���B �i����ψ��j���A���⒬�ň�ԍ����Ă���̂��A�����ꏊ�����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�Ⴂ�l�B�����Z���o�đ�w���o�Ă������ꏊ���Ȃ��A�܂������N�Ń��X�g���ƂȂ������������ӗ~�͂��邯��ǂ��Ȃ��Ȃ��E�ꂪ���Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B�ł�����A�ǂ����Ă��ٗp��n�o���Ă��������B���ꂪ��Ԃ̒��̊�{�ڕW�ł��B�o�ς�ǂ����邽�߂ɂ͌o�ς̊��A�܂��o�ςƕ����Ƃ��A���̓��F�����R�Ƃ��܂��L���Ă��������悤�ȁA���̓v���W�F�N�g�̒��g�������������g���Ɣ��f���Đ��������������܂����B �i������j�ق��ɂ������܂��B �i�����ߗY�ψ��j���A�����ψ��A���ꂩ�璬����������b����܂�������ǁA����̓��[�f�B���O�v���W�F�N�g�A�T���I�Ȗ��ł��ˁB���ꂩ�獡�x�A�@�苦�ɂȂ�܂��ƌ��v�悪�o�Ă���ƁA����ɂ́A�����Ƃ����ƑO�����ȋ�̓I�Ȏ��Ƃ��o�Ă���Ǝv���܂��B�̐S�ȂƂ���͂������Ǝv���̂ł���ˁB�����ŋc�_���Ȃ���ł��ˁA���A�F���炨�b�������������������̂������Ă���悤�Ȍv����܂Ƃ߂�A���ꂪ�厖���Ǝv���܂��B �i�r�c�ψ��j89�y�[�W�ɂȂ�܂�����ǁA���̒��Ő헪�I�{��Ƃ������Ƃł������Ă��܂����A�V���{�����ƂƂ��Ď��グ�Ă�����Ă���킯�ł��B���̎��Ƃ�簐i���Ă���������Ɖ�X�͎v���Ă���킯�ł��B��قǒ����̂ق�����������ꏊ�̖��A�ٗp�̖��A���邢�͕����̖��Ƃ���킯�ł�����ǂ��A���̒��ɍ��V���{�����ƂƂ��Đ헪���{����Ƃ������ƂŁA���̎��Ƃ������Ă���킯�ł��B��������{���Ă����������Ƃ��O��Ƃ��Ďv���Ă���킯�ł��B����������ĉ�X�͒����̕��Ɂi�������Ă����j�B�t�Ɏ��̕����炨�f���������̂ł�����ǁA���p�s�ɂ͐헪�I�{�Ȃ��̂��B�������������������̂ł�����ǁA���̕ӂ͂ǂ��Ȃ̂ł����B �i������j��قǏ���̒���������ꂽ�悤�ɓ����ꏊ���~�����A��҂��c���悤�ȏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������ӂ��Ȃ��Ƃ͑S�������悤�ȍl�����ł����Ă����Ȏ{���W�J���Ă���Ƃ���ł������܂��B���ɓ����悤�ȍl�����ł���Ƃ����C�����ł���܂��B �i���������Y�ψ��j��ρA�������Ȃ���10�N�Ԃ̍��������ꍇ�̐����Ȃ킯�ł����A���Ȃ��ꍇ�Ƃ����ꍇ�͗�R�Ƃ��Ă���܂�����A��͂荇�����ĂȂ�Ƃ����̒n��̈���I�ȃT�[�r�X����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���̂ł�����ǂ��A���͈�����l����ɂ��Ăł����A��ʁA�n�������w��Ƃ����w��őS���̎s�����W�܂�܂��āA����Ȃ�̂��b�����f���Ă����ꍇ�A���ɐl�������͂�1�^3�A4�A5�N�̂����ɍ팸���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������������ɑ��������킯�ł��B�������c��̐���ƌ�����1947�N����49�N���܂�A�x�r�[�u�[���B���a�Ō�����22�N����24�N�B�N��Ō����ƍ�55����56�B���̔N�オ�ސE����4�A5�N���ӂ��������Ƃ����̂ł��B�e�s�����B���p�s�ł�50����[�����l���Ă���ƐV�s�\�z�v���26�N�x�܂ŁB����ł́A������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������B�����������Ɍ��������������Ă��܂����B����ɂ��ẮA���̂܂�c��̐��オ�ސE����邱�̎��ӂ̒i�K��50���̕�[���ł����l�����ł��ꂪ���v���ꂽ���̂��A����ɂ��Ď����ǂ̍l�����A����͂ǂ������l���������Ă���̂��A������Ƃ��q�˂������ȂƎv���܂��B �i���������ǒ��j���A�����c�����\����܂����c��̐���B�����c��Ȃ킯�ł�����ǂ��B�@�m���Ɏ��p�s�̏ꍇ�����̔N�オ��C�ɐl��������킯�ł�����ǁA���̃V�~�����[�V�����ɂ��܂��ẮA��������������I�ȗv���͂����čl�����Ă��܂���B��ʓI�ȃg�����h�Ƃ��Ă̐��v�Ƃ������ƂŁA�Ȃ�Ƃ����������������������Ǝv���܂��B�m���Ɍ������͎��ǂ����킩���Ă���܂�����Ǎו��ɂ킽���Ă̐��v�A����荞�ނƂ������Ƃ͏o���Ȃ������̂ł��������ł���܂��B �i������j����ς���Ɉ�N�Ԃ̑ސE�҂������Ȃ鎖�Ԃ�10�N�Ԃ��炢�����܂�����ǂ��A����������ƌĉ����ėL���ɐ������Ă������Ƃ����Ɍ��ʓI�ɂ���������̍팸�ɂȂ���̂��Ƃ����ӂ��ȍl���͊��҂��܂߂Ăł������܂�����ǂ��A����͎v���Ă��܂��B �i���������Y�ψ��j�������̋c�_�͔��ɐ^���ɎƂ߂Ă������Ƃ���̔����ł�����ǁB��͂�A���̎����������̌��ʂ�����ŏ��ōŌ�̃`�����X�ł���B������Ȃ�Ƃ��܂�T�[�r�X�������Ƃ����ƍ��܂łǂ�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߂�50�����[���Ă����Ƃ�70����[���Ă����悤�Ȃ��Ƃɂ����s���Ƃ��������͍̂ŏI�I�ɂ͐����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃ��������܂��A�����������Ɍ������吨�ł���܂����̂ŁA���̂��Ƃ͎����ǂ��l���ɓ���Ă����Ă������������B�Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă��������Ǝv���܂��B�c���̏ꍇ�͖@�萔��26���ƍŒ��̓�������Ă�2�N�Ԃł����A���Ƃ�26����@��Ō��܂��Ă��Ƃ͍팸���ǂ����邩�Ƃ������Ƃł��̂ŁA����́A�������͂��܂�����I�ȕ��S�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �i�H�{�ψ��j������Ƃ��f�����Ă������ł����B��قǕ��������ȂƎv��������ǁA�u�X�����Ō����I�ȍs���g�D�v�Ƃ�������������܂���ˁB�O�̃y�[�W�Ő\����Ȃ��ł�����ǁA55�y�[�W�B���̂Ƃ���ŕ����Ηǂ������̂ł�����ǂ��A�䂪���ł͐E���̗̍p�ɑ��Ă͋ɗ͗}���č팸�A�팸�̕����ŁA�����킯�Ȃ̂ł����A���p�s����̕��ł͂ǂ̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����ȂƂ������Ƃō��A�������������ȂƎv���Ă����̂ł�����ǁA�ǂ�ȋ�Ȃ̂ł��傤���B
�i�����ߗY�ψ��j���ꂩ��ł��ˁA���V�~�����[�V�����̂��Ƃ͂����������ĕ��Ƃ��Ă͂킩��܂������A���ꂵ���Ȃ��̂��ȂƂ������������܂��B�����A��͂肱�ꂩ��@�苦���ݒu����Ă��낢��Ȑŗ��̎戵���̖��A���邢�͎萔���E�g�p���̎戵���B�g�p���E�萔���͂��������e���͂Ȃ��Ǝv���܂�����ǂ��A�ŗ��̏ꍇ�ɂ́A���̑O�̍s���̌����Ō��܂��Ƃł��ˁA���Ȃ�A���o�����X������킯�ł�����A�����̌������o�Ă���Ǝv���܂��B�ł�����A���A�F�������Ă���l����̖��A���邢�͕�����̖��B�����ւ�傫�ȃE�G�C�g���߂Ă�����̂ł�����A��͂�l����ɂ��Ă͑����ł��ˁA�E���̒萔�Ǘ��v��Ƃ������̂𗧂ĂČv��I�ɂ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B���ꂩ��A������ӊO�ɍ����Ƃ������Ԃł�����A���������肪���������Ȃ̂��B�O�ɂ��b���������ɂ́A���H�W�̕����������ƁA�����������b���ł������A�����ɂ��Ă���͂�ߌ��ł��邾���ߌ����Ă����悤�ȕ��@�𗧂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B���ꂩ��̍����v�悪����Ă���킯�ł�����ǂ��A���������ʂœ��ɐl����͍X�ɍ��x�A�s���g����������֓����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA����͂܂��E�������h���n�ߐE���l����Ƃ����̂�����ɉ����킯�ł�����A���������ʂł̐l����ɑ��錵�����ƑΉ����������Ƃ���Ă����Ȃ��Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�����������ƂŁA�������ꂩ��̍����v������i�K�ŁA�����ȕ�����l���Ȃ���{���ɍ��������ꍇ�͂����������Ƃŗǂ������̂��Ƃ����悤�����v��A�����^�c�ɂȂ�悤�ɂ�����Ăق����Ǝv���܂��B �i�ޗLjψ��j���̓������Ƃł�����ǁA���͍��A���ǂ��̈����c�����\���グ���w�i�͂��̒ʂ肾�Ǝv���̂ł�����ǁA���̌v��\������Ɛl����̏ꍇ��26�N�x�܂�50���ł����A���������Ă���B�����āA���Ƃ͗ގ��c�̂Ɠ����Ȑ����ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��ƂŁA�ގ��c�̂�荂�������ɂ��ẮA�ǂ�ǂ炵�Ă����āA27�N�x�ɂ͗ގ��c�̂Ɠ����Ƃ悤�ɂȂ��Ă���Ǝv����\���ł���܂��B�����A�����炭�����c��������ꂽ�悤�Ȕ��f���炢���ƁA�ގ��c�̂̒萔�ł����A������߂Ă���A�������v�Ƃ������킹���B����Ȃ����R�A����������Ă���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����蓾��̂ł͂Ȃ����ƁB�ނ���ގ��c�̂̕W���ɍ��킹��Ƃ������A�ގ��c�̂̕W����菭���������v��𗧂ĂĂ����Ƃ����悤�Ȍv�悪�K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���킯�ł��B�����A���̕ӂ̏��͎f���Ă��܂��B�ގ��c�̂̍��킹���́B �i���ʑ��������j�܂��A���̂悤�ȏ��͓����ĂȂ��ł�����ǁA������ς��\���͏o�Ă���Ǝv���܂��B����c�����Ȃ��炻�̊W�͌v��̒��ɐ��荞��ł��������Ǝv���܂��B �i���������Y�ψ��j���Ƃ�����_�́A�s�������v�̎w�j�̍���ɓ������Ăł����A��͂�A�e�ہA�����ہA���ہA�Ⴆ�Ό���ɂ�����܂ŁA�܂�ǂ̕�������ڂ��Ƃɖ��ԂɈς˂镪��Ƃ��������̂����ƍׂ₩�ɍ��肵�Đl���z�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��Ǝv���܂��B���������v������킹�Ă��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�i���������ǒ��j�V�s�̏������ɂ��܂��ẮA��4�c��ɂ����܂��Ă��������E�����c���������܂������A������E���ψ���ōēx�����E���c�Ƃ������肪�Ȃ���Ă���܂����B �i������j����������������܂������c�đ�16���ɂ��āA���ӌ������������܂����炲�����肢�܂��B �i�H�{�ψ��j����A�c����̒n���������k��̂Ȃ��ňӌ������������ہA2�Ԃ́u���j�E�����E���R���ʂ�������s�s�v�Ɨǂ��낤�Ƃ����킯�ł����A���̒��ʼn��������Ȃ��ȂƂ������ƂŁA�͋�����\�����߂ɂ́A���⒬�ł����u�����܂��v�ɊY�����錾�t�͂Ȃ��̂��ƁA����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��āA���̂��Ƃ�K�Ȍ��t������A����ɉ����Ă������������Ƃ����ӌ����o����܂����B������Ƃ��ėႦ�A���j�E�����E���R�E�Y�Ƃ���ނƂ����悤�Ȍ����������邾�낤���A�����ǂ̕��ł����Ƒf���炵������������̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ�������܂����̂ŁA���������Ă������������Ȃ��Ƃ����悤�Șb���o����܂����B�ȏ�ł��B �i�T�c�ψ��j�⑫�ł�����ǂ��A�[�I�ɊȒP�Ɍ����u�Y�Ɓv�Ƃ������������Ă��炢�����Ƃ����������Ƃł���܂��̂ŁA�O���̌��t�͎����ǂɂ��C���������Ƃ������Ƃł������܂��B �i������j�ق��ɂ������܂��B �i�����ߗY�ψ��j�Y�Ƃ�������Ȃ����āu�z�R�Z�p�����������̂������Ƃ����A�����������t����ꂽ���������̂ł́v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��̂ł����B �i�H�{�ψ��j�Y�ƂƂ����̂ɂ���������킯�ł͂Ȃ��ł�����ǁA�����܂��Â��������̂��Ƃ����A���⒬�ŋ����܂��Â���Ƃ������Ƃ��������Ă��܂�����ǁA���������Ӗ������̂��Ƃ�����Ă��炢�����ȂƁB���ꂾ���ł́A�Ȃア�悤�Ȋ���������ȂƂ������Ƃł��B �i�ޗLjψ��j���͎Y�Ƃ�����̂́A�ǂ��̂Ƃ������Ƃ͌����܂��A31�y�[�W�̂��̔��̒��ɓ����킯�ł���B��������ƑO��̕��͂Ƃ̂荇��������B�������ǂ������\���ɂȂ邩�Ƃ������ƁB���ꂾ������ĕʂɂ��ĕ\�����Ă��邩��A���������Ƃ������O���Ƃ��V�s�̖��O��t�����ق��������Ƃ��t���Ȃ��ق��������Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ�̂ŁA�����̏������Ƃ��������������̕����ɓ����Ƃ���A�K�ɎY�Ƃ𗠕t�����悤�Ȃ��Ƃ��K�v���Ǝv���܂�����ǂ��A���͂�����ƍ���Ȃ��悤�Ȋ��������ĂȂ�Ȃ��킯�ł��B �i�T�c�ψ��j���⒬�͓��ʂɑ�َs�Ƃ����s���ċ��c��ɓ����Ă���킯�ł�����ǂ��A���̒��ő�َs�̏������ɂ��Ă͎��ǂ��ɂ��Љ��܂����B�������C���p�N�g�������ė͋����Ƃ����Ƃ�������Љ��Ď��p�s�̏ꍇ�͂�����Ǝア����Ȃ����Ƃ����Ƃ��납��b��ɂ���Ď��グ���Ƃ����Ƃ���ł������܂��̂ŁA�����ǂ�������A��َs�̂��Љ�Ă��炦������̂��ȂƎv���܂����B�ǂ��ł����B �i���}�������Lj��j����ł́A��فE����E�c��E���⒬�̔C�Ӎ������c��̐V�s�������ł�����ǂ��A�u21���I�ɔ��Ă������[�s�s�v�T�u�^�C�g���Ƃ��܂��Ēn��̑��ʂȖ��͂őn�������R���Ɠs�s�@�\���Z�������k���k�̋��_�s�s�ƂȂ��Ă���܂��B �i������j�b���x�e���܂��B �i���������ǒ��j��̑�4�c��œޗLjψ��̂ق�����n��C���g���l�b�g��Վ{�ݐ������ƂɊւ��܂��Ă����₪����܂��āA����ׂ���A���̂��w���������肵�܂��Ă킩���Ă������ƂȂ̂ł�����ǁA���̓_�Ɋւ��܂��Ď�A�������\���グ�܂��B�n��C���g���l�b�g��Վ{�ݐ������ƂƐ\���܂��̂͒n��̋���A�s���A�����A��ÁA�h�Г��̍��x����}�邽�߁A�C���^�[�l�b�g�̋Z�p�Œz���n��̍����k�`�m���Ȃ킿�C���g���l�b�g�̐����Ɏ��g�ޒn�������c�̂��x������Ƃ������Ƃŕ���10�N�x�̑�O�������A�����ĕ���12�N�x�ɍL��I�n����ʐM�l�b�g���[�N��Վ{�ݐ������ƂƂȂ�܂��āA���ꂪ�����ɂȂ��Ēn��C���g���l�b�g��Վ{�ݐ������ƂƂȂ��Ă���܂��B���̓����ɂȂ������Ƃɂ����܂��Ċw�Z�̍����C���^�[�l�b�g�ڑ��A�d�q�����̂̐��i�y�юs���������̐��i�����d�_�I�Ɏx�����܂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���܂��āA���{��̂��s���{���A�s�����A��O�Z�N�^�[�y�ѕ����̒n�������c�̘̂A�g��́B�⏕�Ώیo��{�݁E�ݔ��̔�p�A�p�n�擾��E���H��ƂȂ��Ă���܂��āA�⏕�̊����͓ޗLjψ��̘b�ɂ�����܂����Ƃ���s�����P�Ƃ̏ꍇ��1�^3�A�n�������c�̘̂A�g��̂̏ꍇ��1�^2�A��O�Z�N�^�[�����Ǝ�̂̏ꍇ��1�^4�Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă���܂��āA16�N�x����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������b�A�s�m���ȏ�������킯�ł�����ǁA����ɂ��܂��ẮA1�^3�⏕�̏ꍇ�A������̐��グ���Ă���܂��āA���ꂪ�Ȃ��Ȃ�Ƃ������ƂŁA�����Ȃ����ǂ��Ă���܂����̎��Ƃɂ��Ă͍�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���܂��B����ł͂Ƃ������ƂŐ\���グ�܂��ƁA���������N�Ԃ̍��̘g���������܂��āA���ꂪ���������N��70������80���O��Ƃ������Ƃł��B�Ƃ����g���������܂��āA���ہA�H�c�������Ő\����̗v�]��50�����炢�g���Ă���B�ł�����S�̘̂g�̒���70������80���̒��ŏH�c���ł��ꂭ�炢�ł��̂ŁA��ό������ł��낤���Ǝv���܂��B���⒬����̂ق��́A����13�N�x�Ɏ��{���Ă���܂�����ǁA���p�s�̏ꍇ�͓d�Z�S���Ŏ��{�v��̂Ȃ��ŗv�]���Ă���܂���17�N�x�Ƃ����ʒu�t��������Ă���܂��B���������܂��āA����n��C���g���l�b�g�Ɏ��g�ނƂ���A���̕⏕�̑ΏۂɂȂ�͍̂�����̎s�Ƃ��Ă̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂��B�������A���������N�x�Ǝ��̔N�x��2���N�Ɍ����č�������O�̎戵��������Ƃ����ɂȂ��Ă������܂��B����A���g�ނƂ���A���p�s����Ր��������āA���ꂩ�珬�⒬�Ƃ̂Ȃ����ǂ����邩�Ƃ����A���������v��������č���ǂ����邩�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B �i������j���̑��������܂��B �i�p�ψ��j�C�Ӎ�����������5��ڂƂ������ƂŎc���Ƃ���1��Ə��ψ���1��Ƃ����ӂ��ȃ^�C���X�P�W���[���ɂȂ��Ă��邩�Ǝv���܂��B�����ꖯ�Ԑl����̈ψ��̈Ϗ��Ƃ������ƂŁA���̔C�Ӎ������ɏo�Ȃ����Ă��������܂������A��ʎs�����炻�̓s�x�ǂ������ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����ӂ��Ȏ��₪���ځA���̂Ƃ���ɗ��܂��B���ɒ����������ɑ��Ă̈ӎ������܂��Ă��銴�������܂��B�����ō���A�C�Ӎ���������@�荇�����ւ̈ڍs�ɂȂ�킯�ł��傤���A���̈ڍs�̎d���Ƃ��āA�ǂ������ӂ��Ȏ菇���ӂ�Ŗ@�荇�������ݗ������̂��A���p�s���A���ɏ��⒬�̏ꍇ�ɂ͑�فE�c��E����Ƃ̍������ɂ��Q�����Ă���킯�ł�����A���̔��f���c��c�ōs���̂��A��������f�ōs���̂��Z�����[�ōs���̂����Ɉ�ʎs���Ƃ��Ă͊S�̂��邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂼ�ꗧ�ꂩ��s������ƒ������炻�̕ӂ̍���̍����Ɍ����ẮA�^�C���X�P�W���[�����m�点�肦��K���ł��B �i���������ǒ��j���@�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɂ́A�������c��̎Q���s�����̎��@�苦�Ɉڍs����A�ڍs���Ȃ��Ƃ������Ƃ�\�����邩�A���邢�͂��ꂪ�͂����肵�Ȃ��ꍇ�͂悭���̎s�����Ɍ����܂��Z�����[�Ƃ������Z�������ł����A����2�̕��@����߂�ꂽ�Ȃ��ł͂���܂��B�����A��̓I�ɂǂ����邩�Ƃ����͎̂A���̍������c��ɎQ������s��������̓I�ɂǂ�������ł�邩�Ƃ������Ƃ����߂邱�ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B �i�p�ψ��j����ł́A�s������ƒ�������ɂ͂��ꂼ��̌��i�K�ŁA���b���ł���͈͂Ō��\�ł�����A�ǂ����������Ŗ@�荇�����ɐi�ޕ��@���l���Ă��������邩�A���ꂼ�ꂨ�������肦�܂��ł��傤���B �i������j���Ƃ��ẮA���l�������ł����Ƃ��Ă��邢�͋c��̑��ӂƂ��ď���Ƃ̑Γ������Ƃ������Ƃ�\�����ꂵ�Ă���i�K�ł���܂��āA����̔C�Ӎ������c��I�������c��Ɏ����Ė@�苦�Ɉڍs����悤�Ȍ`�Ŏ����Ă��������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂��B�����A����͑��肪���邱�Ƃł������܂��̂ŁA���̕ӂ͐T�d�Ɍ��ɂ߂Ȃ��炱����̂ق��ł����A���ǂ��͈ڍs���܂��Ƃ����ӂ��Ȍ`�ɂ͍s����Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��ȂƁA��͂�s�����A�u�����A�l�����Ȃǂ��\���ɎQ�ނ��Ȃ���ڍs���čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝ��͎v���Ă���܂�����ǁB �i����ψ��j�����̊�����17�N��3���Ƃ������ƂŁA�ڕW�����܂��Ă��܂��̂ŁA���ꂩ��t�Z���Ă��̃^�C�~���O�ɖ@�苦�c��Ɉڂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�@�苦�c���A�܂�������x���낢��Ȏ葱���A�菇������܂��̂ŁA�^�C�~���O�I�ɂ͖@�苦�c���t�Z���ă^�C�~���O�̂��������ɔC������@�苦�c��Ɉڂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�ǂ��������f�Ō��߂�̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂����A������̔��f�����邵�A�������c��ł����k���܂����A7,000�����̕��X�Ɠ����ڐ��ŋc�_���Ă���Ŗ@�苦�Ɉڍs����̂��Ƃ������Ƃ����߂Ă܂��肽���Ǝ��͎v���Ă���܂��B �i�p�ψ��j���i�K�ł́A���ꂵ�������Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁB�͂��B�킩��܂����B �i������j���ɂ������܂��B �i���������ǒ��j�ψ��̊F�l�ɂ͑�ς��Z�����Ƃ��낲�o�Ȃ��������A�����Ȃ��ӌ�������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂����B����������܂��đ�5�Â̒n��C�Ӎ������c������Ă��������܂��B |








