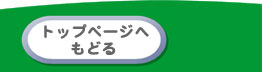|
�T�@���p�n��̊T��
�P�@�ʒu�Ǝ��R�I����
�i�P�j�ʒu�ƒn��
���p�n��́A�k���k3���i�H�c�A�X�A���j�̂قڒ����A�H�c���̖k�����̎��p�~�n�Ɉʒu���Ă��܂��B
��[�ɔ������A�k�[�ɏ\�a�c���T���A�\�a�c���������������ɑ�\�����Y��Ȏ��R���ƖL�x�ȉ���Q�Ɍb�܂ꂽ�n��ŁA���̎��R�̖L�����́u�_�R���߂��炷���p�v�Ɖr�ΐ��̎��ɏے�����Ă��܂��B
�ʐς�885.34�q�Q�ŁA����27�q�A��k61�q�̍L����������Ă��܂��B
�܂��A���̒n��́A���p�~�n�̒��������ї�����đ���{���Ƃ��āA�����A�哒��A�F���Ȃǂ̉͐삪����A�݂͊��n�Ɏs�X�n���J���A���R�n�⒆�R�Ԓn�тɂ͑召�̏W�����_�݂��Ă���A���̎���ɂ͍L��ȎR�n���ʒu���A���R���̏��Ȃ��n���ɂȂ��Ă��܂��B
�i�Q�j�C��
���p�n��́A�������Ɉʒu���Ă��邽�߁A�N�Ԃ�ʂ��Ē���Ԃ̋C���̍����傫���A�T�^�I�Ȗ~�n�^�C��������Ă��܂��B
�ߔN�ɂ�����N�ԕ��ϋC����10���O��A�~���ʂ͔N��1,500�o���x�ł���A�ϐ�͕��n�Ŗ�80�p�A�ϐ���Ԃ�12������3���܂łł��B
�i�R�j�ʐςƓy�n���p
���p�n��̑��ʐς�885.34k�u�ƂȂ��Ă��܂��B
�����n�ڕʂł݂�ƁA�G��n�E���̑���591.37k�u�i66.8���j�ƍł������A�����Ō��삪127.15���u�i14.4���j�A�R��73.53���u�i8.3���j�ƂȂ��Ă���A���R�L���Ȓn��ł��B
�\�@�@�n�ڕʓy�n���p�ʐρ@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�i�P�ʁF�q�Q�A���j
| ��@�� |
���ʐ� |
�c
�� |
��n |
�r�� |
�R�� |
���� |
�G��n |
���̑� |
| ���p�s |
707.34
�i100.0�j |
39.43
�i5.57�j |
32.39
�i4.57�j |
10.07
�i1.42�j |
0.12
�i0.02�j |
61.09
�i8.63�j |
97.95
�i13.84�j |
466.29
�i65.92�j |
| ���⒬ |
178.00
�i100.0) |
5.63
�i3.16�j |
2.91
�i1.64�j |
2.71
�i1.52�j |
0.03
�i0.02�j |
12.44
�i6.99�j |
29.20
�i16.40�j |
125.08
�i70.27�j |
| ���@�v |
885.34
�i100.0�j |
45.06
�i5.09�j |
35.30
�i3.99�j |
12.78
�i1.44�j |
0.15
�i0.02�j |
73.53
�i8.31�j |
127.15
�i14.36�j |
591.37
�i66.80�j |
�i���j�\�a�c�̖ʐς��܂݂܂���B�u���̑��v�Ƃ͍��L�тȂǂł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F����12�N�x�y�n�Ɋւ���T�v����
|
| |
�Q�@���v�i���W�o�߁j
���p�n��́A�Â������ꎟ�Y�Ƃ̔_�ыƂƑ�Y�Ƃ̍z�Ƃ𒆐S�ɔ��W���Ă��܂����B
�Ȃ��ł��]�ˎ���̌c�����犰���N�Ԃɂ����čŐ������}����������z�R�́A����ȑO�̉��B�������O��̉h�ɂ��W���������Ɠ`�����A�����̌o�ϊ����ɑ傫�ȉe����^�����Ƃ���Ă��܂��B
���̒n��́A�����ېV�O�A�암�˂ɑ����Ă������߁A�Â������茧�̐����n���A�X���̔��˒n���Ƃ̌𗬂�����ŁA�z�R�̔ɉh����ՂƂ������L�̕������`�����Ă��܂����B�ېV��A�������A��ˌ��A�O�ˌ��A�]�h���Ȃǂ̕ϑJ���o�āA����4�N�ɏH�c���ɕғ�����Ă��܂��B
���̌�A����22�N�̎s���������ɂ���āA��������������Ă������X��2��8���ƂȂ�A����ɒ����{�s�⏺�a�̒��������ɂ���āA���p�S�͉ԗ֒��A�\�a�c���A���⒬�A�����A����������4��1���ƂȂ�܂����B�����āA���a47�N�ɏ��⒬������3��1���̍����ɂ���Ď��p�s���������A1�s1���ƂȂ茻�݂Ɏ����Ă��܂��B
���̊ԁA�S���́A����42�N�ɏ���`��يԁi����S���F���݂͉ݕ��̂݁j���A�吳12�N�ɑ�ف`�ԗ֊Ԃ��A���a6�N�ɂ͍D���`�ԗ֊Ԃ��J�ʂ��A�ȍ~������z�R�A����z�R�Ȃǂ̍z�R�i�C�ɂ���Ď��p�n��̌o�ςƕ����̈����ݏo���܂����B
�������Ȃ���A�����ԁA�n��̊�Y�ƂƂ��Ēn��o�ς��x���Ă����z�Ƃ��}���ȉ~����z�̌͊����̉e�����珺�a50�N���葊�����ŕR�A�k������ȂǁA�{�n��̌o�ςɑ傫�ȑŌ���^���A�l���̗��o�������炵�܂����B
���̂悤�Ȍ������n���̂Ȃ��ŁA������z�R�́A�B���Ւn���}�C�������h������Ƃ��ĊJ����������A���j�E�����̋��_�Ƃ��đh��A�����̊ό��q�����j��}�������߂ĖK��Ă��܂��B
�܂��A�z�R����̉h�����Ɏc�����l�b�T���X���̏���z�R��������N�y�ق������ۑS����A�ŋ߂ł͑S���ŋ�������c�␢�E�z�R�T�~�b�g�Ȃǂ��J�Â���āA�n������S���I�A���ۓI�Ȍ|�p�E�����̌𗬂̏�ɐ��܂�ς���Ă��܂��B
�ȏ�ɂ݂�悤�ɁA���̎��p�n��́A�傫�ȕϓ������o�č����Ɏ����Ă��܂����A�������_�@�ɁA�b�܂ꂽ���R���ƌ�ʏ������͂��߁A�n����L�̌|�p�E�����A�Â�����|���Ă����z�ƋZ�p�Ȃǂ��܂��Â���Ɋ������A���̂���s�s�Ƃ��Ă���ɔ��W���Ă������Ƃ����҂���Ă��܂��B
|
|
| |
�R�@����I�Ȑ����s�����ƈړ���
�i�P�j�ʋΌ�
���p�n��̒ʋΌ��i15�Έȏ�A�Ǝ҂̒ʋΐ�j���݂�ƁA�啔�������s���Ɉˑ����Ă��܂����A���ӎs�����Ƃ̊W�ł͎��p�s�����⒬�i4.9���j�Ɉˑ����A���⒬�͎��p�s�i15.5���j�Ɉˑ����Ă�����Ԃ��݂��܂�
|
|
�\�@�@�ʋΐ�i15�Έȏ�A�ƎҁA���5�ʂ܂Łj �@�@�@�@�i�P�ʁF�l�A���j
��@�� |
���p�s |
���⒬ |
��P�� |
���s |
17,600
�i89.5�j |
���� |
2,467
�i75.2�j |
��Q�� |
���⒬ |
954
�i4.9�j |
���p�s |
507
�i15.5�j |
��R�� |
��َs |
539
�i2.7�j |
��َs |
173
�i5.3�j |
��S��
|
�c��� |
101
�i0.5�j |
���̑�
|
1
�i-�j |
��T�� |
����� |
54
�i0.3�j |
�\ |
�i-�j |
�ʋΎҍ��v |
- |
19,663
�i100.0�j |
- |
3,279
�i100.0�j |
�����F����12�N��������
|
| |
�i�Q�j�ʊw��
���p�n��̒ʊw���i�S�Ă̒ʊw�҂̒ʊw��j���݂�ƁA���s���Ƃ��ɁA���s���ւ̈ˑ��x������r�I�������ʂɂȂ��Ă��܂����A���ӎs�����Ƃ̊W�ł͎��p�s����َs�i4.5���j�A���⒬�i3.6���j�ȂǂɈˑ����A���⒬�͎��p�s�i10.5���j�A��َs�i4.3���j�ȂǂɈˑ����Ă�����Ԃ��݂��܂��B |
�\�@�@�ʊw��i15�Ζ����̒ʊw�҂��܂ށA���5�ʂ܂Łj �i�P�ʁF�l�A���j
��@�� |
���p�s |
���⒬ |
��P�� |
���s |
4,507
�i91.0�j |
���� |
658
�i83.9�j |
��Q�� |
���⒬ |
223
�i4.5�j |
���p�s |
82
�i10.5�j |
��R�� |
��َs |
180
�i3.6�j |
��َs |
34
�i4.3�j |
��S��
|
�鑃�� |
7
�i0.1�j |
���̑�
|
1
�i0.1�j |
��T�� |
�H�c�s�E
�\��s |
�e2
�i - �j |
�\ |
�i-�j |
�ʋΎҍ��v |
- |
4,953
�i100.0�j |
- |
784
�i100.0�j |
�����F����12�N��������
|
�i�R�j����
����I�Ȕ�������Ŋ�i�i���N�H���i�A���̑��̐H���i�A���p�G�ݕi�A����������ށj�Ɣ���i�i�O�L�̍Ŋ�i�������d�C���A�Ƌ弄C���e���A�A�Q��A�����ߗ��Ȃǁj�ɕ����Ă݂�ƁA���p�s�ł͂������7���ȏオ���s�Ɉˑ����Ă��܂����A���⒬�ł͂���������ӂ̓s�s�ɑ啔�����ˑ����Ă�����Ԃ��݂��܂��B
�Ȃ��ł����⒬�̔���i�́A���ӓs�s�ւ̈ˑ��x������r�I�����A��َs�i56.6���j�Ǝ��p�s�i18.8���j��8�����x�ˑ����Ă��܂��B
�܂��A���⒬�́A�Ŋ�i�ɂ��Ă��A3���ȏオ���p�s�Ɉˑ����A�����ւ̈ˑ����Ƃقړ����x�̔䗦�ɂȂ��Ă��܂��B
|
| |
�\�@�@������i�Ŋ�i�E����i�ʁA���5�ʂ܂Łj�@�@ �@�@�@�i�P�ʁF���j
|
��@�� |
���p�s |
���⒬ |
|
�Ŋ�i |
����i |
�Ŋ�i |
����i |
| ��P�� |
���s |
88.7 |
���s |
70.4 |
���� |
33.5 |
��َs |
56.6 |
| ��Q�� |
��َs |
7.6 |
��َs |
18.7 |
���p�s |
33.3 |
���p�s |
18.8 |
| ��R�� |
�O�O�s |
2.3 |
�O�O�s |
6.2 |
��َs |
26.1 |
���� |
11.7 |
| ��S�� |
�����s |
0.3 |
�����s |
1.4 |
�O�O�s |
2.7 |
�O�O�s |
8.0 |
| ��T�� |
�H�c�s |
0.1 |
�H�c�s |
0.4 |
�����s |
0.0 |
�����s |
0.2 |
�����F����13�N�x����w������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����w�������������Ɖ^�c���c��j
|
| |
�i�S�j�ړ���
���p�n��̈ړ����i�]���҂̌��̋��Z�n�Ɠ]�o�҂̈ڏZ�n�j���݂�ƁA���p�s�ł́A�]���E�]�o�̂�������H�c�s�A��َs�A���⒬�A�\��s�̏��ő����A���⒬��2�E3�ʂ��߂Ă��܂��B
�܂��A���⒬�́A�]����A�]�o��̂���������p�s��2���ȏ���߂čł������A��َs�ƏH�c�s��2�ʂ�3�ʂ��߂Ă��܂��B
|
| |
�\�@�@�]���E�]�o��i���5�ʂ܂Łj�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �i�P�ʁF�l�A���j
| ��@�� |
���p�s |
���⒬ |
| �]���� |
�]�o�� |
�]���� |
�]�o�� |
| ��P�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ��Q�� |
���⒬
��َs |
60�i7.1�j
60�i7.1�j |
��َs |
91�i8.3�j |
��َs
�H�c�s |
18�i8.1�j
18�i8.1�j |
��َs |
19�i9.1�j |
| ��R�� |
���⒬ |
54�i4.9�j |
�H�c�s |
18�i8.6�j |
| ��S�� |
�\��s
����s |
25�i2.9�j
25�i2.9�j |
�\��s |
20�i1.8�j |
�ѓc�쒬 |
3�i1.4�j |
��쒬 |
4�i1.9�j |
| ��T�� |
����s |
17�i1.5�j |
�鑃��
�c�㒬
�{���s |
2�i0.9�j
2�i0.9�j
2�i0.9�j |
����� |
3�i1.4�j |
| ���@�v |
|
849
�i100.0�j |
|
1,100
�i100.0�j |
|
221
�i100.0�j |
|
209
�i100.0�j |
(��)1.�u�]����v�́A�]���҂̌��̋��Z�n���Ӗ����Ă��܂��B
(��)2.�͏o������Ƃ��Ă��邽�߁A�s���Ԃœ]���E�]�o�̐l�����Ⴄ�ꍇ������܂��B
�����F����14�N�x�Z����{�䒠
|
| |
�S�@�Љ�I�o�ϓI�T��
�i�P�j�l���E����
�@�@�l���@�@�@
���p�n��̐l���́A�z�Ƃ�����ł��������a30�N��77,010�l���s�[�N�ɁA���̌㌸���������A����12�N�ɂ�46,315�l�ƂȂ�A���̊ԁA����30,695�l�̑啝�Ȍ����ɂȂ��Ă��܂��B
�܂��A�N��3�敪�l���ł݂�ƁA����2�N���畽��12�N��10�N�ԂɔN���l���i0�`14�j�̊����́A17.5������13.4���Ɍ������A�t�ɍ���l���i65�Έȏ�j�̊�����18.5������27.1���ɑ������Ă���A���q����̐i�s���@���Ɍ���Ă��܂��B
����A���̏Ő��ڂ���ƁA�V�s�ɂ����Ă��l���̌����A���q����͔������Ȃ����Ƃ��\�z����܂��B
|
| |
�\�@�@�l���̐��ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁF�l�A���j
| �敪 |
���a55�N |
60 |
�����Q�N |
�V |
12 |
| ���p�s |
|
45,615 |
44,499 |
42,407
(42,443) |
41,184 |
39,117
(39,144) |
| �N���l��
�i0�`14�j |
9,710
�i21.3�j |
9,175
�i20.6�j |
7,700
�i18.2�j |
6,453
�i15.7�j |
5,366
�i13.7�j |
| ���Y�N��l��
�i15�`64�j |
30,533
�i66.9�j |
28,925
�i65.0�j |
27,060
�i63.8�j |
25,546
�i62.0�j |
23,299
�i59.6�j |
| ����l��
�i65�Έȏ�j |
5,372
�i11.8�j |
6,399
�i14.4�j |
7,647
�i18.0�j |
9,185
�i22.3�j |
10,452
�i26.7�j |
| �N��s�� |
0 |
0 |
(36) |
0 |
(27) |
| ���⒬ |
���l��
(�N��s�ڊ܂�) |
10,526 |
9,728 |
8,035 |
7,703 |
7,168
(7,171) |
| �N���l��
�i0�`14�j |
2,087
�i19.8�j |
1,601
�i16.4�j |
1,151
�i14.3�j |
1,014
�i13.2�j |
862
�i12.0�j |
| ���Y�N��l��
�i15�`64�j |
7,159
�i68.0�j |
6,698
�i68.9�j |
5,230
�i65.1�j |
4,814
�i62.5�j |
4,226
�i59.0�j |
| ����l��
�i65�Έȏ�j |
1,280
�i12.2�j |
1,429
�i14.7�j |
1,654
�i20.6�j |
1,875
�i24.3�j |
2,080
�i29.0�j |
| �N��s�� |
0 |
0 |
0 |
0 |
(3) |
| ���v |
���l��
(�N��s�ڊ܂�) |
56,141 |
54,227 |
50,442
(50,478) |
48,887 |
46,285
(46,315) |
| �N���l��
�i0�`14�j |
11,797
�i21.0�j |
10,776
�i19.9�j |
8,851
�i17.5�j |
7,467
�i15.3�j |
6,228
�i13.4�j |
| ���Y�N��l��
�i15�`64�j |
37,692
�i67.1�j |
35,623
�i65.7�j |
32,290
�i64.0�j |
30,360
�i62.1�j |
27,525
�i59.5�j |
| ����l��
�i65�Έȏ�j |
6,652
�i11.9�j |
7,828
�i14.4�j |
9,301
�i18.5�j |
11,060
�i22.6�j |
12,532
�i27.1�j |
| �N��s�� |
0 |
0 |
(36) |
0 |
(27) |
�����F���������i�e�N10���P���j
|
| |
�A�@����
���p�n��̐��ѐ��́A����2�N�܂Ŋɂ₩�Ȍ����X���ɂ���܂������A���̌�͔����X���������A����12�N�ɂ�14,886���тƂȂ��Ă��܂��B
���̈���ŁA�ꐢ�ѓ�����̐l���͌������A����12�N�̐��ыK�͂�3.11�l�ƂȂ�A�j�Ƒ������i�s���Ă�����Ԃ��݂��܂��B
|
| |
�\�@�@���т̐��ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁF���сA�l�j
| ��@�@�� |
���a55�N |
60 |
�����Q�N |
�V |
12 |
| ���p�s |
|
12,125 |
11,999 |
12,076 |
12,245 |
12,315 |
| ���ыK�� |
3.76 |
3.71 |
3.51 |
3.36 |
3.18 |
| ���⒬ |
������ |
3,111 |
3,178 |
2,647 |
2,638 |
2,571 |
| ���ыK�� |
3.38 |
3.06 |
3.04 |
2.92 |
2.79 |
| ���@�v |
������ |
15,236 |
15,177 |
14,723 |
14,883 |
14,886 |
| ���ыK�� |
3.68 |
3.57 |
3.43 |
3.28 |
3.11 |
�����F���������i�e�N10��1���j
|
| |
�i�Q�j�Y�ƕʏA�Ɛl��
���p�n��̎Y�ƕʏA�Ɛl���́A���̎l�����I�̊Ԃɑ�ꎟ�Y�Ƃ̌������������A��ꎟ�Y�Ƃ����Y�ƁA��O���Y�ƂւƃV�t�g���܂����B
���āA�{�n��́A�z�R�̔ɉh��w�i�ɁA�_�ыƂ�����Ȓn��ŁA���𒆐S�Ƃ����{�Y��ʎ��A��Ȃǂ̕����o�c����������s���A�܂��L��ȎR�ԁE���R�Ԓn�тɂ����ẮA�ыƂ�����ɉc�܂�Ă��܂����B
�������Ȃ���A���{�S�y�ɂ�����Y�ƍ\���̕ω����{�n��ł����l�ɐ����A����12�N�̑�ꎟ�Y�ƏA�Ɛl����3,510�l�i�S�Y�Ƃ�15.3���j�Ƃ���Ɍ������Ă��܂��B
�܂��A��Y�Ƃ́A���a50�`60��ɂ����đ������ōz�R���R�A�k���������̂́A�d�C�@�B�𒆐S�Ƃ�����ƗU�v�ɂ���ĕ���12�N�̏A�Ɛl����7,605�l�i��33.2���j���ێ����Ă��܂��B
����A��O���Y�Ƃ́A���R���������������ό��T�[�r�X�Ƃ̑����Ȃǂɂ���ĕ���12�N�̏A�Ɛl����11,820�l�i��51.5���j�Ƒ����X���������Ă��܂��B
���̎Y�ƕʏA�Ɛl���̍\�������S�́i��ꎟ�Y��11.0���A��Y��30.9���A��O���Y��58.1���A�j�Ɣ�r���Ă݂܂��ƁA��ꎟ�Y�ƂƑ�Y�Ƃ͌���荂���A��O���Y�Ƃ͌������Ⴂ�l�ɂȂ��Ă��܂��B
|
�\�@�@�Y�ƕʏA�Ɛl���̐��ځ@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�i�P�ʁF�l�A���j
| �敪 |
���a55�N |
60 |
�����Q�N |
�V |
12 |
| ���p�s |
|
6,269
(26.9) |
5,790
(26.1) |
4,701
(21.6) |
3,582
(17.2) |
3,160
(16.1) |
| �Y�� |
6,862
(29.4) |
6,272
(28.3) |
7,048
(32.4) |
6,977
(33.4) |
6,280
(31.9) |
| �O���Y�� |
10,190
(43.7) |
10,093
(45.5) |
9,967
(45.9) |
10,322
(49.4) |
10,217
(52.0) |
| ���ޕs�\ |
13
(0.1) |
13
(0.1) |
8
(0.1) |
2
(0.0) |
6
(0.0) |
| �v |
23,334
(100.0) |
22,168
(100.0) |
21,724
(100.0) |
20,883
(100.0) |
19,663
(100.0) |
| �A�Ɨ� |
51.2 |
49.8 |
51.2 |
50.7 |
50.2 |
| ���⒬ |
|
621
(12.7) |
620
(13.4) |
479
(13.0) |
368
(10.5) |
350
(10.7) |
| �Y�� |
2,430
(49.5) |
2,312
(50.2) |
1,653
(45.0) |
1,458
(41.3) |
1,325
(40.4) |
| �O���Y�� |
1,858
(37.8) |
1,669
(36.3) |
1,545
(42.0) |
1,702
(48.2) |
1,603
(48.9) |
| ���ޕs�\ |
0
(0.0) |
3
(0.1) |
0
(0.0) |
0
(0.0) |
1
(0.0) |
| �v |
4,909
(100.0) |
4,604
(100.0) |
3,677
(100.0) |
3,528
(100.0) |
3,279
(100.0) |
| �A�Ɨ� |
46.6 |
47.3 |
45.8 |
45.8 |
45.7 |
| ���v |
|
6,890
(24.4) |
6,410
(23.9) |
5,180
(20.4) |
3,950
(16.2) |
3,510
(15.3) |
| �Y�� |
9,292
(32.9) |
8,584
(32.1) |
8,701
(34.3) |
8,435
(34.6) |
7,605
(33.2) |
| �O���Y�� |
12,048
(42.7) |
11,762
(43.9) |
11,512
(45.3) |
12,024
(49.2) |
11,820
(51.5) |
| ���ޕs�\ |
13
(0.0) |
16
(0.1) |
8
(0.0) |
2
(0.0) |
7
(0.0) |
| �v |
28,243
(100.0) |
26,772
(100.0) |
25,401
(100.0) |
24,411
(100.0) |
22,942
(100.0) |
| �A�Ɨ� |
50.3 |
49.4 |
50.3 |
49.9 |
49.5 |
�����F���������i�e�N10��1���j
|
| |
�i�R�j�Y�ƕʏ����Y�z
�Y�ƕʏ����Y�z�Ƃ́A�n����Ő��Y���������Ă����Ƃ�_�ƂȂǂ��V���ɐ��ݏo�������Y�z�i�t�����l�z�j���璆�ԓ����z�i���I�o��A�������p��Ȃǁj�����������̂ł���A�e�Y�Ƃ̒n��o�ςւ̊�^�������w�W�ł��B
���̎w�W�����ƂɁA�{�n��̎Y�ƕʏ����Y�z�̐��ڂ��݂�ƁA��ꎟ�Y�ƂƑ�Y�Ƃ������X���������A��O���Y�Ƃ������X���������Ă��܂��B
�Ȃ��ł���O���Y�Ƃ̐�߂銄���������A�S�̂�7�����x�A�����đ�Y�Ƃ����悻2���ƂȂ�A��ꎟ�Y�Ƃ��S�̂�6����1���ɂ������Ȃ��ƂȂ��Ă��܂��B
|
| |
�\�@�@�Y�ƕʎs���������Y�z�̐��ځ@�@�@ �@�@�@ �@�@�i�P�ʁF�S���~�A���j
| �敪 |
�����W�N |
�X |
10 |
11 |
12 |
| ���p�s |
|
7,052
(7.6) |
6,124
(6.9) |
5,912
(6.8) |
5,585
(6.7) |
4,804
(5.9) |
| �Y�� |
27,236
(29.5) |
24,945
(28.3) |
24,997
(28.6) |
22,542
(27.3) |
20,731
(25.3) |
| �O���Y�� |
58,217
(62.9) |
57,170
(64.8) |
56,465
(64.6) |
54,504
(66.0) |
56,237
(68.8) |
| �v |
92,505
(100.0) |
88,239
(100.0) |
87,374
(100.0) |
82,631
(100.0) |
81,772
(100.0) |
| ���⒬ |
|
823
(4.5) |
1,056
(5.8) |
1,131
(6.3) |
1,019
(5.6) |
1,095
(6.0) |
| �Y�� |
6,816
(36.9) |
4,577
(25.3) |
4,969
(27.8) |
5,403
(29.4) |
2,643
(14.4) |
| �O���Y�� |
10,802
(58.6) |
12,499
(68.9) |
11,779
(65.9) |
11,949
(65.0) |
14,549
(79.6) |
| �v |
18,441
(100.0) |
18,132
(100.0) |
17,879
(100.0) |
18,371
(100.0) |
18,287
(100.0) |
| ���v |
|
7,875
(7.1) |
7,180
(6.7) |
7,043
(6.7) |
6,604
(6.5) |
5,899
(5.9) |
| �Y�� |
34,052
(30.7) |
29,522
(27.8) |
29,966
(28.5) |
27,945
(27.7) |
23,374
(23.4) |
| �O���Y�� |
69,019
(62.2) |
69,669
(65.5) |
68,244
(64.8) |
66,453
(65.8) |
70,786
(70.7) |
| �v |
110,946
(100.0) |
106,371
(100.0) |
105,253
(100.0) |
101,002
(100.0) |
100,059
(100.0) |
�����F�H�c�������o�όv�Z�N��
|
| |
�i�S�j�s�������z����
�s�������z�����Ƃ́A�n��o�ς̏z�z�ʂ���݂����̂ł���A�y�n�E�J���́E���{�Ȃǂ̐��Y�v�f������s�����ɁA���̑Ή��Ƃ��Č`�������n��E�����E��Ɨ����Ȃǂ̏������ǂ̒��x���z���ꂽ���������w�W�ł��B
���̎w�W�ɂ��ƁA���p�n��̎s�������z�����́A����11�N�x�܂Ŕ����X�������ǂ��Ă��܂������A����12�N�x�ɂȂ��đ������A1,037���~�ƂȂ��Ă��܂��B
�܂��A��l������̎s�������z�����ɂ��Ă݂�ƁA����12�N�x�ł͕��ς�2,177��~�ƂȂ��Ă���A���̊z�́A���̕��ϊz2,448��~��9������x�ɂƂǂ܂��Ă��܂��B
|
| |
�\�@�@�s�������z�����̐��ځ@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�ʁF�S���~�A��~�A�l�j
| �敪 |
�����W�N�x |
�X |
10 |
11 |
12 |
| ���p�s |
|
93,380 |
90,797 |
88,443 |
84,263 |
83,704 |
| �s����l�����蕪�z�����i��~�j |
2,232 |
2,196 |
2,160 |
2,074 |
2,076 |
| �l��(�Z����{�䒠�j |
41,836 |
41,347 |
40,950 |
40,622 |
40,325 |
| ���⒬ |
|
16,536 |
17,988 |
16,913 |
17,271 |
19,956 |
| ������l�����蕪�z�����i��~�j |
2,139 |
2,357 |
2,250 |
2,330 |
2,740 |
| �l��(�Z����{�䒠�j |
7,729 |
7,632 |
7,517 |
7,413 |
7,284 |
| ���@�v |
|
109,916 |
108,785 |
105,356 |
101,534 |
103,660 |
| �s������l�����蕪�z�����i��~�j |
2,218 |
2,221 |
2,174 |
2,114 |
2,177 |
| �l��(�Z����{�䒠�j |
49,565 |
48,979 |
48,467 |
48,035 |
47,609 |
| �y�Q�l�z
�H�c�� |
�s���������z�����i�S���~�j |
3,094,928 |
3,077,763 |
2,982,426 |
2,952,326 |
2,911,319 |
| �s��������l�����蕪�z�����i��~�j |
2,558 |
2,553 |
2,483 |
2,468 |
2,448 |
| �l��(�Z����{�䒠�j |
1,209,970 |
1,205,552 |
1,201,072 |
1,196,166 |
1,189,279 |
�����F�H�c���s�������������v�i���v�j�N��
|
| |
�i�T�j����
���p�n��̌��Z�z�̐��ڂ��݂�ƁA��ʍ����ő傫�Ȋ������߂Ă���n����t�ł́A����13�N�x�Ɏ��p�s��42.2���A���⒬��43.9���Ƃ������4���ȏ���߁A�ˑR�Ƃ��č����ˑ��x�������Ă��܂��B
����A��������̎�̂��Ȃ��ׂ��s���ł́A����13�N�x�Ŏ��p�s��18.4���A���⒬��15.6���ƁA������u3�������v�ɂ������Ȃ��ɂ߂ĒႢ�ɂ���܂��B
�܂��A�Z����l������̍Ώo�z�́A����13�N�x�Ŏ��p�s��76.9���~�ɑ��A���⒬��105.7���~�Ƒ傫���A�P�s�P�����v��81.3���~�ɂȂ��Ă��܂��B
���̂悤�ȍ����̂Ȃ��ŁA�n����������芪����͈�w�������𑝂��Ă��Ă���A�s�����v��j�Ɋ�Â������̌������ƌo��̐ߌ���������ϋɓI�ɐi�߂Ă����K�v������܂��B
|
| |
�\�@�@���Z�z�̐��ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �i�P�ʁF��~�A���j
| �敪 |
�����X�N�x |
10 |
11 |
12 |
13 |
| ���p�s |
|
|
|
|
31,558,561 |
30,691,449 |
32,021,384 |
| |
18,663,776 |
18,060,583 |
19,895,296 |
17,572,695 |
18,725,749 |
|
|
|
|
3,528,470
�i19.5�j |
3,521,819
�i17.7�j |
3,418,239
�i19.5�j |
3,445,679
�i18.4�j |
| |
|
7,836,996
�i43.4�j |
8,286,313
�i41.6�j |
8,304,956
�i47.3�j |
7,903,868
�i42.2�j |
| |
10,467,023 |
10,822,318 |
11,663,265 |
13,118,754 |
13,295,635 |
| |
|
28,569,657 |
28,047,750 |
30,702,079 |
29,617,382 |
30,700,333 |
| |
18,427,191 |
17,612,090 |
19,323,837 |
17,021,550 |
17,932,924 |
| |
10,142,466 |
10,435,660 |
11,378,242 |
12,595,832 |
12,767,409 |
| |
691.0
�i41,347�j |
684.9
�i40,950�j |
755.8
�i40,622�j |
734.5
�i40,325�j |
769.0
�i39,922�j |
| ���⒬ |
|
|
|
|
8,327,715 |
8,463,539 |
7,861,221 |
| |
5,732,302 |
6,190,624 |
5,468,643 |
5,190,188 |
4,680,805 |
|
|
|
|
667,231
�i10.8�j |
675,515
�i12.4�j |
667,811
�i12.9�j |
728,385
�i15.6�j |
| |
|
2,224,987
�i35.9�j |
2,251,539
�i41.2�j |
2,242,870
�i43.2�j |
2,056,005
�i43.9�j |
| |
2,937,104 |
3,008,227 |
2,859,072 |
3,373,351 |
3,180,416 |
| |
|
8,411,058 |
8,962,418 |
8,077,965 |
8,177,098 |
7,599,426 |
| |
5,608,208 |
6,093,367 |
5,368,691 |
5,067,179 |
4,570,731 |
| |
2,802,850 |
2,869,051 |
2,709,274 |
3,109,919 |
3,028,695 |
| |
1,102.1
�i7,632�j |
1,192.3
�i7,517�j |
1,089.7
�i7,413�j |
1,122.6
�i7,284�j |
1,056.5
�i7,193�j |
| ���v |
|
|
|
38,081752 |
39,886,276 |
39,154,988 |
39,882,605 |
| |
24,396,078 |
24,251,207 |
25,363,939 |
22,762,883 |
23,406,554 |
|
|
|
|
4,195,701
�i17.3�j |
4,197,334
�i16.5�j |
4,086,050
�i18.0�j |
4,174,064
�i17.8�j |
| |
|
10,061,983
�i41.5�j |
10,537,852
�i41.5�j |
10,547,826
�i46.3�j |
9,959,873
�i42.6�j |
| |
13,454,127 |
13,830,545 |
14,522,337 |
16,492,105 |
16,476,051 |
| |
|
36,980,715 |
37,010,168 |
38,780,044 |
37,794,480 |
38,299,759 |
| |
24,035,399 |
23,705,457 |
24,692,528 |
22,088,729 |
22,503,655 |
| |
12,945,316 |
13,304,711 |
14,087,516 |
15,705,751 |
15,796,104 |
| |
755.0
�i48,979�j |
763.6
�i48,467�j |
807.3
�i48,035�j |
793.9
�i47,609�j |
812.9
�i47,115�j |
�����F���p�s�y�я��⒬���Z����
|
| |
�T�@��ʖ�
���p�n��̊������H�Ԃ́A���k�����ԓ��i���p�������h.�b�A�\�a�c�h�D�b�A����h�D�b�j����Ƃ��āA����5�H���ƌ���8�H�����c���Ɖ������`�����Ă���A���̂�����v��3�H���i���k�����ԓ��A����282�����A������ُ\�a�c�ΐ��i�ʏ́F���C���C���j�j�����p�s�Ə��⒬�Ƃ̌��т������߁A����ɂ͍O�O�s�A�X�s�A�����s�ȂǑ����̒��S�s�s�ւ̃A�N�Z�X��e�Ղɂ��Ă��܂��B�@
����A������ʋ@�ւƂ��ăo�X��^�N�V�[�A�����ēS���́AJR�ԗ����������甪�����̎R���݂��z���A���p�s�̎s�X�n��ʂ��َs�܂Œn��̑��Ƃ��āA���ꂼ��d�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B����ɖ{�n��̎��ӂɂ́A��ٔ\���`�i�H�c�k��`�j����������A������ʃl�b�g���[�N�̐����̖ʂł͌����ōł������̐������ꂽ�n��ƂȂ��Ă��܂��B
���̂悤�Ȍb�܂ꂽ������ʃl�b�g���[�N���V�s�̂܂��Â���Ɋ������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B
|
| |
|
| |
|
|