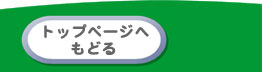| Ⅱ 鹿角地域の課題と発展の方向性 これまでの現状分析から、新市のまちづくりに向けた鹿角地域の課題と発展の方向性をまとめてみると、次のとおりです。
1 人口の動向からみた地域的課題への対応
鹿角地域は、過疎化(人口の減少)と併せて、少子高齢化と核家族化が進んでいます。
したがって、新市においては、定住のための施策や少子高齢化、核家族化に対応したきめ細かな施策が求められます。
(1)過疎化(人口の減少)への対応
鹿角地域の人口は、昭和30年の77,010人(鹿角市60,475人、小坂町16,535人)をピークにその後減少し続け、平成12年には46,315人になっています。
特に人口減少の著しい期間を市町別にみると、鹿角市は昭和35~50年(この15年間に13,131人が減少しています。)、小坂町は昭和40~平成2年(この25年間に7,245人が減少しています。)となり、この期間は地域内及び近隣の鉱山が相次いで閉山、縮小した時期と一致します。(鹿角市の尾去沢鉱山が昭和53年に閉山。小坂町の古遠部・相内・鉛山鉱山は昭和60~61年にかけて相次いで閉山、平成2年には内の岱坑が閉坑。)
したがって、本地域の人口減少は、地域経済を支えてきた鉱業の衰退に伴う、地域特有の産業構造の変化を背景としたものであったといえますが、さらに、鉱業の余剰労働力を吸収する就労の場が域内に乏しく、結果的には首都圏や近隣の地方都市に流出せざるを得なかったことも大きな原因であったと考えられます。
その後、このような急速な過疎化に歯止めをかけるため、鹿角市では、雇用の増大を図るための工業団地の造成をはじめ、マインランド尾去沢、鹿角観光ふるさと館、スキー場、キャンプ場、温水プールなどの観光拠点施設の整備、商店街近代化事業、社会資本の整備などを進めてきました。
一方、小坂町では、企業誘致をはじめ、鉱業技術を活かした資源リサイクルやゼロエミッションなどのエコタウン事業、小坂鉱山事務所や康楽館の保存整備、全国芝居小屋会議・世界鉱山サミットの開催などを進めてきています。
このような就業及び定住促進を中心とした施策によって、平成2年頃から人口減少は鈍化傾向を示してはいるものの、雇用機会の絶対的な不足や高等教育機関への進学者の増加、根強い都会指向などによって、依然として域外への人口流出が続いており、今後とも施策の効果を見極めながら就業及び定住促進のためのまちづくり施策を着実に進めていく必要があります。
(2)少子高齢化への対応
人口の推移を年齢3区分でみると、平成2年から平成12年の10年間に年少人口(0~14歳)の割合が17.5%から13.4%に減少している一方で、高齢人口(65歳以上)の割合は18.5%から27.1%へと大幅に増加し、少子高齢化の進行を示しています。
この少子化の原因としては、出産する女性(特に20~39歳代)の人口減少、子育て環境の変化、女性の就労機会の増大などによる出生率の低下が考えられます。また、高齢化が急速に進んでいる原因としては、医療技術の発達や健康づくり指向などによる長寿社会の到来、若者の流出による必然的な高齢者人口比率の増大などが考えられます。
このような少子化による急激な社会構造の変化は、人口の減少による地域活力の衰退を招き、新市の行財政能力の低下につながることが懸念されるだけではなく、新市においてまちづくりを担う人材が減少することを意味しており、本地域にとっては極めて重要な課題です。また、高齢化の進展は、保健、医療、福祉等における行財政需要のさらなる増加をもたらすものと予想されます。
今後、このような状況に対応するため、より一層の専門的な人材確保と財政的な基盤づくりが求められます。
(3)核家族化への対応
鹿角地域の世帯数は、平成2年以降微増傾向を示し、平成12年には14,886世帯となっていますが、その一方で、一世帯あたりの人員は減少傾向を示し、同年には3.11人になっています。
このような核家族化の進展は、持ち家指向の高まりと親との同居意識の低下などを背景としたものであると考えられますが、一人暮らしの高齢者や夫婦のみの高齢者が増加すること、また家族数の減少によって子育て環境が変化し、子育て支援体制が欠落して少子化に通じることが懸念されることから、特に高齢者福祉対策の充実や子育てを支援するための環境づくりが求められます。
2 停滞している産業の振興
鹿角地域の産業別就業人口は、ここ30年位の間に第一次産業の減少が著しく、また第一次産業から第二次産業、第三次産業へと就業人口はシフトしています。
また、産業別純生産額は、第三次産業が増加傾向を示している反面、第一次産業と第二次産業が減少傾向を示し、地域の中核的な産業である第一次産業は全体の1割にも満たず、第二次産業は2割程度にとどまっています。
(1)第一次産業の振興
鹿角地域は、かつて鉱山の繁栄を背景に、農林業も盛んな地域で、稲作、果樹、畜産に加え、キュウリやトマトなどの野菜、花きなどの市場性の高い作物を組み入れた複合経営が早くから行われ、また広大な山間・中山間地帯においては、林業も盛んに営まれていました。
しかしながら、平坦部の少ない地勢的な制約条件のもとで営まれてきた農業は、経営規模が零細で、生産効率や所得水準も低く、農業労働力の他産業への流出をきたし、農業従事者の離農化・兼業化、高齢化をもたらしただけではなく、農地の転用、遊休地化も進んでいます。
加えて、近年の農業をとりまく情勢は、米の生産調整や海外を含む産地間の価格競争が激化し、国民の間で食糧・農業・農村に対する新たな価値観が生まれるなど、大きな変革の時代の渦中にあり、安定した農業経営の難しさを増長させています。
このような農業経営をとりまく厳しい環境のもとで、農業に魅力をもたせ、やりがいのある職業として選択しうる環境を整えるためには、個々の農家の実態を見極め、選別して、きめ細かな施策を講じていく必要があります。
すなわち、意欲と経営感覚に富んだ経営農家(専業農家、認定農業者)については、農地の集積を進め、市場性の高い戦略作物を導入してブランド化を図るなど、経営を側面から支援しつつ、経営基盤をさらに強化していく必要があります。
また、地域のなかで大部分を占める兼業農家に対しては、農業株式会社や農業公社の設置について検討を進め、兼業農家の春・秋の農作業を受託するシステムを確立して就労機会を確保するほか、農業と関連するアグリビジネス(農業関連産業)等を進め、所得の確保に努めていく必要があります。また、林業は、かつては国有林を中心に木材供給が盛んでしたが、現在は保育・間伐を必要とする山林が多く、廉価な外材需要による国内林業の低迷を反映して、適切な間伐の実施が停滞している状況にあります。
そのため、貯木場や乾燥・加工施設を活用して地域内での木材需要を喚起するとともに、併せて体験学習の機会を通して水源かん養や大気浄化、健康増進、自然保護教育など、森林の持つ公益的機能を再認識し、森林資源の維持・保全に努める必要があります。
(2)第二次産業の振興
鹿角地域の第二次産業は、昭和50~60年代にかけて、急激な円高や鉱石の枯渇の影響を受け、相次いで鉱山が閉山、縮小し、地域経済に大きな打撃を与えました。また、今までに集積をみた製造業の海外へのシフトや景気の低迷による工場の撤退、規模の縮小、リストラなどを余儀なくされる企業もあるほか、企業誘致が地場産業の重層化、高度化に至っていないなどの地域的課題を抱えています。
このような状況のなかで、地域経済の再生を図るためには、地場企業の体質強化と人材の養成、業種間の連携による内発型産業(地域資源活用型産業)の創出が求められています。
県北地域では、県北部エコタウン計画と連動を図り、環境への負荷の少ない循環を基調とした鉱業の技術の革新と高度化が図られ、さらに(財)秋田県資源技術開発機構との連携のもとで進めてきた非鉄金属やレアメタルのリサイクル技術の研究が進み、資源リサイクル産業はポスト鉱業の新たな産業として期待されています。
雇用機会の確保については、研究開発等への助成や人材育成対策などにより地場企業の増強を図るとともに、IT(情報通信技術)、社会福祉、農業等さまざまな分野における起業(ベンチャー)を新事業開拓助成や工場設置促進助成などの支援を利用し、新しい魅力ある雇用環境の創出・整備を図っていく必要があります。
(3)第三次産業の振興
鹿角地域の第三次産業は、観光が中核的な産業になっています。
鹿角地域はこれまで自然、温泉、祭りや史跡を中心とした伝統文化等の恵まれた地域特性を活かした観光施策を展開してきました。しかしながら近年の低迷する経済情勢において、個人のレジャーに対する消費は抑えられており、観光消費額も平成14年度はやや持ち直したものの、減少傾向にあります。また観光ニーズが多様化し、観光形態も団体から個人・少人数グループ型へ変化しており、加えて高速交通網のインフラ整備により遠隔地からの誘客も可能となりましたが、通過型の観光客が増加しています。
十和田・八幡平へは年間約300万人もの観光客が訪れていますが、今後は鹿角全域への経済的な波及効果を誘導することに結びつけなければなりません。そのため、滞留型・通年型の鹿角地域の観光の確立と鹿角地域全体への経済効果の波及を目指し、十和田八幡平国立公園を中核に据えながら、新たな観光資源の掘り起こし、重要な観光資源と観光施設を融合した企画商品の開発やゾーン形成、ホスピタリティ(もてなす意識)の向上、「食」や「癒し」といった観光ニーズへの対応などを図り、鹿角地域全体を観光資源として見立てたトータル的な観光イメージを確立していく必要があります。
3 市民分配所得の向上
鹿角地域の一人当たりの市町民分配所得についてみると、平成12年度では平均で2,177千円となっていますが、この額は、県の平均額2,448千円の9割弱程度にとどまっています。この背景としては、第一次産業、なかでも農業の生産性が低位で生産農業所得が少ないことがあげられます。
そのため、農業のプロフェッショナルを育成することと併せて、農業と関連するアグリビジネスを起業化し、兼業農家の就業機会を創出するなど、農業の所得水準を向上させるための方策が求められます。
また、第二次及び第三次産業に関しても、異業種間の連携や地域資源の活用、高度な技術などによる、生産性の向上と付加価値の創出が求められていますが、まずは観光消費額の拡大と雇用の確保を図り、市民分配所得の向上を目指していく必要があります。
4 住民の広域的活動への対応
鹿角地域1市1町は、北東北3県(秋田、青森、岩手)のほぼ中央に位置し、比較的類似した自然条件のもとで、高速交通網の整備が急速に進み、住民の行動エリアは飛躍的に拡大しています。
人々の日常的な生活行動圏域や転入・転出先の現状をみると、通勤圏、通学圏、商圏、移動圏のいずれも両市町間の依存関係が比較的強く、相互に依存し合いながら一体的な生活圏を形成している実態がわかります。
また、その一方で、買物においては、弘前市、盛岡市など中核的な地方都市への依存がみられ、地域住民の行動圏域は県境を越え、拡大化しています。
このような日常的な活動圏域の広域化は、高速交通ネッワークの整備による必然的な結果であると解釈できますが、鹿角地域の文化を改めて見直し、新たな鹿角地域の文化を構築する機会でもあり、今後、立地条件を活かした文化・芸術の面での広域的な交流を目指し、まちづくりを進めていく必要があります。
5 魅力的な市街地整備と商業の活性化
既成市街地に立地している本地域の商業は、家族中心の個人商店が中心で、小規模経営が大部分を占め、県内他市町と比較しても規模の格差が大きく、極めて経営基盤が脆弱であることから、生活圏の広域化や消費者ニーズの変化の影響を受け、周辺主要都市への購買力の流出をもたらすとともに、域内に立地する大規模小売店舗やコンビニエンスストアへの依存度を高める要因となっています。
このような地元商店街の空洞化は、全国的な傾向であるとはいえ、市街地そのものの衰退を招きかねないことから、商業者などと協同でTMO(タウン・マネージメント機関)の充実を図り、地域で形成する市街地での商業集積を一体として捉え、点在する空き店舗の利用対策、商業者への適切な経営アドバイスや中小商業の高度化、イベントの開催などを一体的かつ計画的にマネージメント(管理・運営)することにより、商店街に人の流れをつくり賑わいを生み出す魅力的な市街地整備に努め、商店街の活性化を推し進めていく必要があります。
6 まちづくりへの交通網の活用と生活空間に配慮した道路整備
鹿角地域の幹線道路網は、東北自動車道を基軸として、国道5路線と県道8路線が縦軸と横軸を形成し、鹿角市と小坂町との結びつきを強め、さらには弘前、青森、盛岡など他県の中心都市へのアクセスを容易にしています。また、本地域の周辺には、大館能代空港が整備され、今後日本海沿岸東北自動車道が小坂町で接続されることもあって、高速交通ネットワークの整備の面では県内で最も条件の整った地域となります。
しかしながら十和田八幡平を観光産業の中核に据えている本地域では、年々通行量の増加が見込まれながらもアクセス道路網はまだまだ十分ではありません。
今後は、高速交通ネットワークを活かした企業誘致の推進、観光アクセスルートの充実・確保、市街地を迂回するバイパスの整備や歩道、自転車道など、生活空間に配慮した道路整備などを、新市のまちづくりに活かしていくことが求められています。さらには住民の生活の足の確保を図るために、公共交通機関の維持に努め、コミュニティバスの運行など効率的で、利便性の高い交通政策を展開していくことも必要です。
7 健やかで安心できる福祉サービスの確立
鹿角地域の老齢人口は、平均寿命の伸びとともに、出生率の低下や若年労働力の流出によって地域の人口に占める比率が一層高くなっています。高齢者の増加、介護保険制度の開始等により、高齢者の意識や価値観に変化が見られ、高齢者が社会参加しやすい環境づくりをするため、より安心で快適なサービスを提供するとともに、民間や地域活力が生かされるような高齢者福祉施策が必要です。
一方、健やかな子育て環境づくりには、保育ニーズの多様化に対応していかなければなりません。幼保一体化、乳児保育や一時保育等による一層の保育サービスの拡大、子育て支援ネットワークづくりや児童館の充実などといった子育てサポートシステム、児童健全育成活動等の整備が必要です。
みんなが健やかに安心して暮らせる幸せが、まちづくりの原点です。
8 歴史遺産・地域文化を伝承する
地域文化を伝承するためには、文化財を適切に保護・保存し、活用することが必要です。本地域には、国の特別史跡大湯環状列石、重要文化財に指定されている康楽館・小坂鉱山事務所、大日堂舞楽や毛馬内の盆踊、花輪ばやしに代表されるように、たくさんの貴重な有形・無形の歴史や文化があります。
郷土の歴史や文化を正しく理解し、後世に継承するための学習講座の開設や資料のわかりやすい公開・展示を進め、これらを正しく伝承していくことが、過疎化や生活様式の変化による後継者不足等の解消に結び付くこととなります。
9 地方分権の推進と行財政基盤の強化
今後地方分権が進められることによって、住民へのサービスの提供は市町村自らが判断し、自らの責任において決定し、変貌しつづける社会経済情勢に対応し、地域住民の福祉向上のため、様々なサービスの提供や住民ニーズの把握に努めていかなければなりません。
そのためには、住民ニーズに対応できる専門的で高度な知識を持った人材の育成を図るなど、分権時代にふさわしい体制を整えていく必要があります。
また、社会経済情勢や財政が逼迫化しているなかで、現状の行政サービスの水準を維持し、少子高齢化など、新たな行政需要に対応していくためには、徹底した行財政改革による効率化と行財政基盤の強化を図ることが求められています。
|