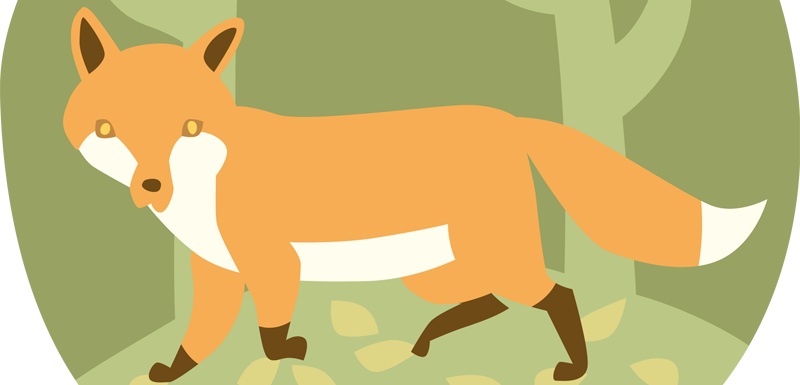 ◆◆真相究明合点コレクションの例 ◆鹿角と毛野のこと 〔鹿角=上津野〕とは、「かみつけぬ(上ツ毛野)」のことだ。 「上津野」とは「かみつけぬ(上ツ毛野)」のことであり、「かづの」と訓じたのであろう。 即ち、「上津野」とは、「米代川の川上にある毛人の国(蝦夷を首長とする国)」である、と推理することが出来る。 また、次のようにも推理出来る。つまり当時の朝廷は、北日本一帯(北関東以北)をひっくるめて、 「毛野(けの)」~「上野(かみつけの)」~「上津野(かみつの・かづの)とみなしていたかも知れない。 ◇参照 : 鹿角の歴史の謎/上津野(かみつの・かみつぬ)考 _____________________________________ 特集【鹿角の通説異説】検証① ◆◆地勢 : 鹿角盆地はAD915年、十和田湖の大噴火(十和田火砕流)により、当時の遺産遺跡は 全て消滅してしまったので、当時の歴史は「鹿角物語(民話)」によって推測するしか術はない。 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔地勢〕 __________________________________________ 特集【鹿角の通説異説】検証② ◆地勢 : ◆黒又山は有史以前の縄文期から、十和田湖噴火鎮静祈願の象徴であった。 従って「大湯環状列石」の組石は、人畜などの「生贄」の記念碑(墓石)だと推測出来ます。 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔黒又山〕 _________________________________________ 特集【鹿角の通説異説】検証③ ◆地勢 : ◆「スバリ」とは、すぼまる(窄まる)と言うことで、地形的に細く狭まった所で、 例えば①尾去沢下新田の旧藩境、②十和田末広の女神男神、③八幡平温泉郷の志張温泉元湯、 ④八幡平夜明島川若狭などが想定されます。 即ち、「スバリ」とは換言すると、この世(人間社会)と 未知の世界(夢の世界・幻想界・黄泉の世界・鬼畜の世界)の 門口だと考えられます。 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔スバリ〕 ____________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証④ ◆地勢 : 鹿角は湖であった(海抜200メートルランドマーク)。 即ち、大昔、鹿角盆地は、男神女神辺りで堰き止められた【堰止湖】であったと推定出来ます。 何故なら、現在海抜200メートルの所が「ランドマーク」を記しているからです。 ◆海抜200メートルランドマーク ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔海抜200メートルランドマーク〕 ____________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証⑤ 地名 : 堀内(ほりない)は鉱山のことなり 地名 : 堀内とは ◆地名 : 堀内(ほりない) 堀内(ほりない)とは、鉱山に由来する地名だと思います。 【1】十和田大湯堀内堀内川上流に廃鉱があります。 【2】八幡平夜明島杉沢国有林内に、小堀内沢・大堀内沢があり、廃鉱らしい跡があります。 此処で産出した鉱石は、八幡平馬見平(曙牧場)を経て八幡平小割沢へ運ばれたものと思います。 小割沢には長者が居て、せっせと鉱石を製錬していました。 ◇参照 : へそこだま物語 【3】小坂町小坂堀内沢に堀内鉱山がありました。昭和22年休山。 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔堀内(ほりない)〕 ___________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証⑥ 地名 : 目名市(めないち)とは免内地のことなり。 ------------------------------------------------- ◆目名市(めないち) ◆地名 :目名市(めないち) 目名市(めないじ)とは、租税など特定の課役を免除された田地=免内地のことと思います。 【1】八幡平黒沢石鳥谷界の「めないじ」より上流は免内地です。 【2】岩手県八幡平市目名市もその例。 【3】秋田県大館市岩瀬越山の目名市もその例。 【4】一色田(いっしきだ)とは、一品だけ献納すべき田地(土地)のこと=「石木田」(花輪鏡田辺りらしい) ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔目名市(めないち)〕 _________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証⑦ 食 : 膾(かい かゆ きゃ けぇ)とは秋田鹿角の郷土料理のことです。 【1】カヤキは、膾焼きのことだと思います。 【2】「けえ」は、膾の意味が含まれていると思います。 【3】つまり「け・けぇ」の汁も、膾の汁だと思います。 ◇参照 : 食 : 膾(かい かゆ きゃ けぇ) ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔膾(かい かゆ きゃ けぇ)〕 ______________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証⑩ シナノキのこと ------------------------------------------------- ◆八郎太郎と漁業用ロープ(繊維) 八郎太郎の伝説の主題は「まだの木(シナノキ)の皮」です。 昔、八郎太郎はシナノキの皮を採取し、八郎潟の漁業用ロープの原料として 供給していたのです。 シナノキの皮は、水に強い(腐食しない)とされています。 八郎潟の漁民は、そのロープを使うことで漁を盛んにし、以て八郎太郎は、 八郎潟の神様として祀られているのです。とっぴんぱらりのぷぅ。 ◇参照 : 八郎太郎と漁業用ロープ(繊維) ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔シナノキ〕 _________________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証⑪ 七時雨山のシナノキ並木 昔は、シナノキ(まだの木)の樹皮を繊維に加工し、荷造り縄に撚ったものと思います。 よって、岩手県七時雨山(ななしぐれやま)にシナノキの並木の場所と、 そのことについて忖度(推理)してみたいと思います。 即ち、八幡平市七時雨山の中腹の【旧鹿角街道】沿いに、シナノキ巨木の並木が二ヶ所あります。 ------------------------------------------------- ◇参照 : 七時雨山のシナノキ並木 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔七時雨山のシナノキ並木〕 ______________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証⑪ 錦木塚物語のこと ◇参照 : 5300錦木塚物語 ◆政子姫は当時草木染に用いる媒染剤=サワフタギ(錦織木)の「灰」を必要としていました。 サワフタギは奥山に生えているので、草木の若者が売りに来るのを今か今かと待っていました。 運よく赤森(小坂川と大湯川の合流点)近くで開かれるマルシェで知り合ったのでした。 ところで錦木塚物語のこのような男女の出会い物語は、万葉集にもあります。 ①紫は灰指すものそ海石榴市(つばきち)の八十(やそ)の衢(ちまた)に逢へる児や誰 〔作者未詳・巻十二 - 三一〇一〕 ②たらちねの母が呼ぶ名を申さめど路(みち)行き人を誰と知りてか 〔作者未詳・巻十二 - 三一〇二〕 言い換えれば万葉期における「灰」に因む「つばきち(=歌垣)」での 男女の出会い物語を当時の文化人達が鹿角へ持ち込んだものでしょう。 ◇参照 : Web「海石榴市ツバキチ」 さて「錦木五木」とは紅葉の美しい木のことされています。 サワフタギは普通マユミ・コマユミなどと群生しています。 マユミ・コマユミは紅葉が美しく山錦と呼ばれています。 サワフタギは紅葉しないので目立たないがこれらの一群が紅葉を呈しています。 よって「錦木五木」とはこれらのことと思います。 ◆因みに「山錦」と「ニシキギ」とは別物です。天然の「ニシキギ」は鹿角では見たことがありません。 _______________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証(12) 大湯環状列石の謎/有名になれば丸裸 ◆①大湯環状列石の組石「石英閃緑ヒン岩」は、米代川支流大湯川大河原集落付近の川原石です。 ◇組石採取推定位置→(GeoHack) ②居住地 当時の大湯環状列石の人達の居住地は、組石採取地点と万座環状列石 の間の崖(万座岩山)でした。 即ち、「万座」と言う岩山に住んでいました。 万座岩山には、清水が流れていました。 万座岩山は、其処と大湯川左岸上流方向集宮倉沢風張~大湯盆地へと 繋がっていました。 集宮(あつみや)も、もともと岩山で、その上流の大湯盆地は、 天然のダム湖でした。 集宮岩山は、その後流失しました。今は集宮にその痕跡を見ることが出来ます。 ◇参照 : FPD 01大湯環状列石の謎/有名になれば丸裸 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔大湯環状列石の謎/有名になれば丸裸/石英閃緑ヒン岩〕 ___________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証(13) 大湯環状列石の謎/円筒式土器の用途 ④殯(もがり)に際し、数日間、建物に死体を安置するときに発生する 悪臭を消すために、土器の中に薬草香草を入れて囲炉裏の傍に据えて 燻したものと思います。 即ち、郊外に竪穴住居を建てて殯のために、短期間居住したのでしょう。 ⑤また及び夏季、郊外の祭場に竪穴住居を建てて天変地異除けの祈祷の ために寝泊まりし、その時ツツガムシなどの病害虫(魑魅魍魎) 侵入防止のために、同じく土器の中に薬草香草を入れて囲炉裏の傍に 据えて燻したものと思います。 ◇参照 : PDF 02大湯環状列石の謎/円筒式土器の用途 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔円筒式土器の用途〕 ____________________________________________________ ◆特集【鹿角の通説異説】検証(14) 03大湯環状列石の謎/どばんくんは六面体 ◆世界遺産「大湯環状列石」と同じ土壌の中から出土したとされる 土版(愛称どばんくん)は、世界的に大変貴重な出土品で、唯一無二? とも言われています。 ご案内のように、どばんくんは六面体の形をしています。 印されている「六」の数値は、時間軸を表していると考えられています。 六面体⇒「十干十二支」と関係があるかもしれません。 とろろで、私は、円環思想に関係があると思います。 地元大湯郷土研究会でも、大湯環状列石について、円環思想のことに 言及されています。 ◇参照 : PDF 03大湯環状列石の謎/どばんくんは六面体 ◇参照 : PDF鹿角の通説異説〔どばんくんは六面体〕 _____________________________________________ ◇芦名沢の【岩穴・衣掛け岩】と【錦木塚石】とは同じ種類の岩石です。 芦名沢の観音さま(十和田山根) ------昔は百姓達にとって大切なものであった馬を欲しい人達は、 このお堂に馬を連れて集まって来て、沢山の良い馬が授かるようにと、 絵馬エマを競って奉納したものです。 このお堂は、こうした絵馬が沢山、昔のまんま残っているので有名です。 このお堂の近くには、慈覚大師が仏像を彫るときに籠ったと云う岩穴や、 慈覚大師が身を浄キヨめるために、水垢離ミズゴリを執ったとき着物を 掛けた衣掛けコロモガケと云う大きな岩が今でも残っています。 ◇参照 : 5901芦名沢アシナザワの観音さま(十和田山根) |